 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る腸は第二の脳と言われて久しい。腸と脳がタッグを組んでいるという話はもはや周知の事実だ。少なくともマウスの実験では、腸内細菌が行動にまで影響を与えているという証拠は着々と集まってきている。
今回新たに発表された研究によると、腸内細菌を取り除いたマウスや、無菌室の中で育ったもともと腸内細菌がいないマウスは、一度植え付けられた恐怖を忘れられないことがわかったという。
通常なら、そこに恐怖がないとわかれば消えていく恐怖心
通常、動物は環境が変化すれば行動を変えて適応する。そのよく知られた事例として「恐怖消去学習(恐怖条件付け)」というものがある。
動物に音や光などの無害なものから嫌な連想をするよう教え込んだとしよう。しかし、その連想がもう当てはまらないことがわかれば、動物はそうした印象を忘れることができる。
もっと具体的に説明すると、たとえばマウスにある音を鳴らすと同時に電気ショックを与えてみる。するとマウスは音を聞いただけで、恐怖で身をすくませるようになる。
そして今度は音が鳴っても電気ショックを受けないという経験を繰り返しさせてやる。すると、音は特に危険ではないのだということを学習し、やがて音が鳴ってもマウスは怯えたりはしなくなる。
お腹の中に健康的で多様な腸内細菌を持つマウスなら、危険がないことがわかればそこで恐怖心はなくなるのだ。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る腸内細菌をとりのぞくと恐怖を忘れられなくなるマウス
ところが、抗生物質で腸内細菌を取り除いたマウスや、無菌室の中で育ったためにもともと腸内細菌がいないマウスになると話が違う。
そうしたマウスは恐怖を忘れられない。どんなに音が安全であると教えても、相変わらずそれを聞けば身をすくめてしまう。まるでPTSDの患者のようだ。
なぜ腸内細菌がいなくなると恐怖を忘れられなくなるのだろうか?
これまでの研究によって、迷走神経と適応免疫系が腸と脳をつなぐ経路であることが明らかにされてきた。
そこで米コーネル大学の研究グループは、無菌マウスの迷走神経と免疫系を調べてみた。ところが、それらは特に問題なく機能していたのだ。そのふたつの経路はシロということだ。
腸内細菌を取り除いたマウスの遺伝子が変化
そこで研究グループは次に、脳の「内側前頭前皮質」という恐怖消去学習に大きな役割をはたしている領域で発現する遺伝子を見てみることにした。
すると腸内細菌を取り除いたマウスは、「シナプス(神経細胞同士の結合部)」の組み立てと統合に関連する遺伝子が過剰に発現していることがわかった。
また恐怖の記憶を保存しておく領域の「興奮性ニューロン」の密度が高い一方、消去学習をうながす領域の興奮性ニューロンの密度が低いことも判明した。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見るシナプス可塑性が低下し代謝産物も大きく減少
さらに恐怖消去実験の最中に脳撮像検査を行なってみると、無菌マウスは「樹状突起スパイン」の形成が少なく、スパイン消去が多いことが確認された。
樹状突起スパインはシナプスの半分を形成し、ニューロン結合には不可欠なものだ。つまり腸内細菌は脳細胞の中の遺伝子発現を左右し、シナプス可塑性を低下させていたということになる。
その結果として、学習が阻害され、恐怖を忘れられなくなっていたということだ。
さらに腸内細菌が分泌する代謝産物を確かめてみた。この検査からは、無菌マウスの脳脊髄液の中で、とりわけ4種の代謝産物が大きく減少していることがわかった。そのうちふたつは人間の精神神経疾患にも関係があるとされるものだ。
腸内細菌と神経の共進化の謎
とはいえ腸内細菌と学習との関係は完全に明らかになったわけではない。恐怖心に取りつかれているからといって、くれぐれも安易に自己流で流行りの便微生物移植をやって安心してみようなどとは思わないことだ。
共進化を遂げてきた腸内細菌と神経系と哺乳類の行動との関係をもっと詳細に定義する必要があると研究グループは述べている。
この研究は『Nature』(10月23日付)に掲載された。
かつて日本人は世界一の怖がりであり、多くの人が恐怖遺伝子を持っているという報道があったが、もしかしてそれって腸内細菌が関係している?
References:Are you a mouse who can’t let go of fear? Your microbiome might be the problem | Ars Technica/ written by hiroching / edited by parumo

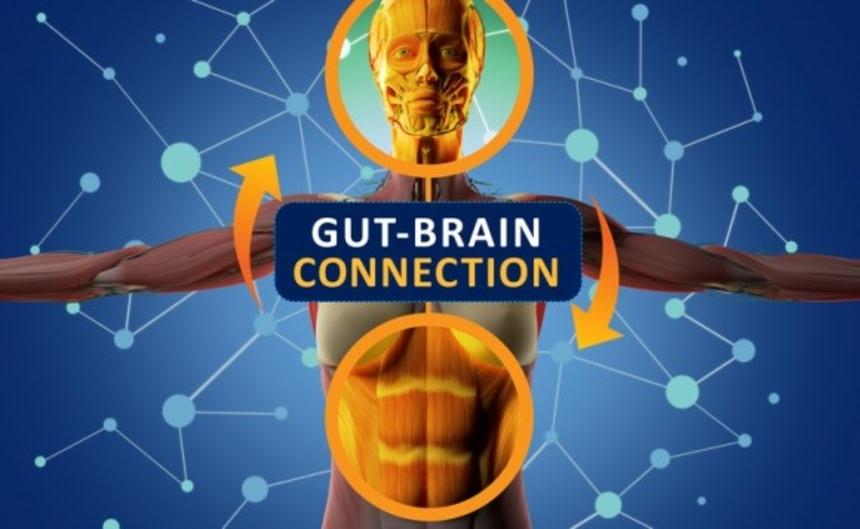













お腹が弱い人が大抵怖がりというかメンタルが弱いことと関係してる?
>>1
腸内環境が悪いと感情の起伏が激しくなるからあながち間違いではない。
が、感情で言わせてもらうとお腹が弱いからって怖がりメンタル弱いというイメージを勝手に当てはめられるとムカつく。
それは私はお腹が弱いから。
しかしムカつくのは人間として当然の考え方であることのはご理解いただきたい。
じゃないとお腹が弱くないこれを読んだあなたは考えなしで早とちりが過ぎるトンチンカンと思ってしまうから。
何かを食べたいって思うのは腸内細菌がそれを欲しているからなんだぜ。
食べる物で腸内細菌の種類もその割合も変わっていくんだ。
脳だけ移植してサイボーグになるSFあるけど実際やろうとしたら腸も神経系も全部そっくり
移植しないとその人格になれないんじゃないかと思った。
メンタル系の治療に活用出来るかな?
腸が健康な状態であれば脳はその機能の一部を腸に預けるようになってるが、
腸が不健康な状態になると脳が全てを処理するようになって機能不全を起こすって事なのかね
胡麻を食っているせいか少々の恐怖は気にしてない
腸内細菌元気なりまくってるのかな
腸だけじゃないよ。皮膚と表皮常在菌の作る生態系、表皮フローラだって体内や神経系と関連があると示唆されている。何故か腸ほど注目されてないけど、皮膚の研究者たちは皮膚を臓器のひとつと考えていて「皮膚は第二の脳だ」とさえ言う人もいる
腸、超~怖~い
一度でもアタった食べ物とかを、
思いっきり拒否するようになるのは、
それが原因だったりするのですかね?
腸も、
「あれの処理はマジ大変だった……」
みたいな。
むしろ細菌に操られているのでは
とすると、「トラウマ」も原因は腸にあるわけか。
何にしても、「IBS(ストレス性腸過敏症候群)」の例を見ても、脳と腸が密接に結びついているのは、確かなわけだし。
その原因が、「腸内細菌である」こういうことね。
これは間違いなくあると思う。
自分も1年中合成甘味料がぶ飲みしてた所、慢性的な胃腸の不調とともに鬱病になった。
ついでに社会恐怖症になったし、自律神経失調も起こした。
特に精神的に落ち込んでいる時に胃腸の調子が悪くなる事が多かったから、試しにビフィズス菌サプリを毎日飲むようにしたところ、3日で胃腸の不調は無くなった。
1ヶ月経って、気づいたら精神疾患も何故か全快してた。どうも因果が逆だったらしい。
※13
興味深い報告ありがとう。
とりあえず、今日近所の薬局で乳酸菌のサプリ買ってきましたよ。