 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見るまた植物の新たなる一面が明らかとなった。科学者によると、野生の草は進化を迂回するために、近くにいる草から遺伝子を盗んでしまうのだそうだ。
つまり、草は自然なやり方で、自らを遺伝子組み換えしてきたということだ。
親子間以外の遺伝子の継承
ダーウィンが進化論を唱えて以来、そのほとんどは、遺伝子が親から子へと受け継がれる中で生じる、同じ血族内での自然選択を対象に考察されてきた。
しかしイングランド、シェフィールド大学の研究者は、様々な草がこの法則を破っていることに気が付いた。
彼らは「遺伝子の水平伝播」という進化の抜け道を使い、直接は関係のない遠く離れた種から手に入れた遺伝子を利用してきたようなのだ。
「草はまさに遺伝子を盗むことで、進化のショートカットを行なっているわけです」とルーク・ダニング(Luke Dunning)博士は話す。
「スポンジのように、近くにいる生物から役に立つ遺伝情報を吸収しています。こうすることで、普通なら数百万年もかかる適応のための進化をすることなく、仲間との競争に勝ち、危険な生息環境で生き残ることができます。」
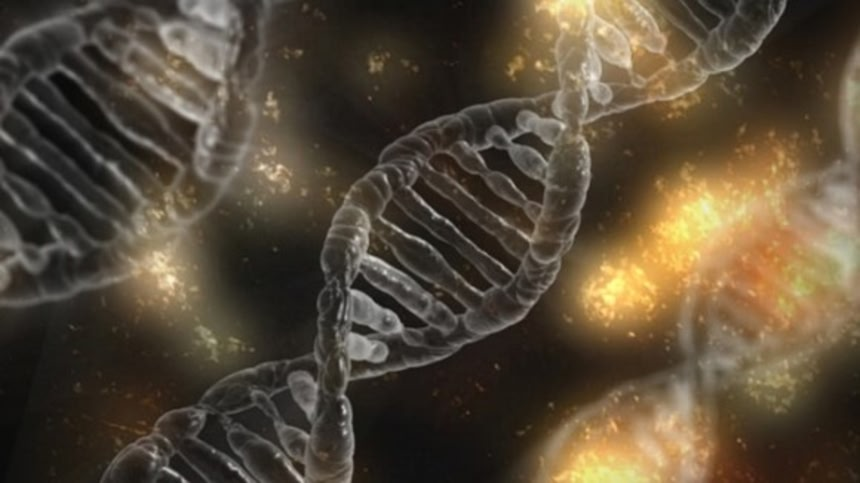 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る様々な草が他の草の遺伝子を盗んでいる
ダニング博士らは、アフリカ、アジア、オーストラリアに自生するアロテロプシス・セミアラタ(Alloteropsis semialata)という草のゲノムを、ほかの150種の草(米、トウモロコシ、キビ、オオムギ、タケ等)と比較してDNA配列に類似点がないか調べることで、水平伝播で獲得された遺伝子を特定した。
さらにアジア、アフリカ、オーストラリアの熱帯・亜熱帯地域に生えているアロテロプシス・セミアラタを調べ、こうした水平伝播がいつ、どこで起きたのかも調査した。
「遺伝子の偽造は、周辺環境に適応し、生き残る手助けとなる大きなアドバンテージを草に与えます。そして、今回の調査では、こうしたことがアロテロプシス・セミアラタだけではなく、ほかのいろいろな草からも検出されました。」
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る他植物の遺伝子を盗み出し組み込むアロテロプシス・セミアラタ
image credit:Flower of the grass species Alloteropsis semialata
天然の遺伝子組み換え技術
ダニング博士は、この発見が遺伝子組み換え技術について社会に再考を促すことになるかもしれないと話す。なにしろ、草は自然に同じようなプロセスを利用して、自らを遺伝子組み換えしていたのだ。
また、こうした仕組みをきちんと理解することで、自然界に流出した遺伝子組み換え作物から遺伝子が水平伝播し、除草剤に耐性があり、繁殖力も強い、いわゆる「スーパーウィード」が出現することを防ぐヒントが得られるかもしれないという。
今後のステップは、この現象の背後にある生物学的なメカニズムを解き明かすことだそうだ。
この研究は『Proceedings of the National Academy of Sciences』に掲載された。
How our plants have turned into thieves to survive/ written by hiroching / edited by parumo














草wwwww
具体的にどうやって「盗む」のか
動物では起こり得ないのか
人為的な遺伝子組み換えとの相乗でどれくらいの繁殖が見込まれるのか
色々と好奇心が刺激されて面白い!
※3
虫が別の植物をかじった口でかじったところに他の植物の欠片が傷口から混入したりってとこでないかな
ちょい前にコウモリとかの高等生物も遺伝子情報を横で運ぶって記事もあったし、それと根っこは一緒だと思う
>>26
遺伝子が同じだと自家受粉を防ぐ為に雌花に付いた花粉から伸びる管が途中で止まるとは聞いた
物理的に短くなれば官が少し伸ばせる
先端部分が無くても
違う種でも官が伸びるなら
確かに交配出来そう
>>3
ファージ等のウィルスは遺伝子を運ぶ事がある
詳しく見たいなら赤痢とO-157の事を検索すると出るかも?
このようなウイルスを遺伝子組み換え技術に適用している
その事を書いてるのかも知れないし
脊椎動物の免疫が無いなら交配が可能と書いてるのかも知れない
星雲賞でも狙っているのかw
説自体はわくわくする。
ぜひ具体的なメカニズムを!
遺伝子どころか、生物そのものを取り込んだ歴史があるのが驚愕 そう葉緑体ですよ
しかも、この葉緑体の取り込みは別件で複数回起こっているという事実
そして葉緑体を取り込んだ、生物がさらに取り込まれて進化したこともあるという、、
ミドリムシは取り込みを2回した生き物で、その証拠が三重の細胞膜として残されてるのですよ
※自然界で遺伝子組み換えがおきているからと言って、安易な人工遺伝子組み換え植物の作成が許されたわけではないので、お間違えのないように!
目は元々、植物プランクトンの光を感じる細胞を、動物プランクトンが食ったことで出来たってNHKスペシャルでやってたよな。
ただ、脊椎動物の目は脳の一種なのに対して、イカやタコを含めた軟体動物のは皮膚の一種。
※8
脳になる元の細胞が皮膚まで到達して共同作業で出来上がるから、水晶体やガラス体は皮膚由来、網膜と視神経は神経由来の細胞でできている。
異能力バトル系漫画のラスボス能力やんけ!
やはり生き物の原点にして頂点は植物なんやな。
バクテリオファージによる遺伝子の水平伝搬を知らないのか まあ確かに高校で生物を選択しないと知る機会はないかもしれんね
動物どもは、なにか自分たちが出来ないことがあると、決まってそれを「変則的」とみなす。自分たちこそが「標準」であり、「正統」なのだと信じて疑わないのだ。
だが地球の生命体は、ずっと自由にーーー「水平」にーーーゲノムをやり取りしてきたし、ゲノムもまた、ずっと自由に生命体の間を行き来してきた。
後生動物、とりわけ脊椎にすがって生きている連中の方こそが例外的なのであり、ゲノムをめぐる一種のコミュニケーション障害をきたしているのだ。
phys.orgの記事が悪いけど
元の論文は盗んでいるとか言っていない
遺伝子水平伝播のことなんだけど
動けない植物がどうやって遺伝子を盗むことができるのか
受動的に他の種の遺伝子を捕獲してるだけ
chloroplast captureみたいなもんで
別にとりわけて騒ぐことのほどではないと思う
生き残るために遺伝子を盗み合っていると考えるより、共存するために遺伝子を分け合っていると思いたいなぁ・・。
やっぱり記事書いてる人より、コメント欄の方が博識な人が多いな、、
>>14
記事を作成するのに必ずしも最先端の専門知識が必要というわけではない
好奇心を刺激する文章、翻訳の仕方とかね
それとワクワクするイメージ画像や記事全体の構成
カラパイアのスタッフは本当にワクワクさせてくれる!専門的な知識の紹介や、海外の英語サイトでしか詳しく載っていない科学研究を紹介してくれるのはほんとうに貴重なことだよ
よく知られているのがライ麦でしょ
ライ麦は小麦畑に生えてた雑草だった
そのうち、小麦に似たものが出始めて除草から免れて繁殖
水平伝播があるから逆に遺伝子組み換え植物を外界に晒してはいけないというのもあるね。まあ遺伝子組み換え植物を食べることを過剰に怖れる必要はないんだけど何が起こるか分からない面はある。何かのスイッチで突然思わぬ毒性を発揮する可能性もある。もっと怖ろしい可能性もあるかもしれない。我々はまだ気軽に遺伝子をいじっていいほど遺伝子を理解していないのだ。
>>16
毒性のある観賞用植物から種を取る目的の食用植物を離して置かないといけない
むしろ種芋が取れるようにして遺伝子の交雑を防ぐ為に遺伝子組み換えが効果的な解決策になる
>>16
確かに安易に野に放つべきじゃないよね。
「遺伝子組換え」をどう捉えるかだけどさ、多くの人は「怖い!」ってイメージで研究室で人為的に操作された物は怖くてそれ以外は安心安全だと思ってる。
でも交配ってのは遺伝子の組み替えなわけで、出来てみないとどう組み変わったかわからない。
遺伝子操作によるものは一部、1つだったりするのに比べて交配だと大雑把に半分が組み変わるとしてどっちが元よりより離れたものか考えると複雑。
遺伝子の水平伝搬や量子の情報伝達、はたまた離島のサルが道具を使ってエサを採るようになるのと同時期に、情報が隔絶されているはずの別の島のサルも道具を使いはじめる不思議。これって全部同じものなんやろか?それともワシが自分に都合のいい情報だけをピックアップしとるだけなんやろか?
※18
遺伝子の水平伝播=細胞、ウィルスレベルで実際に起っている
量子テレポーテーション=素粒子レベルの現象、いくつかの実験が成功している。
離島の猿=「百匹目の猿」現象のことかな?これは創作なので実際には起こっていない。
そもそも、接ぎ木できる事が驚異的。
>>19
脊椎動物の拒絶反応の研究では
鶏にウズラの頭と胸腺の移植で拒絶反応の発生を防げた記録があるらしい
鶏がピヨピヨ鳴いたら満足出来る人も珍しいと思うけど実用出来るのか?の前に実用した時に発生する問題の予測と対抗手段を研究したようだ
※19
それは単に植物に免疫系が無い為です。
自己と他者を細胞レベルで区別する
仕組みが無いので、何かくっついた?
位の感覚で繋がってしまうのです。
なんでもかんでも接ぎ木出来る訳でも
無いのは、細胞の浸透圧とか必須栄養素の
微妙な違いとかが影響する所為かと。
蓮と睡蓮が似てるけど(蓮は水面から出る)、全く別モノであるというけどコレかな?
でも伝播というか、遺伝子の横の移動が想像がつかない。
いくつか例を上げてほしいものだ。
>>20
赤痢の毒を作る為の機能⇒Oー157
毒を作れるO-157の完成
ファージ等のウィルスは感染した細菌を増殖の為に食い潰すが
遺伝子を運ぶ事もあるようだ(ざっくり)
ソ連が使うのを辞めたのも抗生物質を作る事が出来たからだけでは無さそうだ
※31
ありがとう。
でも、それ植物じゃないし。
その細菌の戦略は知ってました。
これは盗むんじゃなくて
お互いに情報を根を通して
交換してるんじゃないかね
共生してるほうが
近いと思う
普通に根から吸収した物を再利用してるだけ
人間でも食べ物を食べたら起こり得る減少。
>>22
遺伝子に?
副生成物の混じった枯れ葉剤被った食べ物を食べれば遺伝子に変化は起きるだろうけど
特定の生き物から遺伝子を引き継いでる事にはならないな
この論文の新しさは、遺伝子の水平伝播があるってことじゃなくて、淘汰圧のかかるような遺伝子が真核生物レベルで流動してるってところだね
簡単に可能なら生物は他個体から積極的に適応的遺伝子を盗むように進化するだろうし、逆に自分は奪われないように選択圧がかかるだろう
これは間違っているな
草どうしで遺伝子情報を盗む能力があるのなら
全世界の草は1種類になっていなければおかしい
生物誕生後何億年たっていると思ってんだ
>>24
自然に遺伝子組み換えと同様の交雑が起きる事は稀な事
加えてファージが運べる遺伝子はその一部でしかない
植物によっては交配をしなくてもクローンと同様に次の世代に遺伝子を引き継ぐ(芋)
>>24
適応すべき環境が地域によって異なるから、植物は多様性は保たんじゃないかと。
イネ科作物の雑草が栽培品種に対するミミクリーを示す原因が人為選択だけじゃない可能性があるのか
カニンガムの法則で賑わってますね。
しかし研究中の事案に対しては
正しい回答が集まるとは限らない。
とうもろこし(遺伝子組み換え作物ではない)※自ら遺伝子を組み替える場合があります。
盗むって表現が実に傲慢な人間らしい表現だと思ったわ
共生だろどう考えても
いつ、どこで、はどうでもいいんだけど
どうやって、が知りたい
脊椎動物だって普通にウイルスに遺伝情報を挿入されて、それが時には癌の引き金になったりもするわけだけど(タスマニアデビルの感染性の癌とかね)、植物においてはその辺のことがもっと頻繁かつ広範に起きている、ってことなのかな。
植物たちの、枝一切れからでも本体が再生するような自由度の高さを見るに、一部の細胞に新しい性質が備わった時、脊椎動物に比べると、その変化が個体(という概念が植物にうまく当てはまるかも微妙だが)の死に直結しづらくて、結果的に新しい性質が受け継がれやすいのかもしれないね。
微生物単位で起こる取り込みが、植物レベルでも起こるってこと?
関係ないけど東南アジアあたり行って現地の植物みてると
静かな生き物どころかキメラだなって思う、毎回
元々ライ麦なんかも意図的には植えていない野生種の変異が混ざり込んで他の麦不作の場合でも割と採れる事から気候の厳しいところで積極的に植えられるようになった経緯もあるね。
イネ科は割と混ざりやすい感じがある。
ファージなんて外部要素使わんでも細菌は直接に遺伝子の水平伝播やってるから知識自慢したい人たちはそっち挙げようぜ
高校生物でもちゃんとやったはず
植物はシアノバクテリアを取り込んで葉緑体とし、動物は何を取り込んだか忘れたけどミトコンドリアとし、細菌は近くの遺伝子を取り込んで進化して…
と思ったけど、植物→植物の遺伝子の移動があるとはびっくりだ。メカニズムが解明されて、心配されてる食糧難に新たな対抗手段が見えてきたりするといいな
恐ろしいと思っているのは、種苗会社が開発した遺伝子組み替え作物に特許をかけて、それが水平伝播した植物に対しても、うちとこの特許の侵害だと主張してくるところ。
具体的な方法は知りたい
評価制度がつくようになってからか、コメント読むのが面白い!
一部の線虫が遺伝子のキャリアーだってのは知られているし、NHK「人体~」でもメッセンジャー物質は食物からの摂取でも機能するってやってたね。
カニバリズムにおいて「相手の力を取り込む」ってあながち間違いじゃなかったりして。
ごく稀に食物からも遺伝子が入る事がある?とか
食虫植物なんて虫から遺伝子取り込んで…ワクワクしてきた
作物の品種改良の過程でも他から遺伝子が紛れ込んでそうなった可能性もあるのか