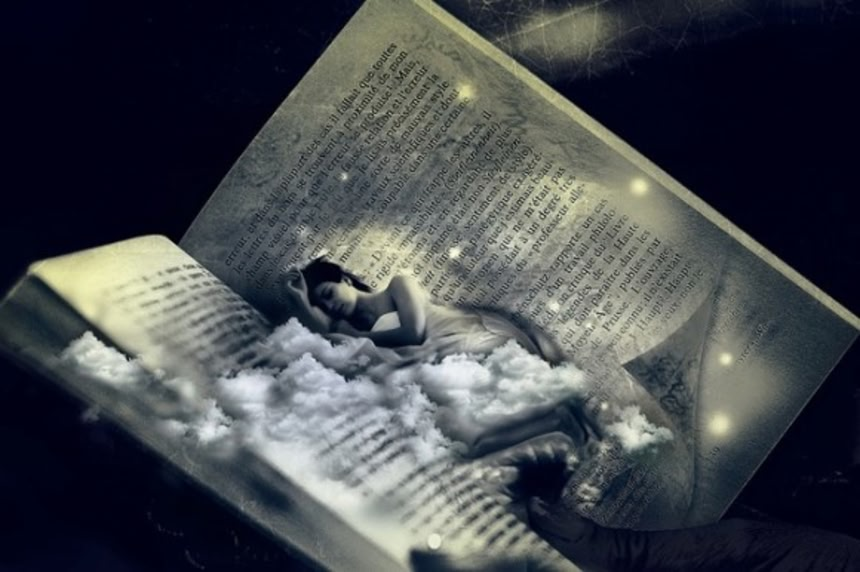 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見るあなたは夢をよく見るほうだろうか? あまり見ないほうだろうか?
基本的にあまり夢を見ないという人は、寝室が寒すぎたり、暑くて寝苦しかったりする場合が多いという。
スイス、ベルン大学の神経科学者によれば、脳は夢を見ることよりも、まずは体温調整を優先するらしいのだ。だから、夢を見るには、ある程度快適な温度の中で眠らなければならない。
寝ているだけでも結構大変なレム睡眠
では夢を見るメカニズムについてまずは見ていこう。
夢を見やすいのは、急速眼球運動睡眠――いわゆる「レム睡眠」と呼ばれる睡眠状態のときだ。
このレム睡眠、確かに睡眠であるのだが、夢という心の劇場を公演するために結構な労力を払っている。
それがアクション映画さながらのスリリングな夢だったりすれば、呼吸は上昇し、目は想像上のキャラクターを追い続け、手足はまるで戦おうとでもするかのように緊張する。
わざわざそんな大変な思いをして夢を見なければならないからには、それなりの理由があるはずだ。一般的な仮説では、夢は日中に起きた出来事を心の中で処理する方法だと説明されている。
夢の最中、体温調節は抑制される
じつは人間のような温血動物が夢を見るとき、体温調節は抑制されている。レム睡眠に入ってしまうと、体の重要な部分の体温(中核体温)を維持するための、発汗・震え・呼吸の速まり・顔の高潮といった機能があまり効率的になされなくなる。
そのせいだろうか、寝室が暑すぎたり、寒すぎたりすると、なかなか夢が訪れない。快適な状態でなければ、脳は休憩している状態からレム睡眠にスムーズに移行してくれないのだ。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る夢と体温調整をいっぺんにはできない
「このレム睡眠中の体温調節機能の喪失は、睡眠の一番奇妙な点の1つでしょう」とベルン大学の神経科学者マルクス・シュミット氏は話す。
少し論理を飛躍させるなら、こう考えることができるだろう――その日の出来事を夢によって処理するか、あるいは体が凍えたりゆでダコになったりするのを防ぐために夢を諦めるか、脳はどちらかを選んでいる、と。
なぜなら、両方をいっぺんにはできないと考えらえる理由があるからだ。
光遺伝学で遺伝子のスイッチを操作
この仮説を検証するためにシュミット氏らは、マウスの脳の奥深くにある「視床下部」を調べてみることにした。ここは体温調節とノンレム睡眠の両方に関連する部分だ。
「メラニン凝集ホルモン神経細胞」がレム睡眠に関与していることはこれまでに知られている。
そこで実験では、メラニン凝集ホルモン受容体がコードされているマウスの遺伝子のスイッチを、光遺伝学的な手法によって自由にオンオフできるよう改変した。
快適な暖かさがレム睡眠の秘訣
それから普通の実験用マウスの周囲の温度をいろいろ調節してみると、快適な暖かさに近くにつれてレム睡眠の長さが伸びることが明らかになった。
しかしメラニン凝集ホルモン受容体を停止させたマウスの場合、そのような変化は起きず、まるで視床下部が外気の温度に無関心になってしまったかのようだった。
また受容体のスイッチを入れたり切ったりすることで、気温に応じてレム睡眠になるかどうか管理するための鍵は、メラニン凝集ホルモン神経細胞であることが確認された。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見るエネルギー負荷の高い作業の同時進行は避ける
体温の繊細なコントロールと夢という脳の作業は、哺乳類が生きるためにやらねばならない作業の中では特にエネルギー消費の激しいものだ。
そのために、この大事な2つの作業を同時にやってしまえば、どこかの時点でそれぞれに支障が出るという可能性は十分に考えられることだ。
眠っている間、多少寝苦しいからといって、起き上がって別の場所に移動するようなことはできない。だから体はその場所で中核体温を維持することをまず優先する。
しかし、それなりに快適で、労せずして体温を維持できるような状況では、夢を見て記憶を処理することにエネルギーをさく。
だから、今晩久しぶりに夢を見てみたいと考えている人がいれば、寝室の温度が快適かどうか確かめてみよう。
この研究は『Current Biology』(5月30日付)に掲載された。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る人はなぜ夢をみるのか?その謎を解くために様々な研究が行われているが、まだまだ完全に解明されたわけではない。
実は我々は毎日夢を見ているのだが、目が覚めたときにそれを覚えていないので、夢を見ていないと勘違いしているふしもあるという。
夢を見たいという人は、とりあえず室温を調整し、快適な睡眠を心がけてみよう。そして、寝る前に「今夜は絶対夢を見る」と強く考えると良いという。夢に意識を向けることが以外にも効果を発揮するというので、試してみると良いかもしれない。
・どういう人が夢を見やすいのか?性別・年齢・性格など6つの要因から分析した夢を見やすい人 : カラパイア
追記:タイトルを一部修正して再送します(2019/07/21)
References:/ written by hiroching / edited by parumo














起きたときに暑くて汗だくになってるようなときでも夢は見る(覚えてる)よ。体感、不快なときは、快適なときより悪夢を見る割合が多い気がする。
寒いと怖い夢をよく見る
夏場にエアコン切った部屋で寝ていると、悪夢で起こされるから警告なんだと思う
※3
夏場でエアコン切った部屋で寝ていると、最悪永遠に起きられなくなったりするからね。
今時期は。
そういう意味では、その「悪夢」はいい仕事をしているのかもしれない。
暑かろうが寒かろうが毎日夢見てる
どんな内容かも覚えてる
でもほぼほぼアクションスターみたいな内容じゃなくて日常を過ごしてる夢だな
ウチのワンコとニャンコ達は、走ってる夢を見て足を動かしてたり寝言を言ったりしてる。
適温だと体が感じてくれてるんだね。嬉しいな。
※5
ごめんなさい
+押すつもりが-押しちゃった
疲れた日の夜はあまり夢を見ない気がする
ん?快適な方が見れるって話なのか
暑苦しい時以外の夢は記憶に残って無いな
見てるかどうかすら怪しい
>基本的にあまり夢を見ないという人は、寝室が寒すぎたり、暑くて寝苦しかったりする場合が多いという。
逆だ
夢を見るのは熟睡できていない証拠
寝室が寒すぎたり、暑くて寝苦しかったりする場合に夢を見る
「メラニン凝集ホルモン神経細胞」
睡眠に関係しているのはメラトニンでは?
※9
リンク先を見たら、
「Melanin-concentrating hormone (MCH) neurons」
で合ってる。
軽くググってみると、
メラトニンも、メラニン凝集ホルモン(MCH)も
主要な働きは、状況に応じて表皮の保護色が変化する動物で
細胞内のメラニン色素を縮小させて色白にすること。
いずれも、ヒトではそんなコロコロ肌色を変える作用は
退化していて遺物的なホルモンだけど、
メラトニンは昼夜で周期的に生産量が変化し
それが睡眠や概日リズムに関わっていて
ヒトにもその機能はよく保たれていることが知られていた。
そして近年、MCHの方にも
レム睡眠・ノンレム睡眠や覚醒の制御に
関わっていることが分かってきた。
…という事のようです。
夢で情報の整理を行っているという説と合わせて考えると、快適な環境で生活している人の方がIQが高くなる可能性があるって事だよな
やっぱり出自って大切なのかなあ
私はほとんど夢を見ないけれど、同じベッドで寝ている夫は毎日のように夢を見ているよ
温度は本当に関係あるのかな?
ホラー系の怖い夢から覚めた直後、布団の中で心臓ばくばくだった事がある。
この記事のお陰で理由がわかった。
なお、内容はとっくに忘れた。
思ったより部屋が暑いとやべぇ夢みる。起きろ!命が危険だ!と体が警告してるみたい。
-20℃~+35℃まで快適だからようわからん
確かに悪夢を見た時は大概汗だくになってるな
最近エアコン入れずに寝たらとんでもない悪夢を2本立てでみたよ・・・
無理せずエアコンつけてます。蒸し暑い・・・
一番の悪夢は朝起きていつも通りの生活をしている夢
気付くのが遅れると、現実で遅れるという恐ろしい夢
タイトル、誤字ではありませんでしょうか?
以外な関係→意外な関係
もし意図的な文字使いでしたら、ごめんなさい。
※21
タイトルだけではなく最後の締めの文末が「夢に意識を向けることが以外にも効果を発揮するというので~」になってしまっている。
あと追記の日付が(201/07/21)になっとるやんけ!
ほんまそそっかしいなwww
寝てる間も脳は活動しているわけで夢は毎日見ている
それを覚えてるかどうかだから不快な方が夢を覚えたまま覚醒するんじゃないかな
これ大分前から気付いて利用してたわ
以下は全て自分の場合だけど、体の一部分、例えば胴体だけ布団に入り、
手足を外に出すなどして温度をずらしてやると夢を見やすくなる
個人的体感だと、四肢を全て外に出すと面白い夢が見られる
足か手どちらか一方の場合だと、触覚や痛覚などが
特にその部位に強く現れる夢を見る
今の時期だとクーラーガンガンにかけて
胴体だけ布団に包まって寝ると夢を見やすくなる
ただしクーラーの作動音がでかい場合は大抵悪夢になる
夢は見れば見るほど、生きるのが辛くなるものだよ