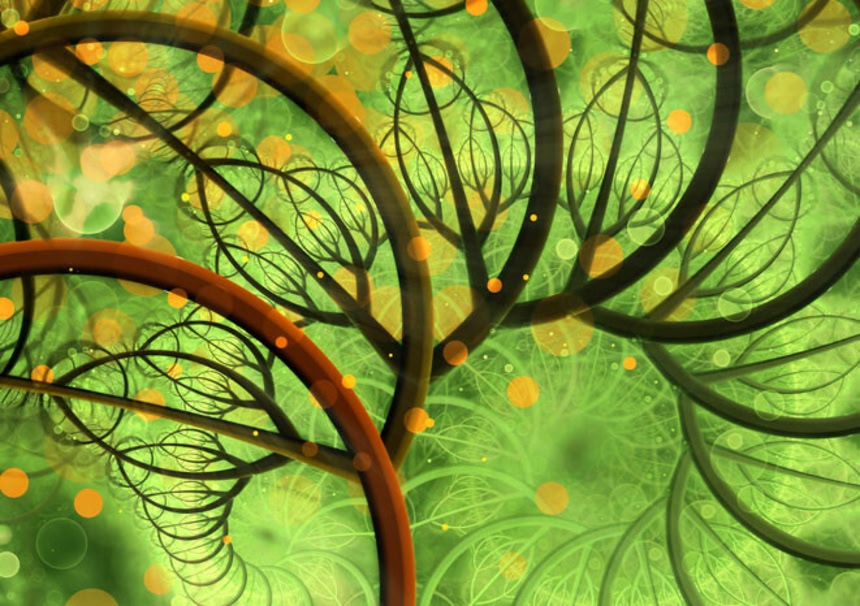 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る地球に衝突して恐竜を絶滅させた小惑星のように、人類の活動が生命の樹(進化の系統属)全体の枝葉を切り落としていると、研究者が警鐘を鳴らしている。
メキシコ国立自治大学の生態学者ヘラルド・セバージョス氏とスタンフォード大学の保全生物学者ポール・エーリック氏によれば、人間の活動の結果による生物の絶滅スピードは、自然に起こる絶滅の35倍の速さであるという。
それは個々の属の生物が果たしている生態系を維持するという大切な機能が失われるということでもあり、私たち自身が生きるための基盤すら崩しつつある。
「ホモ・サピエンスにとって、文明の存続と将来の環境の居住性に対する不可逆的な脅威である」と、『PNAS』(2023年9月18日付)に掲載された研究では述べられている。
地球規模で様々な属の生物が姿を消している
今、地球史上6度目となる大量絶滅ががすでに始まっていると言われている。
海鳥の大量死、海岸に打ち上げられたおびただしい数の魚の死骸、ペンギンの雛の大量餓死、昆虫の激減など、地球上の生物が姿を消している兆候はそこかしこで観察されている。
このような状況を鑑み、メキシコ国立自治大学の生態学者ヘラルド・セバージョス氏とスタンフォード大学の保全生物学者ポール・エーリック氏は、1500年から現在までにどれだけの生物が絶滅してきたのか調べ、その結果を過去5億年と比べてみた。
まず明らかになったのは、我々人類が過去500年で73属の脊椎動物を絶滅に追いやったということだ。
生物の分類における「属」とは、「種」の一つ上の階級のこと。要するに、兄弟や姉妹のように近い関係にある生物でまとめたグループのことだ。
そして500年で73属というスピードは、歴史的に起きてきた属レベルの絶滅の35倍もの速さである。
つまり人間の活動の影響がなければ、同じくらいの属が絶滅するのに約1万8000年かかったということになる。それがたった500年で起きてしまったのだ。
こうした絶滅スピードは脊椎動物だけの話ではなく、植物・菌類・無脊椎動物でも似たような状況だ。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る生物の消滅は生態系全体に影響を及ぼす
それは生物がそれぞれはたしている大切な機能が急激に失われているということだ。セバージョス氏とエーリック氏は、論文の中で次のように説明する。
「6度目の大量絶滅によって、生命の樹が急激に伐採されており、枝全体(種・属・科などのグループ)が、それが果たす機能ともども失われつつある」
私たちが暮らす生態系は、それぞれがまったく無関係に見えても実はつながっている。生物それぞれが独自の役割をはたすことで、お互いに支え合っているのだ。
だから、そうした役割を果たす生物が1つ消えてしまうと、それに頼って生きていた別の生物にも影響が出る。その結果、悪影響が連鎖的に広がっていく。
「私たちも含め、すべての種は、安定した生命の樹の中で一緒に暮らしながら進化してきた」
それは人間にとっても他人事ではない。なぜなら私たちもまた生態系サービスに頼って生きているからだ。
代表的なのは、昆虫がやってくれる受粉だろう。私たちの食を支える農業にとって、昆虫の受粉という生態系サービスが不可欠だ。昆虫がいなくなれば、農業ができなくなってしまう。
また中央アメリカでは、蚊を食べるカエルが少なくなるにつれて、蚊が媒介するマラリアの感染が増えたという報告もある。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る運命を変えることができるのは人間次第
セバージョス氏とエーリック氏によれば、こうした属の絶滅スピードはさらに加速すると予測されるという。
仮に今のままのペースで絶滅が続き、2100年までに現在絶滅が危惧される属がすべて消えたとする。これは1800年からの300年で失われた属の数に相当するのだが、自然に起こる絶滅スピードなら10万6000年分の絶滅量だ。
困ったことに、弱い生物は多くの場合、とても個性的でありながらも見過ごされがちだ。
知らないうちにそうした生物が姿を消すということは、数百万年にわたる進化の歴史がひっそりと失われるということでもある。
失われたものは、そう簡単には戻ってこない。セバージョス氏とエーリッヒ氏によれば、「絶滅で失われた機能の代わりが進化によって生み出されるには、数百万年」が必要になるだろうという。
絶滅の背景にある大きな要因の1つは温暖化だ。それは生態系を支える働きを変えてしまい、全体を不安定にしてしまう。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る第6の大量絶滅の背景にあるもの
だが第6の大量絶滅の背景にあるのは、気候変動だけではない。プラスチック汚染、殺虫剤、生息地の喪失、密猟にいたるまで、私たち人類はありとあらゆる手段で地球の生物を追い詰めている。
「このような絶滅と社会への悪影響を防ぐには、前例のない規模の政治的・経済的・社会的努力が不可欠」と、セバージョス氏とエーリッヒ氏と述べている。
一つ救いがあるとすれば、恐竜を絶滅させた小惑星とは違って、私たちは自分たちが何をしているのか自覚しており、その気になれば別の行動を起こせることだろう。
地球の生物たちの運命は、次の20年で私たちがどのような行動をとるかにかかっているそうだ。
References:Mutilation of the tree of life via mass extinction of animal genera | PNAS / Mass Extinction: Entire Branches on Tree of Life Are Dying, Scientists Warn / written by hiroching / edited by / parumo














人間も含めた現生種が大量絶滅しても生き残った種で隙間は埋まる
そんな事言ってもどうすりゃいいのさ?
※6 ※24
何よりもまず、状況を正しく知ろうとすることが大事
次はそれを自分にできる範囲で広めること
現状についての正しい知識を持つことで、知ってしまった以上何か行動せずにはいられなくなる意欲が湧く
そして知識を増すことはそれだけ取れる選択肢が増えるってことでもあり、無力感への特効薬でもある
知は力なんだよ、マジで
知っている人が増えるというただそれだけの事で世界は確実に変わっていく
だからもっと勉強しよう、そしてそれを他人とシェアしよう
>>37
庶民が現状を知る手段にその資産家の手が加わってる訳ですが…
で、この結論が出せるのは寧ろ知ってるからでもある訳です
現状がどれだけ酷いか、そして自分達が如何に無力かって事をね
社会の無力感を作り出してるのは知る気力すら奪い取る貧困
その貧困層を拡大させてる人達ですよ
それだけ他に新たな種が発生する余地が生まれてるってこと
特定の星で一つの種が完全な勝利者(その星全体を覆うほどの繁栄)になると
多様性が減って種が激減するという一つの循環なのかな?
例え人間でなくとも同じことが起きそうだけど
逆に人間は偏食じゃない(環境に優しいはて)
途中で投稿してしまった
逆に人間は環境に優しいからこそここまで増えることができたとも言える?
>>16
人類が種全体として本当に自然を駆逐できるレベルに達してから100年も経ってない
>>16
産業革命以前は自然の恵みに感謝しながら自然の恩恵を享受する事で栄えてこれたのだと思うけど
産業革命以降は自然の恵みに感謝する事を忘れ自然を破壊し搾取し続ける事で栄えてきた
産業革命以前の暮らしに戻る覚悟を持てるならやり直すチャンスはあるかもしれないけど
それが出来ないなら今までのしっぺ返しで人類が身を滅ぼす事は避けられないと思う
今の電気文明が滅びても人類自体はごくわずかに生き残れるかも。石器時代に逆戻りしても切り替えていこ。
人類以外の生物が全滅しようと人はその歩みを止めることは無いだろう
人類同士で争いあってる下等な生き物だもの
先に豊かになった国、後から豊かになりたい国
もうどうしようも無いとこまできてると思うね。
>>19
むしろ人間同士の争いを止めたせいかもよ。
近頃の異常気象続きの世界を見て もう取り返しの付かないところまで来てるのではと考えていた。でもコロナの時と同じように世界はそれを重要と捉えて来なかったからなんだろうな。
庶民に訴えられても遣れる事なんて高が知れてる
その資源を資産に替えてる人達が率先して動いてくれなきゃ変わらないよ
人類が起因とする今の悪環境は、海で増えすぎたプランクトンが原因で発生する赤潮が周囲の生き物を道ずれにするのと似ている
人口増加に伴いヒトとその仲間(作物・家畜 他の有用生物)が有限の環境の中でのシェアを高めていく。
それにともなって野生生物の生活空間は狭まっていく。昔 野生の楽園とかいわれたアフリカやアマゾンでも進行中だ。生物種数は減る一方だ。どこまでいけるのか壮大な実験の最中なのだ。
光合成を始めたシアノバクテリア(ストロマトライト)、恐竜が滅びる切っ掛けと言われる隕石、何度も到来した氷河期、今回はそういうトリガーがホモサピの活動ってだけで、もうしょうがないんだろな、と思ってる。
次の生態系でも想像して暑さに耐えるよ…(もう耐えたくないけど
そうはいってももうすでにどうにもできない段階だよなぁ。
今更対策を練って実行したとしてもまず人類全体の足並みを揃えることは絶対に無理だし今の人類のが作った倫理観の世界では強硬手段も取れないので残念だけど詰んでるとしか。
対症療法でしかないとはいえNASAはSFのような日照量軽減手段を研究しているし国連は真面目にそれらの採用を検討している
世界が一丸となるのは無理だろうがだからといって諦めていいわけではないぞ
今すぐ火力発電を原子力に変えたとしても、もう気温上昇を止めれないらしい
そりゃそうだよ、乗用車一台が一日走るとガソリン20L燃してる
大型トラックなら一台で200Lの軽油を燃してるようなもんだからな
まあ人類が資源の取り合いの果てに核戦争して地上に放射性物質まき散らして絶滅しても、
放射能に強い生物達が台頭してそれが進化してやがて宇宙線をものともせずに宇宙に飛び立って行くだけだから
ヒトがどうこうしようなんておこがましい。保護しようが滅ぼそうが
スーパープルームや巨大隕石の衝突のような定期的に訪れる大量絶滅イベントがリセット掛けてくれる
>>35
人類の知性は絶滅イベントを乗り越えるために地球が編み出した一つの答えだと思ってるわ
予測できることなら、回避できるかもしれない
>>35
いつか死ぬからと言って今すぐ死んでいい、とはならんでしょ。
スーパープルームや巨大隕石級のイベントは
億年単位のタイムスケールで起こるけど
人為的な環境破壊が今のペースで続いたら
億年どころか万年も持たないのは明白なわけで。