 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る2022年も早くも半年が過ぎようとしている。これまでに発見された太陽系外惑星の数は、今年でついに5000個を突破している。
スーパーアースから木星のようなガス惑星、巨大な氷でできた惑星まで、今では太陽系の外にも魅力的な惑星があふれていることを我々は知っている。
なにしろ天の川銀河だけで1兆個もの惑星があると推定されている。7月に初の映像を送り届けてくれるはずのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が本格的に稼働すれば、さらに不思議な世界が見つかることだろう。
だが今年発見された太陽系外惑星にも奇妙で魅力的な惑星がある。金属の雲をもつ惑星から発展途上な惑星まで、今年これまでに見つかった惑星を紹介しよう。
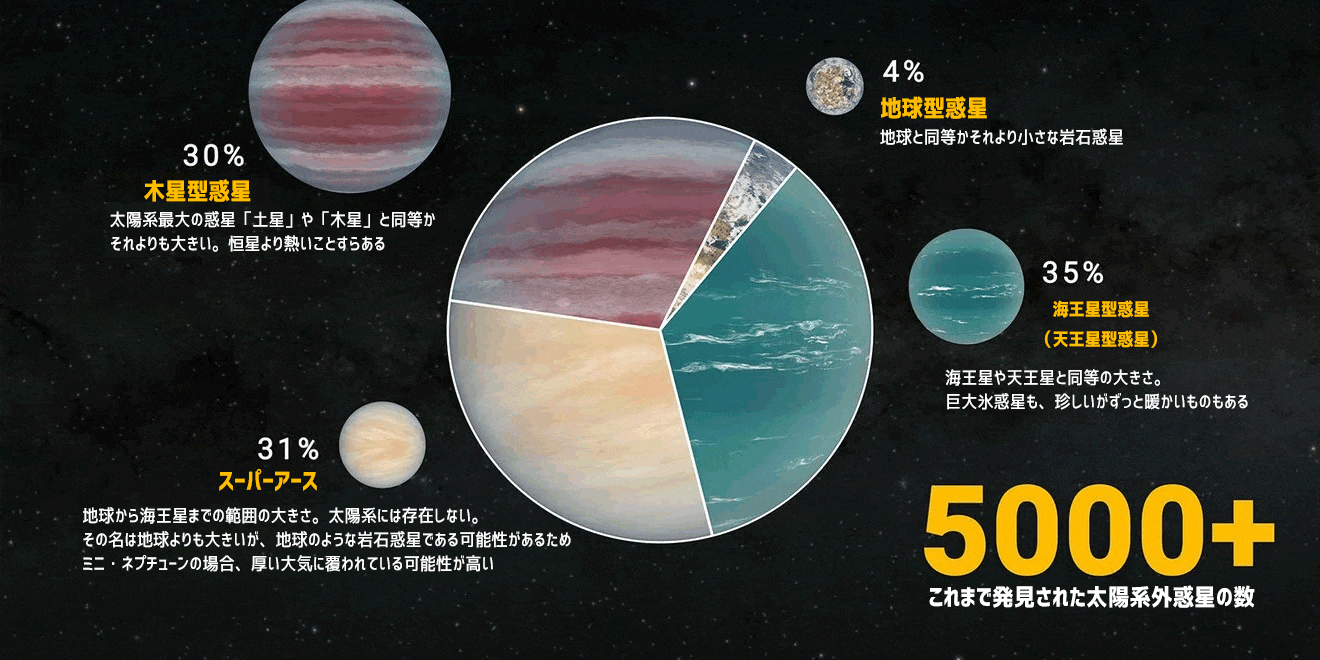 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る1. 金属の雲から宝石の雨がふる惑星「WASP-121 b」
太陽系外惑星を探す研究者は、恒星の一時的な光の翳りを求めている。これは惑星がその前を横切ったこと(トランジット)を示すサインだ。
そうした観測では、ときに太陽系外惑星の大気すら垣間見られる。(次世代望遠鏡ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡ならもっと頻繁に観察できるだろう)。そうした中には我々の知る大気とはまるで違うものもある。地球から855光年先にある「WASP-121 b」には、どうも金属と宝石が漂っているらしいのだ。十分温度が低いので、マグネシウム・鉄・バナジウム・クロム・ニッケルといった金属が凝縮して雲になる。
そんな金属の雲はどんな見た目だろうか? はっきりしたことはわからない。雲の形成は複雑なプロセスだし、太陽系に参考にできそうな雲はない。
だがWASP-121 bを発見したマックス・プランク天文学研究所のトーマス・ミカル=エバンス氏の想像では、地球の砂嵐に似ているのではという。赤や青、グレーや緑といった色がついている可能性もあるそうだ。
雲がさらに凝縮すれば、空から宝石の雨が降ってくるなんてことも考えられるようだ。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る2. ラグビーボールのような惑星「WASP-103b」
ほとんどの惑星は球形だ。だが中には変わり種もある。
欧州宇宙機関(ESA)のCHEOPS宇宙望遠鏡が発見した「WASP-103b」は、木星の2倍という大きさながら、たった1日で恒星を1周してしまう。
このおかげで、月の引力が潮汐を起こすように、WASP-103bもまた強烈に引っ張られる。その結果、かつてはありふれた球形だったのが、今ではラグビーボールのように変形してしまった。
CHEOPS宇宙望遠鏡は光のわずかな変化をとらえ、恒星の前を通過するWASP-103bの奇妙な形を観測することに成功。
ESAのケイト・アイザック氏によれば、変形した形状がトランジットによる恒星の陰りに与える影響はごく小さなものだが、CHEOPS宇宙望遠鏡は観測精度が非常に高いため、それを史上初めてとらえることができたそうだ。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る3. スーパーネプチューンのレアな発見「TOI-674 b」
地球から150光年先で発見された「スーパーネプチューン」(海王星よりも質量の大きな惑星)の大気には水蒸気が含まれている。これは非常に珍しいことだ。
NASAによると、「TOI-674 b」は天文学的には”近く”にある惑星で、そのおかげもあって大気の化学組成を調べることができるという。
今の時点では、大気に含まれる水蒸気の量など、わからないことは多い。だがほとんどの太陽系外惑星に比べれば、ずっと観測しやすく、詳しく調査するには格好のターゲットだ。
2022年7月に最初の画像を送り届けてくれる予定のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡なら、TOI-674 bの大気をさらに詳しく覗き込んでくれるだろう
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る4. 形成過程にある惑星「ぎょしゃ座AB星b」
「ぎょしゃ座AB星b」はまだ形成途中にある巨大な太陽系外惑星だ。
ハッブル宇宙望遠鏡がとらえたその惑星は、若く揮発性の高いガスと塵でできた原始惑星円盤の中で成長を続けている。その主星であるぎょしゃ座AB星もまた若く、まだ誕生して200万年が経過したに過ぎない(ちなみに太陽は45億歳)。
非常に大きな惑星で、木星の9倍はあると推測されている。主星から138億キロと、非常に遠いところを公転しているのも特徴。これは冥王星と太陽の2倍以上もの距離だ。
ほとんどの惑星の場合、原始惑星円盤内の小さな天体が衝突することで形成されると考えられている。しかしぎょしゃ座AB星bは、冷えた円盤が大きな破片に割れて形成された可能性がある。
img src=”https://livedoor.blogimg.jp/karapaia_zaeega/imgs/4/8/48c04520.jpg” width=”1340″ height=”520″ border=”0″ alt=”5″ hspace=”5″ class=”pict” />
ぎょしゃ座AB星bのイメージ画像/Credit: NASA / ESA / Joseph Olmsted (STScI)
小惑星「りゅうぐう」の砂から、生命の源となるアミノ酸を発見!
ここで緊急速報です。
日本の探査機「はやぶさ2」が地球へ持ち帰ってきてくれた、小惑星「りゅうぐう」からサンプルの砂から、生命の源となるたんぱく質の材料になるアミノ酸が発見されたことが6月6日明らかとなった。
宇宙から地球へ落下した隕石からアミノ酸が検出されたケースはあるが、地球外の天体から検出されたのは初めてだという。サンプル砂の中には、20種類以上のアミノ酸が見つかったそうだ。
これは生命の起源の謎に迫る大発見であり、近く論文で公開される予定なので、発表され次第またお伝えしたい。
今年も半分が過ぎようとしているが、近いうちに地球外生命体に関する新たな情報が得られるかもしれない。
References:The stunning new planets discovered in 2022, so far | Mashable / written by hiroching / edited by / parumo
















地球型惑星の割合が少ないのは残念だけど、大きい惑星の方が見つけやすいから仕方ないとも言える。
速報について、星間分子雲にアミノ酸が存在してることは分光法で知られていたけど、現物を持ち帰れたのは大きな前進だな。
隕石で検出されたアミノ酸と違ってどんな発見に繋がるかは見もの
それともそこまで話題にならずに終わるのかな
※2
初期の地球では高温のために、アミノ酸が生成されたとしてもすぐに破壊されてしまう可能性が高い
ただ、アミノ酸生成が宇宙でも可能であったならば、後期重爆撃期以降に降り注いだ隕石によってももたらされた可能性が出てくるので
生命起源や地球外を含む生命の在り方についての議論が活発化する可能性しかなくて、逆に話題にならずに終わる可能性はほぼない
生きているうちに
宇宙大戦争を見たい。
地球は過去全休凍結して氷に包まれた惑星となったけど
広い宇宙の中には、陸地の無い惑星「海洋惑星」なるものがあるそうな
そんな深い海の中にいる生物なんか考えたら眠れなくなるよね
いつかこの中から
知的生命体の住む星が
見つかるのかな・・・・・
いや無理か100%あるわけないかも
そもそも生命体がいても
宇宙に進出可能なほどの文明発達した
「知的な」生命体に進化すること自体が
確率的に低いもんなー
地球なんて人間だけだし
※6
なにかの話で観たな
—
宇宙に知的生命体が人類しかいないと言う話は宇宙の広さを正確に理解していないし、傲慢すぎるが、
知的生命体が地球にやって来ていると言う話も、宇宙の広さを正確に理解していない
—
みたいな話。ちなみに”ドレイクの方程式”というものがありましてー
地球型惑星の、地球型生命体に限定した知的生命体発生率だけを我々の”天の川銀河”限定で計算しても、確率的には現時点で30~40個ぐらいあるそうです
ちなみに天の川銀河を含む超銀河団は10万個ぐらいの銀河を抱えているそうです。宇宙広いね☆
>>7
ドレイクの方程式は変数がまるっと仮定過ぎてな…
※8
宇宙のことをほとんど何もわかってない人類の仮定だから何だっていい感じがある