 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見るチリに囲まれた巨大なブラックホールは星を引き裂くと、超高速の粒子のジェットを噴出する。そのエネルギーは太陽が1年に放出する量の1億2500万倍だという。
超大質量ブラックホールは、太陽の数百万倍から数十億倍もの質量を持つブラックホールで、ほとんどの大型銀河の中心に存在すると考えられている。
この怪物に接近した星は、強力な重力によって引き裂かれる。これを「潮汐破壊現象(tidal disruption event)」という。
ブラックホールが星を引き裂くと、その物質は回転する円盤を形成し、穴の中に落ちる前に明るく輝く。
これまでの研究では、粒子のジェットが降着円盤の極から外側へ向かってとんでもない速度で噴出されるとも示唆されていた。
衝突する銀河「Arp 299」を観測
今回の研究によると、超大質量ブラックホールはほとんどの場合は、活発に何かをむさぼっいるわけではないという。
これまで検出された少数の潮汐破壊現象は、このジェットの形成と進化について学ぶチャンスを与えてくれている。
今回の報告に関して研究者が手にした最初の証拠は、「Arp 299」という地球から1億5000万光年先で衝突する銀河のペアを解析して明らかになったものだ。 これは、カナリア諸島のウィリアム・ハーシェル望遠鏡によって2005年6月30日にもたらされた。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る片方の銀河のコアから光が放出
研究著者であるフィンランド、トゥルク大学のセッポ・マッティラ氏によると、片方の銀河のコアから赤外線光の明るい放出が発見されたのだという。
さらに2005年7月17日、10機の電波望遠鏡ネットワークで構成される超長基線アレイ(VLBA)によって、Arp 299と同じ位置に新たな電波放出源が検出された。
「時間が経過しても、新しい物体は明るい赤外線波長と電波波長のままでした。ところが可視光やX線では検出できないのです」とマッティラ氏は声明で述べている。
「最もあり得る可能性は、銀河の中心にある分厚い星間ガスとチリがX線と可視光を吸収し、それが赤外線として再放出されたというものです」
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見るジェットを飲み込む超大質量ブラックホール
最初、このバーストは超新星の爆発だと考えられていた。しかし、それではデータと一致しない。
「Arp 299-B AT1」と名付けられた電波放出源を10年近く観察し続けた結果、超新星とは違い、ジェットのように一方向に拡大していることが分かったのだ。
電波のデータは、ジェットの物質が平均すると光速の25パーセントの速度で外側に突き進んでいることを示唆していた。一方、10年が経過した超新星の平均的な膨張速度は、せいぜい光速の5パーセント程度だろうと予測されている。
「赤外線と電波の観測に、電波ジェットの最新シミュレーションと超大質量ブラックホール周辺の埃っぽい領域からの赤外線放射の計算を組み合わせた結果、1つの現実的な説明にたどり着きました。赤外線放射と電波放射は、超大質量ブラックホールにうっかり近寄りすぎて飲み込まれている、不運な恒星の破壊に起因するというものです」
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る太陽の2000万倍の質量
推定では、このジェットを飲み込む超大質量ブラックホールは、太陽の2000万倍の質量がある。それは衝突している銀河ペアの片方のコアにあり、太陽の2倍以上の質量を持つ星を砕いているところである。
「この現象で発生したジェットの形成と進化を直接観察できたのは史上初のことです」とペレス=トーレス氏は述べる。
驚きの発見だ。Arp 299-B AT1は銀河の衝突で生じた超新星爆発を検出するためのプロジェクトの一環として発見された。
当初、超新星だと考えられていた赤外線バーストだが、2011年になって細長く伸び始めていることが判明し、発見から6年目にして実はジェットであることが明らかになった。
それからほぼ10年にわたり、1.5 × 10^52エルグ以上もの赤外線と電波が放出された。これは太陽が1年に放出するエネルギーの1250億倍という量である。
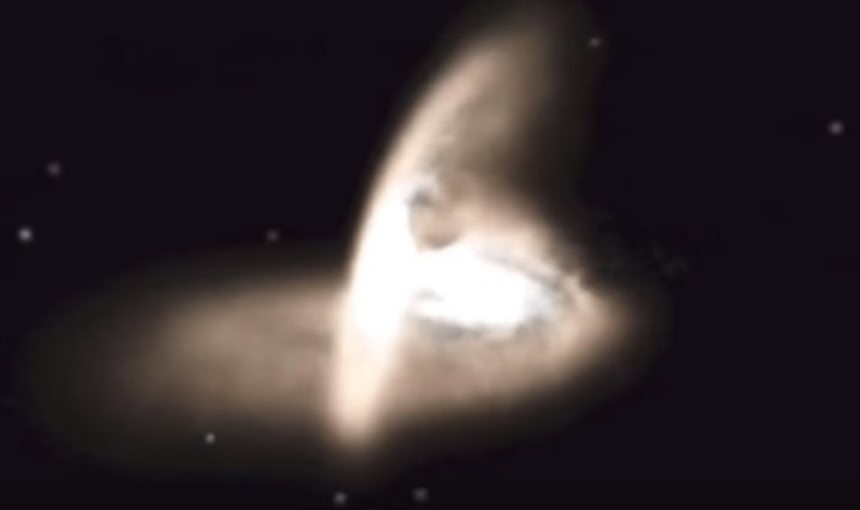 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る潮汐破壊現象の解明に
今、VLBAを使って、「電波源がいくつもの電波源にばらばらになる様子を目撃しています。ここから、ジェットと周辺の媒体が作用する様子を知ることができます」とペレス=トーレス氏は言う。
この現象は、おそらくガスやチリの影響で、可視光やX線波長では明るくなかった。このことは潮汐破壊現象が理論的な予測よりも明るくない理由を説明するかもしれない。
「赤外線や電波でないと観測できないなんて、一体いくつの似たような現象が見逃されているんでしょうね?」とマッティラ氏は話す。
このことは赤外線望遠鏡や電波望遠鏡なら、これまで見逃されてきたかもしれない潮汐破壊現象を捉えられるかもしれないということだ。そうした現象は実は初期宇宙ではもっと一般的なことだったのかもしれない。
研究は『Science』に掲載された。
References:phys / sciencemag/ written by hiroching / edited by parumo
追記(2018/6/21): 本文の一部を修正して再送します
















タイトルの倍数間違えてる??
吸い込まれてる恒星から1.5×10の52乗エルグ(=1.5×10の45乗ジュール)のエネルギーが放出されてるんであって、ブラックホール自体のエネルギーではないことに注意。
全くわからんけど、ブラックホールに行ってみたいよね
それだけのエネルギー放出に耐えられる宇宙空間?が凄いな
相変わらず宇宙の話は億単位が平然と飛び交って感覚が狂うな…
※6
まさに天文スケール
宇宙こえーよ
まったく見当が付かん。
1メガダイソン(高い掃除機1000台分)ぐらい?
なるほど、わからん
チリ(塵)は ちり だよね。
イライラする時には宇宙に関する本やネット記事を読んでいる。
人が決して及ぶ事が出来ないスケールのデカさに興奮や好奇心も通り越して恐怖を抱き、気付けば苛立ちが治まっている。
「ニコッ」(拙い言葉で今日の出来事を一生懸命報告する子供に曖昧な笑顔を向ける母親)
えっ!?光や粒子さえも呑み込むってのがブラックホールじゃないの?
ナンデ、赤外線出しとんねん!
※13
星がブラックホールにぶっ壊される時、ここから先は光も逃げ切れないってギリギリ限界の重力境界線ができる。逆に言えばその範囲でなければ逃げ出せる、運よく重力とのチキンレースに勝って逃げた放射線もあるから、その僅かな量を調べて最大値算出してるんだと思う
※20
今回の記事は「事象の地平面から逃れた電磁波を観測した」というよりは、
「ブラックホールのジェットから出た電磁波を観測した」という事じゃない?
※26
貴方が正解な気がする
ブラックホールに天体が吸い込まれるときは真っ直ぐ突っ込んでくんじゃなくて水平の渦を描きながら徐々に引き延ばされながら吸い込まれていく
この時に極方向に強烈な電磁波を放出(γ線バースト等)したりする
日本は何に金使ってるんだろうね この手の話はみんな海外
※14
何時だか一位じゃなくちゃ駄目なんですか言われて仕分けされちゃってから低迷してるよね
※23
二番じゃダメか?
ちょっと前に宇宙の解説動画みてたら、あんまりにもデカくてもうデカくてデカくて瞬間移動装置が無いと無理って、うちゅースゲーってワクワクした。
ブラックホール「粒子吹いた」
そもそも銀河の衝突ってなんだよって話だよ
いや、星も星系も銀河も物凄い速度で複雑に回転しながら移動してるらしいってのはどこかで聞きかじったけども…規模がデカすぎて想像できない
四つの銀河が衝突途中で核(BH)を四つ持つ銀河があって、これが奇妙なことに赤外線で物凄く明るいから見逃されていたって言うのもある。
大体人間って言うのは可視光で判断するので紫外線やX線と言った大きなエネルギーの方に着目しがちだったのだけど、「電波~赤外線で明るい」という実例の元に全波長での観測が当たり前になりつつある。
宇宙とか知識はまったく素人だけど、銀河の写真とか見ると、もうなんか自分の想像の外だわ。実感がわかないというか。。
あそこに無数の星があるんだろ?
俺にはただの「煙」しか見えないんだが。。。ww
銀河でベイブレードしたらヤバイな…←
太陽じゃなくって平均的なブラックホールのサイズで比較してくれよ
東京ドーム何個分、という例えよりは分かりやす…くねぇよ!
とりあえず凄いっていうのは分かるんですよね…えぇ
その周りの宇宙空間がこのエネルギーに耐えられているかは分からないんだよなあ……
場がねじ曲がって空間おかしなってるかもしれんのやで
食べたら出す、ブラックロールも生物だった
まるで何も進んでないのと変わらない気がするが
宇宙とやらが解明される時は来るのかね