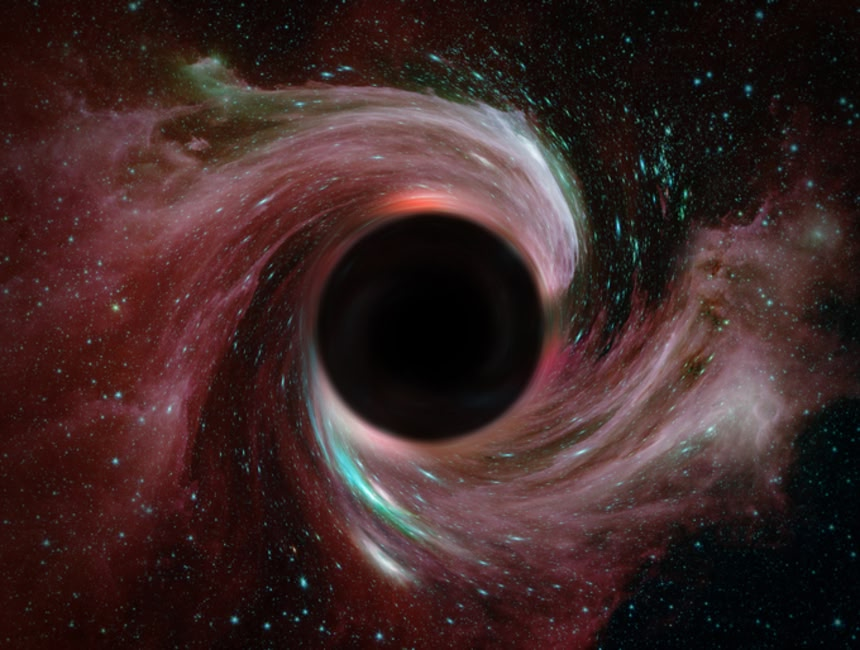 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る「ブラックホールの奥深くには重力の特異点と呼ばれる領域が存在する。ここでは時空の歪みが無限大となり、いかなるものも生存できない場所だ」と、これまでは考えらえれていた。
しかし、ある最新の研究では、ブラックホールの中心にはワームホールがあり、これが裏口として機能していると論じられている。
ワームホールとは時空が歪んで作り出される近道のことだ。例えば、折り紙に鉛筆で2点の点を描いて、その間の距離を宇宙の距離に見立てたとしよう。このとき折り紙を折れば、点の距離を近づけることができる。ワームホールもこれと同じようなものだ。
スペイン、バレンシアにある粒子物理学研究所(Institute of Corpuscular Physics)の物理学者らは、特異点を時空の幾何学構造の中の欠陥であるとみなすシナリオを提唱する。
ブラックホールの活動に似た構造を利用して検証
この考えを検証するために、グラフェン層の結晶の構造に似た幾何学構造を用いるというあまりないアプローチが採用された。この結晶の構造はブラックホールの内部活動によく一致しているのだという。
研究チームが焦点を当てたブラックホールは、動きがなく、電荷を持つタイプだ。
「ブラックホールは重量に関する新しいアイデアを試すことのできる理論的な実験場のようなものです」とバレンシア大学のゴンサロ・オルモ氏。
結晶にはミクロスケールの構造に欠陥があるように、ブラックホール中心領域は時空の異常であり、正確に記述するには新しい幾何学要素が必要になると解釈することが可能なのだという。
研究チームは新しい幾何学配列を分析することで、小さく、球状面を持つ中心点を発見。これはブラックホール中心にあるワームホールを表しているのだそうだ。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見るブラックホール中心にワームホールという出口
彼らの理論は電荷を帯びたブラックホールを解釈するにあたって存在するいくつかの問題を解決できる、とオルモ氏は説明する。
まず第一に、特異点の問題が解決される。ブラックホール中心にワームホールという出口があるため、ここから時間と空間が継続することができる。
計算によれば、中心のワームホールは原子核よりも小さいが、ブラックホール内に蓄えられた電荷に応じてサイズが大きくなるという。
万が一ここに物質が近づくと、ブラックホールからの距離の違いが生み出す重力の差異によって極端なまでに引き伸ばされて(スパゲッティ化)ワームホールに進入できるようになる。それから反対側に到達したときに圧縮され、元のサイズに戻る。
人間が生きたままここを通過することはできなさそうだが、研究チームの主張によれば、ブラックホール内の物質は従来から考えられてきたように永遠に失われるわけではなく、宇宙の別の領域に追い出されるようだ。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見るまたアインシュタインの重力理論が示唆するような、ワームホールを発生させるエキゾチックエネルギーも必要なくなる。ワームホールは電場のような通常の物質とエネルギーから出現することが可能となる。
















そうであって欲しい
ブラックホール突入時に引き伸ばされることに変わりはないのか
引き伸ばされた後元に戻るって、そんなことが可能な物質あるの?
つまりパソコンが宇宙として、ネットに繋がったのが、ブラックホールみたいなもんかな。
案外、宇宙はパソコンの中にある仮想空間なのかも。
その中に入ってプレイしていて。
死んだら得点がでて。
得点が低いと地獄に。
なーんて考えてみたり。
想像がとまんない。
そのワームホールを抜けられない残りカスみたいな物質が僕らだよ
これは人類が無限の宇宙へ旅立てる可能性を示唆しているようで
実際は夢のワームホールが人間の手の届かない領域にあって、これまで「ワームホールを使えば遥か宇宙の深遠に行ける」って願望を否定する研究結果なのかな?
インターステラーが現実味を帯びてきたな。
しかし、スパゲッティ状にされてもミクロ単位で元に戻るなら人間も或いは通過することが出来るんじゃないだろうか。意識の連続性は無いかもしれないが。
そんなもの無いよ
カー・ブラックホール特有の「吸引力の落ちない唯一の引力式サイクロン掃除機的な何か」で吸い込んで出しているだけ。
どういうこと?!!特異点を計算式で表すことに成功したってこと?!!そうなら強烈鮮烈なニュースだと思うんだけど?!!
もうちょい説明欲しい!
スパゲッティになるということはわかった
象の上に大地があって我々がいるって大昔の学者が言ってたのとたいして変わらないんじゃない?先ずは目視確認できてからじゃないと
人間はスライムの様な物体だった…?
おお・・・わからん
圧力調整弁みたいな感じで増えすぎたエネルギーを抜いてるのがBHじゃないのか。
言いたい事 言ったもん勝ち 青春なら~
突撃!隣の晩ご飯ハイパー(スパゲティか
大小様々なブラックホールは見つかっているのに物質が噴き出してくる特異点が1つも見つかってないってことは、やっぱり違うんじゃないの?
ブラックホールは重みで空いた穴なんだよ。
どこに落ちるか、というとその場に落ち続ける。言葉としては成り立ってないけど、宇宙では上下左右の概念がないから、重たいものはどこに落ちるかというとその場に落ちる。静止してるけど落ちてるんだ。
トランポリンに重たい玉を置くとへこむ。軽い玉を置くと、当然へこみで斜面になってるから転がり重い玉にくっつく。それが重力。宇宙では上下左右ないから360度へこむ。重すぎると皮が破れる。それがブラックホール。穴の奥は重たいものがあるだけ。でっかい惑星があるんだろうな。
吸い込んで吐き出す先がどこかは分からないけど宇宙空間の中で物質を循環させる装置としても働いていそうな感じだね
※17
ブラックホールからジェットが出てなかったっけ
※17
360°へこみ続ける空間に引き寄せられたら、物質は空間の一点に収束するよね。
で、何故その一点が「穴」なのか意味がわからない。最後の一点は収束点なんだからそれ以上落ちようがないわけで。
というか、宇宙空間には上下左右前後の区別がないのだから、そもそも「落ちる」って表現が間違ってる。
そもそもブラックホールは穴じゃないんだしさ・・
※18
違う。空間をトランポリンの様な膜で例えるのならば、ブラックホールはそこに存在する非常に深い凹み。
重すぎて皮が破れたのならば、その破れ目はワームホールと表現される。その穴を通る物はトランポリンの表面にある連続性から逃れる事ができる。
ハラペーニョ
素人のイメージとして質量が圧縮されて臨界?超えると
次元に穴が開く・・・なんてのは昔から漫画でよくあった話だな。
超絶圧縮プレス機で潰されて放り出されてるなら物体はガス状だろうか?
つまり人類がスパゲッティ並の細さに進化する、もしくは液体状になれるなら通り抜けられるってことだな!
つまり、どういう事だってばよ?
向こう側の宇宙に出たとたん、出てきたワームホールに吸い込まれて永遠に行ったり来たりする羽目になる気がするんだが
特異点はやっぱりどうにもならないので、特異性が小さくなるように一般相対性理論を拡張してやったところ(この拡張「f(R)重力」自体は昔からある)
面白い解が見つかったってことらしい。ブラックホールなんだけど、中心は点ではなく球面になってるらしい。
吸い込まれたものがどこかに出て行くなら、
質量を維持できずにあっという間につぶれるのでは?
出口が見つかってないのにバカじゃねって話
吸い込んだものが出てくる場所が見つかってから夢見ような
そして次は出口は異なる宇宙とか言い出すんだろ
調べようがないし言ったもん勝ちじゃねーか
こんなアホな事を本気で言ってるなら笑い者だろ
※29
出口や出てくるものが、今の技術で観測可能とは限らない。
詳しくはゼリーマンレポートを参照せよ
>>30
とんでもない持論があってそれを馬鹿にしてたら
その人が死んだ後に実は正しかったと証明されたってのはよくある話じゃん…
結構昔から言われていた事だけどね
例えワームホールがあったところで事象の地平線の向こう側なら確認のしようが無いし生きた人間が抜けられる訳でもない
外から見るとバラバラになったそれは永遠にブラックホールの地平面に到達することは無いのに
どうやってあっち側にいくんですかね
ブラックホールって時間と共にひたすらデカくなるだけなんだけど…
お盆のとき、ご先祖様はワームホールを通り抜けてやって来るらしいよ。
これホント。
この特異点にたどり着く前に事象の地平面で粉々になりそう。
なるほどね
俺はカルボナーラで頼む
ちょっと前に見た番組だと、
ブラックホールの底はドーナッツ型で、その穴を通ればワープできるとか……
いやいや、原子レベルまで分解されて、2次元の情報としてブラックホールの表面に保存される(理論的にはその情報から3次元に復元できる ※宇宙ホログラム説)、とか……
まぁ、訳がワカランけど興味が尽きないね
※38
ケチャップぶっかけてやるぜw
ドラえもんで見た!
※40
それって乙女座銀河団の巨大楕円銀河m87の事?それ6億倍とか言ってた気がする。
で、どうやったら生きて向こう側に行けるようになるの?
スパゲッティ化ねぇ・・・
まあ、スパゲッティ化する前に我々人類はミートソースになってしまうと。
どっちにしても、現時点の地球人類の科学レベルでは、実際に実証できる力がないというのが少し悲しい。もし地球人類に現在よりも数千年、数万年くらい進化した文明が有ったなら
『じゃあ、実証するためにブラックホールの中に探査機を送り込みましょう』という事ができるだろうと思う。多分、地球人類も将来的には実証しようとするんじゃないのかな?どのくらい先の事になるのかは判らないけれど。
やべ、寝る前に読んじゃったよ。
もう宇宙の神秘が気になって眠れない。
はやく実際に、精密な観測と研究ができる時代になりませんかねぇ~。
ま、宇宙開発技術で凄いブレイクスルーでもないと自分が生きているうちには、実現されんだろうけど。
観測できない以上、まだまだスパゲッティ・モンスター教レベルか。それでも計算式で可能性が見いだせたってのは面白いね。
動きがないってのが意味わからないんだけど、角運動量が0ってこと?
たとえ宇宙開闢インフレーション名残のBHにしたって、物質を吸い込む過程で角運動は獲得すると思うんだけど。
何をもって「動きのない」って言ってるんだろう。
ロシアの巨大隕石
核融合エンジンの実用に目処という噂
空間を折り曲げて(フォールド)跳躍…
次は巨人がきますね
つまり、ブラックホールは巨大ところてん製造機ってことか。
入るとスパゲッティ
出ると肉団子か・・
>ブラックホールからの距離の違いが生み出す重力の差異によって極端なまでに引き伸ばされて(スパゲッティ化)ワームホールに進入できるようになる。←わかる
>それから反対側に到達したときに圧縮され、元のサイズに戻る。←はぁ?
※54
その肉団子がお星さまだったりして
なんって、なんって。
元のサイズに戻る 高圧力で体が潰れる 高温で炭化、ダイヤまで圧縮されたのち蒸発
その気体がプラズマ化 出口に近づくほどに徐々に冷え 気体、個体、液体と
それぞれ物質的な質量として元に戻るってことかね?
まあ確かに元のサイズには成るが物体としてで・・生きては無いな
引き伸ばされてから戻るまでの時間が短い時間だと分子構造はそのままらしいから普通にワープ出来るんだってね
BHの吸い込む質量の限界があって それを超えたらビッグバンを起こす
って聞いたけど。つまり別次元の宇宙を無から作り出すって。我々の宇宙の中心
(ビッグバンの始まりとせれる中心)がそれであって、BHは発見されても
ワームホール(出口)が発見されないのはそういう事かと納得した。
ビッグバンが起こればその入口も出口も消滅するだろうし。
ブラックホールは黒い穴を意味するけど実際は穴じゃない
質量と重力が巨大な天体なだけ
ワームホールなんかあるわけ無い
↑当たり前だが、ブラックホールに地上はないと思うけど。
空間への質量が、原子が潰れる中性子星程度の比じゃないんだから
そんなもの形成できる単位が破壊されてる
内部が観測できないからブラックホールなのに
ブラックホールの内部活動に一致ってどういうこと?
まずスパゲティ状に伸ばされた時点で大抵のものは破壊されると思うんですが
>>63
スパゲティを食べるのは得意だが、スパゲティ状に伸されて食べられるのは得意じゃない。
一言潮汐力って言えばいいのを重力の差異云々って説明してるのは初めて見た
たとえ出口が有ったとしてもそれは別の法則で運営されている宇宙。
そこでは銀河の中心はブラックホールではなくホワイトホールになっている。
本文の
>ワームホールとは時空が歪んで作り出される近道のことだ。
>例えば、折り紙に鉛筆で2点の点を描いて、その間の距離を宇宙の距離に見立てたとしよう。
>このとき折り紙を折れば、点の距離を近づけることができる。ワームホールもこれと同じようなものだ。
折り紙を上から見たとき、確かに2点間は近づく。だが、その2点を移動するには折りたたまれた平面状を折られた通りに屈曲しながら移動するのだから、結局のところ「移動距離」は変わらないよね。
つまり、三次元の住人から見れば二次元(紙面)上の2点間は縮まったように見えるが、二次元に住む住人は、飽くまでも二次元の中を移動するしかない(三次元には飛び出せない)のだからワープすることは出来ないということだ。平面状をずっと辿って行くしかないからね。
この手の話題には、ブルーバックスシリーズなんかの科学読み物で昔からよく見る例えなんだけど、なぜ三次元空間の歪みを説明するのに二次元の紙を持ち出して例えるのか疑問なんだよな。
それじゃ実質的な例えになってないのにと…
※68
そうでもないよ
紙の端と端を繋げば輪になるじゃない
そうすると地続きだよね
では次に穴を開けて繋いで八の字にすれば地続き(平面視点移動)でワープになるよね
問題はホントに空間が歪んだりしてるのかどうかだね
光は歪む、それは確かなこと
でも空間はどうなんだろう、無空間が歪む?!