
����������ǽ�פ�����Ϥ��ޤ�ˤ�ʹ���ͭ�Τ�Τǡ�����Ԥ�ϡ����ΤȤ館�����Ф꤬���뤳�Ȥ˵����դ�����
��ưʪ�Ϥ��줾��ޤä����ۤʤ�ʲ���Фƺ��ˤ����롣��������餬����������ǽ�ϡ��ʹ֤����Фδ��Ȥ�����ΤǤϤʤ�����ä�����Ū�ʴ�������¬����٤��Ǥ������Ȥ����Τ���
������������ǽ�Ȥ�����ǰ���Ѳ��˲ä��ơ��ɥ������AI�Ȥ��ä����ޤ��ޤʥƥ��Υ������ϡ�ưʪ����⤹�뤳�Ȥʤ����������ʤ��ͻҤ�Ĺ���֤ˤ錄��ѻ����뤳�Ȥ��ǽ�ˤ�����
���������Ȥ������椫��ϡ�ưʪ����ǽ�Ͻ���ͤ����Ƥ����ʾ�ˤ��ä���������Ƥ��ꡢ������Х饨�ƥ�˭���Ǥ��뤳�Ȥ����餫�ˤ���Ƥ��롣
�ʹ֤�Ʊ���褦�ʹ�ư����ưʪ����
����ǽ�ˤĤ��Ƥγ�ǰ���礭���Ѳ������ȤϤ������������֤Ϥä���ȴ�������Τϡ���Ϥ�ưʪ���䤿���ʹ֤˻�����ư�����Ȥ�������ΰ�̣���Τꡢ��֤�Ĥ����
�����Ȥ��Х����ϡ��������֤���������Ф��Ƥ��ꡢ��������뤳�Ȥ��Τ��Ƥ��롣��֤λ��Τ˶����ؿ���������ϻ��Τ����Ԥ��ƴ�����ʬ���ޤǤ��ä�³���������Τ��Ȥϥ�����������̤ʴؿ��������Ƥ��ꡢ�����켫ʬ����̤��Ȥ�ռ����Ƥ����ǽ������ۤΤᤫ���Ƥ��롣

Photo by Bisakha Datta on Unsplash
���ߤ���̾����Ƥӹ礦���륫
���ޤ����륫����֤�̾���ǸƤ�Ǥ����ǽ�������롣̾���Ȥ��äƤ�ʹ֤Τ���Ȥϰ㤤����ͭ�μ��ȿ��θ�ū�������ɤ������ϡ���֤��줾������Ѥμ��ȿ��������Ƥƥ��ߥ�˥����������路�Ƥ���褦�ʤΤ���
�����ߥ�˥��������Ȥ������ˤĤ��Ƹ����С������ޤ��ե�������𤷤���֤Ȥ��Ȥ���魯���Ȥ����롣����������Υ��ߥ�˥��������Ǥϡ����뿮����Ф��Ƥ��Ĥ��ޤä�ȿ�����֤äƤ��롣
�����������륫�Τ���Ͽʹ֤θ���Τ褦�ˡ���äȽ����ʸ̮�˱������Ѳ�����褦�������Ȥ��С��֥饸�������Υ饰���ʤ���©���륤�륫�ϡ�100ǯ�ʾ�ˤ錄�äƵ��դȸ�ή������̡���ͭ���¤꤬�Ǥ������Ȥ��Τ��Ƥ��롣

photo by iStock
ʣ���ʼҲ롼�פ��������Ļ��
�����������ޤ�ǿʹ֤�פ碌����ǽ�ϡ�Ӯ��������Τ�ΤǤϤʤ�����������ʤɤ�¿����Ļ��ϡ�ʣ���ʼҲ롼�פ�������뤬��������Ǥ����Ȥδط��ˤ�äư��������Ѥ�äƤ��롣
�����Τ褦�ʽ����ϡ�Ļ�����Ϲ⤤��ǽ����ΤȤ�����Ϣ��ؽ��ס�2�Ĥ�ʪ���δ�Ϣ����ؽ����뤳�ȡˤ��Ǥ���餷�����Ȥ����Ƥ��롣
ǧ��ǽ�Ϥ���ĺ���
���ޤ�����Ͼ�����Ǿ�����ʤ��ʤ��顢ƻ��λ��Ѥ�����ǧ���ޤǡ��ä��ۤ�˭�٤�ǧ��ǽ�Ϥ�ȯ�����롣��Τ���Ǥ��뤷��������ѻ����Ƴؽ����뤳�Ȥ��äƤǤ��롣
Photo by Vandan Patel on Unsplash
ưʪ����ǽ�ȿʲ��δط�
����������ưʪ��������ǽ�Ͽʹ֤Τ����Ϣ�ۤ����뤬�����������줬ȯã�����ʲ���ƻ�ڤϻ䤿���ȤϤޤ�ǰ�ä���Τ��⤷��ʤ������̿ʲ��ˤ�äƤ⤿�餵�줿��ǽ
���Ƕ�ޤǡ����٤�ǧ��ǽ�ϤϥҥȤ����ɤäƤ����ʲ��ʤ�ǤϤΤ�Τȹͤ����Ƥ��������������ߤǤϡ�������ϵ���뤵��Ƥ��롣�����Ȥ��С������ʤɤ�Ƭ��Ͽʹ֤ȤϤޤä����ۤʤ�ʲ��ɤäƤ�����ʪ������ξ�Ԥ�Ǿ�ι�¤�ˤ�����������뤳�Ȥ����餫�ˤʤäƤ��롣
�����Τ��Ȥ��顢�ɤ�����ǽ�ϡ����̿ʲ��ʼ�«�ʲ����סʤޤä����̤���ʪ��Ʊ����ǽ��������ʲ������뤳�ȡˤλ�ʪ�餷�����Ȥ����������롣�Ĥޤꡢ�Ķ�����Ŭ�ڤʰ��Ϥ�Ĺ���֤ˤ錄�äƼ�����������С��ɤ�ʼ�Ǥ��äƤ���ǽ��ȤˤĤ�����Ȥ������Ȥ���

Photo by Diane Picchiottino on Unsplash
�����ʬ����ͽФ���ǧ��ǽ�Ϥ����
���ޤ���ǽ�ˤϡ��ʹ֤Τ����ĺ���Ȥ���ҥ���륭���Τ褦�ʤ�ΤϤʤ����綠�줾��˥�ˡ����ʤ�ΤǤ���餷�����Ȥ����餫�ˤʤ�ĤĤ��롣���Ȥ����Τ⡢���⤫��Ĥʤ����ʤ��ʤ��Τ��Ȥ��Ƥ⡢�ۤȤ�ɤ�ưʪ�ˤ�1�Ĥ�ʬ��ʤ�з�Ф���ǧ��ǽ�Ϥ����뤫�����
�����Ȥ��Х���ѥ��Ρ�û�������פϡ��¤Ͽʹ֤���ͥ��Ƥ��롣���Τ褦���Ϥ�ȤˤĤ��뤳�Ȥ��Ǥ����Τϡ�����������˴ؤ����Ǥ�������������������Ӥ�ˤϡ�û�������������Ȥ����꤬��������������ȹͤ����롣

Photo by satya deep on Unsplash
ưʪ�ϰ�̣���Ǥ���
��ưʪ����ǽ�˴ؤ��븦��ϡ����вʳؤ���⤿�餵�줿�θ��ˤ��礭�ʱƶ�������Ƥ��롣�����Ȥ��С����ʤ�ο���ưʪ��������̣�����פ���äƤ��뤳�Ȥ��Τ��Ƥ��롣ʪ�����̤�ʪ���˷�ӤĤ����ϤΤ��Ȥǡ����ʤ����ϥ��ơ��ɤ��줿���ˤ���Ϣ�ۤǤ���ΤϤ��Τ���������
������˺Ƕ�θ��椫��ϡ���åȤ�ϥȤȤ��ä�ưʪ�ˤϡ����ԥ����ɵ�����Ĺ�������Τ������Ŀ�Ū�и��˴�Ť���Ρˡפ��餢�뤳�Ȥ���������Ƥ��롣�Ĥޤ�Ƭ����Dz��ηи��äȺƸ����ƻפ��Ф���Ȥ������Ȥ���

Photo by dadalan real on Unsplash
ưʪ�ϼ��ʤ�ǧ�����Ƥ���Τ���
����ǽ�Ϥ��Ф��С�����伫�ռ��Ȥ��ä�����Ū�ʵ�ǽ�ȷ���դ����롣����Ͽʹ֤ʤ�ǤϤȤ��������������ưʪ�Ǥ⤳���ϴѻ�����Ƥ��롣����ͱ��¿���ϡ����˱Ǥ뼫ʬ��ʬ��ǧ���ʶ���ǧ�ΡˤǤ��뤬������ϥ��륫�䥾���⤽���Ǥ��롣
������������ϼ����ξ��֤Ǥ�̵�����������μ¸��Ǥ϶���ǧ�Τ����뤳�Ȥ��������Ƥ��롣���Τ��Ȥϼ���ǧ���Ϸ����ǿȤˤĤ�����ǽ�ϤǤ��������Ȥ����Ƥ��롣
���������������餬�֤ɤ������Ƥ��뤫�פ��Τ뤳�Ȥϡ��֤ɤ��ͤ��Ƥ��뤫�פ��Τ��������
�����Ȥ��С����٤Ƥ�����ưʪ�Ͽ��зϤ����Ƥ��뤿��ˡ�����Ȭ�塢�ˤߤ��Ƥ��롣�����Ǥ�����θ���ΤۤȤ�ɤϡ��ͥ��ƥ��֤ʴ���ˤΤ߾��������Ƥ���Τ���
������ϤĤޤꡢ����ʳ��δ���ˤĤ��ƤϤޤ��ޤ��褯�狼�äƤ��ʤ��Ȥ������Ȥ���
��������Ѥ߽Ťͤ�ƥ��Υ�������ȯã�ˤ�äơ�ưʪ�ˤ϶ä��ۤ��������줿��ǽ������äƤ��뤳�Ȥ����餫�ˤʤäƤ������������������Τϡ��䤿����ưʪ�Ϥ���ޤǹͤ����Ƥ����ʾ�ˤ��äȤ褯���Ƥ���Ȥ������Ȥ���
References:Animal intelligence is far deeper than we ever imagined - Big Think / written by hiroching / edited by parumo
���碌���ɤߤ���
 ưʪ����֤λ���ᤷ��Τ��������ʳ�Ū�˲������뤳�Ȥϲ�ǽ�ʤΤ���
ưʪ����֤λ���ᤷ��Τ��������ʳ�Ū�˲������뤳�Ȥϲ�ǽ�ʤΤ��� ��������֤λ���ᤷ�߰���ΰդ������롣�̼�Υ����λ���Ф��Ƥ���ؿ������쥢�եꥫ��
��������֤λ���ᤷ�߰���ΰդ������롣�̼�Υ����λ���Ф��Ƥ���ؿ������쥢�եꥫ�� Ǿ��9�Ĥǿ�¡3�ġ��Ĥ����ή�����٤���ǽ����Ķä��٤���̿�Ρ��������Τ�줶��9�λ���
Ǿ��9�Ĥǿ�¡3�ġ��Ĥ����ή�����٤���ǽ����Ķä��٤���̿�Ρ��������Τ�줶��9�λ��� ���饹���̳ʡ����饹��Ǿ��ĻƬ�ǤϤʤ���������ǽ�ι⤵��ʿ�Կʲ��ˤ���ʥɥ��ĸ����
���饹���̳ʡ����饹��Ǿ��ĻƬ�ǤϤʤ���������ǽ�ι⤵��ʿ�Կʲ��ˤ���ʥɥ��ĸ���� ��������ä��ԤäƤۤ�������ʪ�˰ռ�������Ȥ�����Ĭ����ʸ��ȿ�����븦��ԡ��Ƹ����
��������ä��ԤäƤۤ�������ʪ�˰ռ�������Ȥ�����Ĭ����ʸ��ȿ�����븦��ԡ��Ƹ����













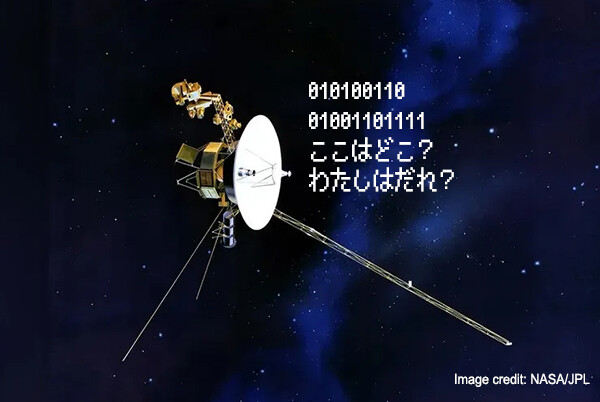
 6175
6175 309
309 10
10 37
37



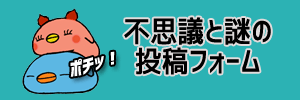





























































������
1. ƿ̾������
�Τ����λ���ǭ���⤤�Ȥ�����α�ޤä����ν��Ĥ˰��Ƥ˥����������������������Τ��ߥ㡼�ߥ㡼�Ĥ��Ƥ����ʡ�ǭ�Dz������Ȥ��δ��𤬤������ʤȻפä���
2.
3. ƿ̾������
�����Υ����������Ǥ⥷���奦���餬�����ʸˡ���äƤ���
���Ʊ�β��ä��Ƥ������Ȥ��ͤ��ߤ�ä��äƤ�����
��Ļ�����ϲ��ä��ƴ��������ͭ���Ƥ�������
�Ҷ��Τ��������ᤵ�����ơ����ñۤ��ޤǤΣ�ǯ��
�����������ᤫ������ƨ�����Ƥ�����ʬ�������Τ�����Τ�
4.
5. ƿ̾������
���ƻ�����ѤǤ��ơ����ǧ����Ǥ��ơ���Τ���Ǥ��ơ�������ѻ����Ƴؽ��Ǥ���äƤ����Τ������ˡġ�
6. ƿ̾������
��桹���פäƤ���ʾ�˸���
�夫������
�ʹ֤Ϥ������֤äƤ���
�����ϤϽä�����
�臘�ϤϤ�����ˤ�������Ȥ����Τ�
�ϵ�β��Ԥ�ˤƤ���
7. ƿ̾������
>>3
�������ƨ�����ʤ��褦�ˤ���Ȥ�����ζ�
���⡢��ʬ���ΤȤΥ�����������ܤε�����ʪ����Ť��Ƥ����顢ƨ����Τ������ʤ����
���Τ���ξ������Τ���ʤ����
8.
9. ƿ̾������
Ļ��ʪ�����������顢ĻƬ�äƸ������ɤ��ˤ��ʤ���ȻפäƤ롣
�Ϥ⸭�����顢�ϼ��äƸ��դ�Ʊ��������
���������ռ��ꤷ�����櫓����ʤ����ɡ�
10. ƿ̾������
�פ�����礷��Ƚ�����Ƥʤ����ʹ֤�ǧ�Τ��Ƥʤ������äƻ������
����ưʪ�Ͽ��зϤ����Ƥ��뤫���ˤߤ���äƷ����ʤΤϡ�Ʊ����ˡ����äƤʤ���ʪ���ˤߤδ������å����������Ƥʤ�����
�äƲ�ǽ���������⤤��ʤ�����
���ä���ʪ����ˤ����ʤ��������Ĥ������ߤ���ͳ�ΰ�Ĥ˶��˲����ͭ�ꤽ������ʤ�
11. ƿ̾������
�����ư�䤽�κݤ�Ƚ�ǥ����Τ��꤫��������������Τ���ã�����ꤷ�Ƥ����������Ū����ǽ�Ϲ⤤�Ǥ��礦
�ʹ֤�ǧ����ʤ������ʤ�ʤ�����
12. ƿ̾������
��9
�ϼ��θ츻���Ϥ���ǽ�Ȥ������ط���̵���Ǥ���
13. ƿ̾������
>>12
���ͥá��������ϼ���>>9���äƸ��������Τ�����
�Τ��ˡ��������⤷��ʤ�����ɤ⡪
14. ƿ̾������
���⤽��ʹ֤�ĺ���ǹͤ����������������
15. ƿ̾������
�ɤ��ưʪ��ʹ֤��¿�����ΤäƤ���פȤ�ï�θ��դ��ä���
16.
17. ƿ̾������
��7
�����ʤ�����ɻҶ����ä����饹���ᤵ���ǹ�������ޤ������ä����
�����Ⱦ���ʿʹֳ����٤�1���ְʾ���ɤ��ݤ���
�Ǹ�ϥ������©���䤨�䤨�ʤäơ����٤ʤ��ʤäƤ��ޤä�
�����ǽ��Ƽ�ʬ���Ҥɤ����Ȥ��Ƥ뤳�Ȥ˵��դ��Ƥ�
�������ˤ⤳���˽��ʡ��Ф��Ƥ���ͤ��뤫�⤷��ʤ�
���줭����ñۤ��ޤ�Į��ο��˷����ޤ��äƤ���
��ʬ���Ѥ�ʤ���ȡ��Х�����ߤ��ȡ��������Ƥ˱��Ф�����ƨ����
���Τ�������ʤ�����ñۤ���ο�����ʬ�Ƥ�ƨ���ʤ��Τ�ߤ�
�֤�����äѤ�����Ƥ�������פäƵ㤱����
�����ο��μ�̿�Ϥ�������1��2ǯ��ʹ������
���줬��ǯ�ʾ�ʿʹֳ����٤�300ǯ�ʾ夫���ˤˤ錄�ä�
�����Ѥ���Ƥ����Τ��������ˤ����ã���ʤ��ʤ��櫓���ʤ�
18.
19.
20. ƿ̾������
>>17
�����Ρ��������ʵ���Ǻ��äƤ����顢���ˤ�������������ФǶ�����Ƥ���
����Ƥ����ڤ�α�ޤä������������ԥ�ݥ���ȤǷ��ȴ����褦�ˤʤ�ȡ����٤����Ф�¾��̱�Ȥ�����Ǥ����褦�ˤʤä��Τǡ����Фˤ�����ϼ���뤳�Ȥˤ���
���̤ˤ��륹����˶�Ť���ƨ�����뤱�ɡ����ޤ���˥ѥ�ʤα¤��ȶ�ޤǴ�äƤ��뤾
�����ܤ�������֤�ɤ�������Ƥ�Τ�Ф��Ƥʤ������
�����ϸ��αؤν�������ˤϳ�ϩ�������������������ˤϤȤ�Ǥ�ʤ��̤Υ�������뤱�ɤӤä��ꤹ�뤯�餤ƨ���ʤ���
Ƨ���٤���ʤ����äƤ��餤�ܶᤷ�ʤ���ƨ���ʤ�