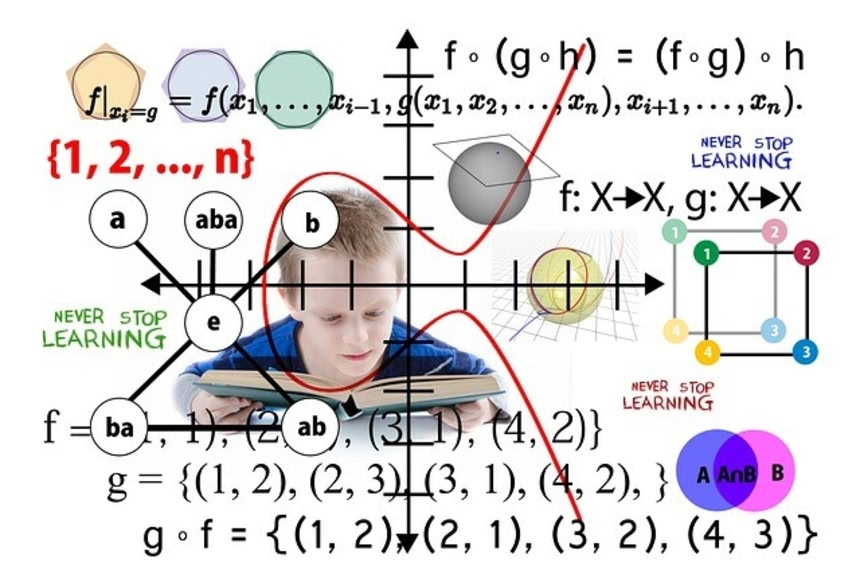 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る数学は得意?苦手?そもそもそれすらわからない?実はあなたの数学的能力を調べる方法があるという。
『PLOS Biology』(7月22日付)に掲載された研究によると、数学の能力は、脳内の神経伝達物質「GABA」と「グルタミン酸」に関係しているのだそうで、それらの量から予測できるのだそうだ。
ただし子供と大人ではその量の比率が真逆となる。子供の場合、GABAが多くグルタミン酸が少ないほど数学が得意であるが、大人の場合はGABAが少なくグルタミン酸が多い方が数学的能力が高いことがわかったのだ。
脳の発達と神経伝達物質の関係
何かを学んだり、技術を身につけたりするためには、脳内の神経細胞同士を新しく結合してやらなければならない。そのために決定的に重要なのは、神経の抑制と興奮のバランスだと考えられている。
ストレスの低減や良質な睡眠にいいとされるGABA(γ-アミノ酪酸)は、主に抑制をうながす神経伝達物質だ。またタンパク質構成アミノ酸のひとつ、グルタミン酸は、興奮性の神経伝達物質である。
これまでの研究では、脳が刺激に敏感に反応してくれる幼少期において、GABAによって作動する神経細胞の成熟が、脳の機能や構造を変化させることがわかっている。
もちろん、学習は幼少期が過ぎてもずっと続いていく。そうした中でGABAやグルタミン酸がはたしている役割はあまり知られていない。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る若い人の場合、GABAが多くグルタミン酸が少ないほど数学が得意
それを解明するべく、イギリス、オックスフォード大学のロイ・コーエン・カドシュ氏らは、6歳の子供から大学生までの255人の神経伝達物質を調べてみることにした。
彼らが調査したのは、「左頭頂間溝」という部分だ。ここは数や数学的な概念の処理に関係があるとされている。
そして判明したのは、”若い人たち”では、左頭頂間溝のGABAが”多く”、グルタミン酸が”少ない”ほど、数学が得意であるということだ。
最初の実験から18か月後に行われた2度目の実験では、これら2つの神経伝達物質の量から数学テストの成績を予測することができたそうだ。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る大人になると逆転現象が起きる
だが面白いのはここからだ。不思議なことに、大人になるとその関係が逆転してしまうのだ。大人の場合、GABAが少なく、グルタミン酸が多いほど数学が得意だったのである。
なぜこのような逆転が起きるのか、その理由は不明だ。しかし研究グループの推測によれば、どこかの時点で数を処理する方法が変わっている可能性があるようだ。
あくまで仮説だが、左頭頂間溝は、主に子供の頃に数的な認知をになっているのかもしれない。だから子供の場合、ここにGABAがたくさんある方が数の処理がスムーズに行われる。
ところが大人になるにつれてそれが海馬へと移り、左頭頂間溝の役割は徐々に減っていく。そのために2つの神経伝達物質の関係に逆転が生じるというのだ。
まだ不明な点が多いが、ことの真偽はいずれ明らかになることだろう。
こうした知見を利用すれば、数学脳の発達を助けるプログラムも開発できる可能性があるとのことだ。
References:Neurotransmitter levels predict math ability / written by hiroching / edited by parumo














親と学校に恵まれるかどうかが99%
ひょっとして公文式よりも手っ取り早い?
「左頭頂間溝」の物質をどうやって調べたんだろう?頭蓋骨を貫通する注射器を使ったのかな?
※4
最近はMRIで脳内のGABAとグルタミン酸の量を計れるらしい
逆に言うと、GABAとグルタミン酸量くらいしか計れないから、今回の結果は各物質が本当に数学的素質と因果関係があるかはわからない
数字を処理する能力と数学の能力は別物では?
※5
確かに。年齢じゃなくて数学と算数の違いって可能性もあるよね。
昔から数学がずっと得意なんだけど、俺の頭の中子供のままなのか?
自分は一応理数系だったのに、大学入ってから数学がさっぱりわからなくなって身の振り方を修正した。
ほんとに急にわからなくなったんだよね。鬱のせいもあったのかな。
※7
大学の数学科の学生の80%は授業が全然わからないそうだ
少なくとも受験~入学までは数学が得意だった人ばかりなのに、だよ
数の処理方法が変わっていくからでは?
例えばだが8+5を幼児は10の位に一つ繰り上がって1の位に3残って~といちいち計算するところを、成人はそれまでの経験から13の答えを即導き出せるよね?
演算によって処理してたのを暗記で省力化するようになったらそりゃあ脳の使う部位も違ってくるよね
子供の頃の数学(算数)は直感的もしくは絵画的な理解が分かりやすい
大人(高校、大学)になってからの数学は論理的思考に基づくもの
タイプが違う
>>10
というかテストに使う問題が違ってるなら、脳の使う部位違っても当たり前なのでは?
どんな問題を使ったんだろう?
※10
数学に必要なのは数学脳。しかも分野毎に全然違うカスタムプロセッサみたいなもの。
論理思考能力は大前提でしかないよ。
論理的思考の発達も関わって来るからだろうなぁ
学力はガチで遺伝やで 結局は親ガチャ
>>14
これはガチ。数学物理できる奴はガリ勉しなくても普通に偏差値70超えたりする。
その他の科目は40くらいだから別に勉強してる訳でもなく、むしろ授業サボってたりする。
数学的な考え方はすき
でも数式見ると頭に霧がかかったようになる
つらみ
※15
ワイの親は両方とも頭よくて成績もよかったらしいけど、ワイは普通にアホや。
なんでや。
これがマジなら俺は多分グルタミン優勢タイプやわ
(子供の時数字が嫌いだっただけかも
俺が若い時は阿保だったけど歳食ってから急に頭良くなったのも似た様な関係が有るんだろか
理系の方が美味しいという認識でよろしいか?
誤字脱字が多かった数学者が、分からない人には分からないし、分かる人には分かるのだから
推敲する意味を感じないとかなんとか言ってたが、なるほどこういうことだったのか
好きでもないのに覚えるわけない!!
興奮と抑制という説明をそのまま信じるなら、
子供→落ち着きがある子は成績いい
大人→知的好奇心が強い人が成績いい
であって、根本的な数学の能力とは関係ない気がする