
����������㳰�⤢�롣�桹�ʹ֤�����1�Ĥǡ��νŤ�Ʊ�����餤��¾��Ӯ�����ꤺ�ä�Ĺ�������롣���ޤ���˵�С��ʹ֤��⤺�ä��νŤ��Ť���30ǯ���٤��������ʤ���
�����ơ������ǰճ��ʥȥ�ӥ������Τ��礭�����θ������硢�ʹ֤�ꤺ�äȼ�̿��Ĺ���ȹͤ�����19���Ӯ����Τ�����18��ޤǤ��������ʤΤ������ϤȤäƤ�Ĺ��������
�����ǯ��������ǯ���������ϡ�
���������֥������ˤ��Ƥߤ�С��νŤ��ڤ��Ȥ����Τ���������������Ϥ狼�뤬��Ӯ����ΰ��̥롼��˽�����̿��û���ʤ�ʤ���Фʤ�ʤ�������ʤΤˡ��ɤ������櫓�������Υ������Ϥ䤿���Ĺ�����������Ȥ��Х֥��ȥۥ��ҥ��������Ϥ��ä�7����ष���ʤ��Ȥ����Τˡ�������40ǯ�ʾ�������롣
����Nature Ecology and Evolution�٤˷Ǻܤ��줿�ǿ��θ���Ǥϡ��������٤���25ǯ�ʾ������륳������ܤ���Ĵ�٤Ƥߤ뤳�Ȥˤ�����
��Ĵ����ˡ�Ϥ�������������ޤ�����դ�μ褷�����������դ��Ƥ��顢�ޤ��������֤���������6ǯ���вᤷ�Ƥ���Ƥ�Ʊ�����Ȥ�Ԥ���
����������100ɤ�ʾ�Υ������Υǡ����ᡢ��ǯ��ˤ����Ƴ��������Ƥ�������Ҥ����פ�������ˤ���պ�˦���Ѳ���ѻ�������

CreativeNature_nl/iStock
�и���Ķ��˱����ư����ҳ������Ѳ����륳�����
���ġ��Υ������ϡ����줾�줬�ۤʤ�и��ơ��ۤʤ�Ķ�Ū�װ����������뤿��ˡ������Ҥγ������Ѳ����롣�������Ǹ���Ԥϡ���������Ǥϥ���ץ����Ⱦ��¸�ߤ�������ҳ����������֤��вᤷ���Ȥ��ˤɤΤ褦���Ѳ����뤫�����ܡ��������顢�����ҳ��������������ۤǡ�����˴�Ϣ�����Τ�9�ѡ�����Ȥ����ʤ��Ȥ������Ȥ��ͤ��ߤ��
��������������9�ѡ�����Ȥ���ˤϡ������Ĥ��ܤ���������Ҥ����ä�������˴�Ϣ���뺹�ۤΤۤȤ�ɤϡ������������礭���Ѳ�����100�ΰ����Ҥˤ�ä��������뤳�Ȥ��Ǥ����Τ���
�������ơ�������DNA��»����������»������������ʤ�ò��������Ѥ���Ȥ�������˦����ݤĥץ������˴ط���������Ҥ��ä���
���ޤ��������ϡ������Τ���ü��ݻ����ơ���˦��Ϸ������Τ��ɤ����ȤޤǤǤ��롣���̡����������ץ������ˤϡ��ƥ��ᥢ�����Ȥ����ƥ��ᥢ���佼������Ǥ���Ϳ���Ƥ��뤳�Ȥ�¿���Τ������������ξ�硢�ɤ��⤳���Ȥ鷺�˹ԤʤäƤ���褦����

fermate/iStock
Ӯ����֤β������
�����������ԻĤ����⤭Ħ��ˤ��뤿��ˡ�����Ԥϥޥ������������ߡ��ҥȤ˴ؤ���Ʊ�ͤθ����Ĵ�١���������Ӥ�Ԥʤä������������顢������4��ˤϡ�����ˤ�ä��ȱ�ȿ�����㲼���롢��ճ������㲼����Ȥ��ä��������Ĥ��ζ����������뤳�Ȥ�Ƚ����
���������������ξ�硢�����3��Ȥϰ㤤������ˤ�äƱ�ɤ����ä���褦�ʤ��ȤϤʤ��褦���ä����ޤ��¸���ʪ�μ�̿���Ф������ҳ����ˤ����Ĥ��Ѳ��������Ƥ�����
Ϸ����Ʊ���˴ⲽ���ɤ�
��������miRNA��RNA��û������ǡ�¾�ΰ����Ҥγ���������ˤ�Ĵ�����줿������������Ƚ�������Τϡ��������Ϻ�˦ʬ������ߤ�����miRNA������������Ĥġ�¥�ʤ������Τ��Գ����������Ƥ���Ȥ������Ȥ���
���Ĥޤꥳ�����������Τ���ü���ۤĤ�ʤ��褦�ݻ����ơ���˦��Ϸ�����ɤ��ʤ���⡢Ʊ���ˤ��줬�ⲽ����������ǽ�ʤۤɤ���Ĺ���Ƥ��ޤ����Ȥ��ɤ��ᥫ�˥������ͭ���Ƥ���Ȥ������Ȥ���

Ocs_12/iStock
Ĺ��������ǽ�Ϥλפ�̥ץ쥼��ȡ�
����������Ӯ����Ȥ���ͣ�졢Ļ���ɤŨ��������ǽ�Ϥ�ȤˤĤ�������ʪ���������������ԤȤϡ���դȤ������Ǹ����������٤ι⤤�٤����Τ��礭������դȼ�̿�˶�����ؤ����뤳�ȤϺǽ�˽Ҥ٤�������դ˹⤤��٤�������ǽ�Ϥ������������ˤϡ���������Ȥ��Ƽ�̿������Ƥ��ޤäƤ⤪�������Ϥʤ���
�������Ƕ�����������ʪ�����ϡ����������⤤��դˤ��������ڸ�������Ȥߤ�ʲ������Ƥ����褦�������Ȥ��Х������ϡ�Ļ�Τ褦�ˡ��������٤ƥ��Υब���Ū����ѥ��ȤˤǤ��Ƥ��롣
���⤷�������顢��������Ĺ���ϡ�����ǽ�Ϥ������줿���Ȥˤ��פ�̥ץ쥼��Ȥ��ä��Τ��⤷��ʤ���
References:Why do bats have such bizarrely long lifespans? | Ars Technica/ written by hiroching / edited by parumo
���碌���ɤߤ���
 �������Τ褦�������Ķ�ε�β��Ф�ȯ������롣�����ˤ϶�ε���������֤���λ�Ժ����κ��פ�������
�������Τ褦�������Ķ�ε�β��Ф�ȯ������롣�����ˤ϶�ε���������֤���λ�Ժ����κ��פ������� ���������ʤ����ΤʤĤ��äפ�ޤǡ������ֻҸ����衪�äƤ��餤�������θ�������������˴ؤ��ơʥ������ȥ�ꥢ��
���������ʤ����ΤʤĤ��äפ�ޤǡ������ֻҸ����衪�äƤ��餤�������θ�������������˴ؤ��ơʥ������ȥ�ꥢ�� ����ǯ��512�С������ǹ��������ưʪ�Ȥ���륵��������Τ�ȯ�������
����ǯ��512�С������ǹ��������ưʪ�Ȥ���륵��������Τ�ȯ������� ��å����ѥ���ϰճ���Ĺ����ǭ�ȥ���ޥ����μ�̿��Ʊ����27������ʪ������ʿ�Ѽ�̿
��å����ѥ���ϰճ���Ĺ����ǭ�ȥ���ޥ����μ�̿��Ʊ����27������ʪ������ʿ�Ѽ�̿ ǭ�������Ĺ��������ͳ��
ǭ�������Ĺ��������ͳ��







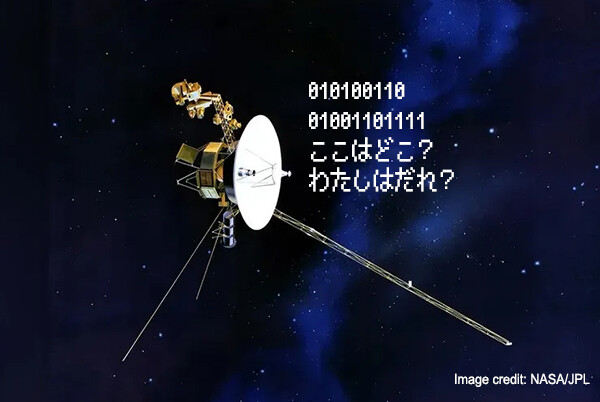
 6175
6175 313
313 11
11 37
37



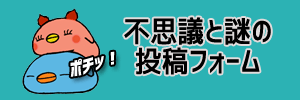





























































������
1. ƿ̾������
�ʹ֤ξ��ϰ��ŵ��Ѥˤ���̿�αƶ��⤢���ʤ���
2. ƿ̾������
�ʹ֤������Ϲ��Ĺ����û̿�ä�ʹ�����������
3. ƿ̾������
���������ϡ�Ķ���Ȥˤ������İ��٤Ȥ����礭��£��ʪ��
��¤�礫��Ϳ�����Ƥ���Ȼפä��褿����
����ʳ��ˤ��̿��Ĺ���Ǥ�ͥ������Ƥ����Τ�����
��äѤꡢ�ɤ������̻뤵��Ƥ�������ʪ�ʤΤ��ʡ��Ȥϻפ�
4. ƿ̾������
����ۥ�Ȥ��ʡ�
Ӯ����μ�̿�Ͽ�¡�Υȡ������ư����ä�ʹ�������Ȥ��뤱�ɡ�
5. ƿ̾������
��1
�������⤢�뤷���Űʳ�����ʬ��빽�礭��
�Ῡ�����̤��礭����
�����οʹ֤Ϥ���ޤ�ǡ������ʤ�����ʤ�Ȥ������
ǭ�Ȥ�����٤�ȥΥ�ͥ��Ȼ��餵��Ƥ�ǭ�ǤϷڤ����ܰʾ�ϰ㤦
6. ƿ̾������
>>2
���Ĺ�οͤ����Ĺ�οͤ���٤Ƥ����Ĥ��μ���Υ���ˤʤ�䤹�������Ϥ���餷����
����϶��餯��Ĺ�ۥ���ȥ����˦��ȯ���˴ط��������ʤ�����
�դ����Ĺ�οͤۤ����¤��ɤ��µ��ˤʤ�䤹���ä��ä�ʹ�������Ȥ���
7. ƿ̾������
19��Τ���18�郎�������Ȥ����Τ�ʬ���ä����ɡ�����ʳ��Τ⤦��郎�����Τꤿ����
�ϥ����ǥХͥ����դꡩ��Ŭ��
8. ƿ̾������
�ǡ����Ф��餤�ޤ��������
9. �̤ꤹ����
����������Ϸ꤬�����䤹��
���ӤΤ褦��ʪ�ȸ����ˤ�;��ˤ��������Ӥ����뤬���Ԥ�٤ˤɤ����Ƥ�ɬ�פʿ���Ϥ�ͤ��Ƥ⿶��Ҥ�Ť��������ˤ⤤���ʤ�
�鲼���ä����ü������
��ʪ�Ȥ��ƺ���ǽ�Ϥγ�ȯ��ͥ�������ä�����˷����֤�������(Ϸ��)���Ѥ����Τ�ɬ�פȤ��Ƥ����Τ��Ȼפ�
����ץ������������˿�����������ʬ�ۤ����ΤǤϤʤ����ʡ�
ʿ��Ū�ʼ�̿���礭���ϰۤʤ�ʤ���Ĺ�����������Τ�ȯ��Ψ���⤤�Ȥ���
10. ƿ̾������
��4
���͡�
�֥����λ��֡��ͥ��ߤλ��֡ס�
��4
����Ǥ��Ѥ��������ϼ����Ƥ��ޤ���
���������դǤ��ꡢ���Ǿ�����Ȼפ���
�ͤ���Ϥ�ⵤ�����Ӥ���Ĺ��������ʤɤ��������ǡˡ�
11. ƿ̾������
Ĺ�����Ǻ�˦��٥�Ǿ�˼㡹�����Ȥ���
�������۷쵴���äߤ����Ǥ��͡�
�۷쵴�����������ѿȤ����ꤹ���ä�
���߽Ф��줿����ˤ�Ƚ�ä�̵���ä��Ϥ��ʤΤˡ�
�����������¤ȶ����Ǥ��Ϻ���̤äƤ�Τ�
������̣�����ä��Ǥ���
12. ƿ̾������
�ʤ�Ĥ��ȡĥ������϶�������ǽ�Ϥ����Ǥʤ���
�ΤνŤ����Ф����̿��Ĺ���ޤ�Ļ��Τ褦�˼��̿ʲ����Ƥ����Ȥ����Τ�������
�����Ļ�ब���Ǥ���褦�ʤ��Ȥ�����Сʤ���Ϥ����餯���ꤽ���ˤʤ�����
��̤�����ζ��ˤϥե롼�ĥХåȤΤ褦�˻�Ф�ȯã����������꤬��¿��������褦�ˤʤ�
��������������Ĥ������Ĥ�����ե�ʿ��̤�ޤȤ��ᰦ���륳����꤬������뤫�⤤��ʤ�
13. ƿ̾������
������ꤵ��
������ꤵ��
14. ƿ̾������
��̣���狼��ʤ�
��ȿ�ФΤ��ȽƤ���
����դ˹⤤��٤�������ǽ�Ϥ������������ˤϡ���������Ȥ��Ƽ�̿������Ƥ��ޤäƤ⤪�������Ϥʤ���
��⤷�������顢��������Ĺ���ϡ�����ǽ�Ϥ������줿���Ȥˤ��פ�̥ץ쥼��Ȥ��ä��Τ��⤷��ʤ���
15. ƿ̾������
���䡢������ѥ����ߤ������
16. ƿ̾������
�֥��ȥۥ��ҥ��������Ϥ��ä�7�����
���ä�7������Ӯ���ब�ޤ��Ӥä���
�����1/2���餤�νŤ���
17. ƿ̾������
��10
���֤äƻ��ϡ�������դ����䤵���������汿ư�⤻���ͥåȻ�������褬Ĺ����������äƻ��Ǥ���͡�
��
�缣��֤ʤ��������ޤ�����ʻ������Ƥ�Ǥä��������ø����ΤƤ뤾����
18. ƿ̾������
�Ҥ�äȤ��ơ��������μ�̿��(�ʹ֤��ν�/���������ν�)�äƤ��������ʤ顢���������νŤϤ��ޤ�˷ڤ����顢�ͤ���٤ƶ�ü��Ĺ�����Ȥ��������ǤϤʤ���������
�⤷�����Ǥʤ���С��ȤäƤ������á�
19. ƿ̾������
�ե롼�ĥХåȡ��Ȥ����äƤ�ͤΤϲ�ǯ�����Ƥ�����
20. ƿ̾������
>>3
��¤��Ƥʤˡ�
���륫�����̤ʤΡ�
�ʹ֤��ü쵻ǽ�ǥ���å����Ǥ�������Ķ���Ȥο������������뤱�ɡ��������¤��Τ�Ƴ���ʤΡ�
�Ǥⲿ������θĿͤˤ������ä�Ϳ���ʤ��Ρ�
��¤��Ϻ���Ū����¤�ʤΡ��ʤ�Dz��ä�����ʪ�ˡ�Ϳ���ʤ��Ρ�
�ʤ�Ǽ��������Τ褦���Ը�ʿ�������ˤ����Ρ�
21. ƿ̾������
��1
����ʸ��������ŵ��Ѥ�Ȥä���ʿ�Ѽ�̿40���餤�ˤʤ�餷����
22. ƿ̾������
���٤�褦�˷ڤ��ʲ����Ƥ��뤫��ñ�����Ӥ���ΤϤ�������
23. ƿ̾������
��֤˻糰���Ӥ�����Ƥ��ʤ����餫��͡��դ��ޤǤ褯����Ȥ����ʹ֤ˤ⻲�ͤˤʤ뤫�⤷��ʤ���
24. ƿ̾������
>>14
�����ʤ����Ԥˤ����٤��������̿�������Ϥ�������ɡ��������Ϥ�����䤦Ĺ��̿��Ϳ�����Ƥ��롢�Ȥ�����̣�Ǥϡ�������������ǽ�Ϥ˲ä�Ĺ���������롢�Ȥ��������Ǥ��礦��
��ȿ�ФΤ��Ȥ���äƤ���櫓�ǤϤ���ޤ����
25. ƿ̾������
>>14
�����������ɤߤޤ�����
�ֶ�����������ʪ�����ϡ����������⤤��դˤ��������ڸ�������Ȥߤ�ʲ������Ƥ����褦�������Ȥ��Х������ϡ�Ļ�Τ褦�ˡ��������٤ƥ��Υब���Ū����ѥ��ȤˤǤ��Ƥ��롣��
26. ƿ̾������
�֥�����ꤵ�����ơ�������ꤵ���
�֥�ϥϥϥϥϥϥϥϥ�〜〜�סʹ��ˤʤäƤ�ҡ�������Ū�ʡ�
27. ƿ̾������
��7
������ʸ���ɤ���櫓�ǤϤʤ��������餯�̶˥����餫�ʡ�
28. ƿ̾������
��20
��¤�礬�錄�Ȥ��ơ��ɤ��������Ƥɤ��ͤ˹ͤ��������ʤ�ơ���ˤ�ʬ��ʤ��衣�������������ݤȤ��ơ����������Υ롼������ߤ������������Ƥ�¸�ߤ�ʿ���˰����٤Ȥ����Τϡ��ʹֳ�Ū�ʥ롼��������͡��Ǥ�ʸ����ȯã�����Ӿ��������Ȥ����Τ����ޤ������Τ������Ȥϻפ����ϵ������ʪ�˰�줿���ˤ��뤿��ˡ��������Υ롼��Ȥ��Ƥϡؼ��������Υ롼���ɬ���Բķ���ä��٤Ȥ������������͡�
29. ƿ̾������
>>13
��ϥϥϥϥ�
30. ƿ̾������
������19��λĤ���ϥϥ����ǥХͥ��ߤǤ���(��̿��30ǯ)��
31. ƿ̾������
☝️ ή�Ф˥ϥ����ǥФ��Ͽʹ֤�����Ĺ������
👇