
Tanes Ngamsom/iStock
�����ͥ���ΰ�̾����������ҥ�����Ʊ°����Ǥ����������ߥ����ʳ�̾ Solenopsis geminata�ˤϡ������ҥ���Ʊ�ͥ�����å��֤ǡ������������Ȥߤʤ��ȳ����դ����ꡢʢ���οˤǻɤ����ꤷ�Ƥ��롣���������ߥ���⥢���ҥ���Ʊ�͡��ǰפγ���ˤ�ä��������Ϥ�ȯ������Ƥ��ꡢ��άŪ�ʳ����Ȥ�������ˤʤäƤ�������ܤǤ�������������ȯ�����줿�ˡ�
���������ߥ��꤬���������Ϥ˿��������Ȥ����㤬�¤��Ƥ��뤿��˶�Ƹ��ۤ�������ʤ�������ȡ��Ҷ��˰���Ū�����꤬�����䤹���ʤꡢ������¸������̤Ȥʤ롣
���ǤϤɤ�����Τ����ǿ��θ���ˤ��ȡ��������ߥ���϶������뤳�Ȥǡ�����Ū¿������˳�����Ȥ����������ۤ��褦�Ȥ���Τ���������
��ä�����Τ������ΤΥ���
���������ߥ��꤬�������Ϥ���礹��ˤϡ������������ͤФʤ�ʤ������Τ���ˡ���������ϸ�����Ѥޤ��ȿ�ŷ�Ϥ���ƶ�������Ω�äƤ�����������ϴ�����ιϩ�����Ῡ�Ԥ��Ĥġ������Ŭ�������Ĥ��ͤФʤ�ʤ��������ơ�®�䤫��̼�ʡ�Ư������ˤळ�Ȥ��Ǥ��ʤ���С�������������餺��������ˤ��뤷���ʤ���
�����������2�������ࡣ�������̤������ǡ����Ԥ����Ư������Ȥʤ�������Ԥ���ϴ���Ū�˸����Τ����¸�ߤǤ����ʤ����������ޤ�롣
���椨�˥�ˤϳư����ҤΥ��ԡ���2�Ĥ���������Ρˡ������ˤ�1�Ĥ����ʤ���ñ���Ρˡ�
���Ȥ���������������ȸ������η��ط����ᤤ�ȡ������������ᥫ�˥���η�٤Τ����ǡ��������Ⱦ����Ư������ǤϤʤ������ΤΥ�����ȯã���Ƥ��ޤ���
����Ҥ����Ȥ��ꡢ������ô�����Ͻ�������Ȥθ������������������褦�ʤ��ȤϤʤ��������ޤ���Ȼ��Ǥ��ޤ�������ǽ�ϥ����Ǥ��롣
������ʤΤ˺��ä����Ȥ������ΤΥ����ϡ���ǥ�ʾ���ð�Ū�Ѱۤΰ�Ĥǡ��������Τ��ð�Ū������ǽ�Ϥ��ѰۡˤǤ��뤳�Ȥ�¿���������¸�߰յ�����̤����ʤ��������Ĥ��Ǥˡ����������Ư������Τ�Τ����礭�������ӿ��餤�������ʤ����Ԥ���
������������ۤ����ȴ�ĥ�äƤ����������ϡ������᤺���Ҷ�����ʤ�������Ǥ���äȤ������ʤ���������ɤ������Τ��礭�����������Ω���ʤ��ۤ˥�����Ϳ���Ƥϡ����Ťʻ�̵�̤ˤ��뤳�ȤˤʤäƤ��ޤ���

�������ϥ��������ʸ�Ȥϴط�����ޤ���cturtletrax/iStock
Ư������Կ���ʪ�ˤʤ롣�ΤƤ�줿��票���Ȥʤ륪��
���������ȥ�ꥢ�Ǥ⡢�����Ƹ����Υ������ߥ���ʤɤΥҥ���ο���������ȤʤäƤ��ꡢ���ζ����ʤ��ϸ������ַϤ��뤿��ˡ���������Ĵ�����Ԥ��Ƥ��롣�����ΰ�ĤȤ��ơ��������ȥ�ꥢ���������ॺ�����å���ؤθ��������ϡ���������������夷���������ߥ�������Ĵ����10ɤ��8ɤ�������ΤΥ����Ǥ��뤳�Ȥ�Ƚ��������
�����������Ϥ���˸��������Ф���ν�������1187ɤ�ᡢñ�Ȥ��뤤��¾�ν�������Ȱ�������餻�Ƥߤ���
�����η�̡������ΤΥ��������ޤ줿���34�ѡ�����Ȥǡ��������꤬�����ΤΥ���������Τƾ���֤��ơ�Ư�����������ȳ�Υ����Ȥ������ѻ����줿��
�����꤬������֤λ��¾����֤�����Ƥ����ΤϤ褯���뤳�Ȥ����������������ߥ���μΤƤ�줿�������������������Ǥߤ�ȡ��ʤ�Ȥޤ������Ƥ����ΤǤ��롣
���������������ϼ�ʬ��©�Ҥ�����ΤƤ������Ǥʤ����ɤ���鿩�äƤ���餷���ä����ѻ������Ϥ���Ƥ���12������ˡ������ΤΥ���������109ɤ�Τ���4ʬ��3���㤫��Ѥ�ä��Ƥ����Τ���
�����λ�����������ä��ΤϽ������ꤷ�����ʤ����Ȥ������Ȥϡ��������꤬�����ΤΥ����٤�����Ư�����������˥����Ȥ���Ϳ�������Τɤ��餫���Ȥ������Ȥ���

�������ϥ��������ʸ�Ȥϴط�����ޤ���HonBK1988/iStock
�������ˤ�ä�̵�̤餷�����������Ư������˱��ܤ�Ԥ��Ϥ餻��
�����������������ˤ�äơ����¸�ߤ�����ܤ�������꼫�Ȥ����������Ū����֤˺��ٿ���ʬ���뤳�Ȥ���ǽ�ˤʤ롣�������ΤΥ���������ϡ��ޤä�������Ω�������Ȥ����Τˡ�Ư��������������¿���α��ܤ�ɬ�פȤ��롣
�����Τ���˼¸�����ͽ�ۤǤϡ������ΤΥ�����������ޤ줿��Ǥϡ������Ǥʤ������٤ơ�����������νŤ��ڤ��Ϥ����ȿ�¬���줿��
���Ȥ����������ǤϤʤ��ä��Τ��������ơ������餯���θ����ϡ��������꤬��ʬ�λҶ������٤Ƥ��뤫��ʤΤ���
���ʤ���������Ʊ�ΤǶ��Ϥ�������餻���������Ǥϡ�Ư�����꤬¿�����ޤ�뤳�Ȥ��狼�ä���
���ʤ����ǥ���������������ޤ줿�Ȥ��Ƥ⡢��Υ��С���������Ӥ��ǽ���Ϲ�ޤ�Ϥ�����
������ʤΤˡ�6�ѡ�����ȤΤߤǤ��뤬�����ϴط�����þ������⤢�ä��������Ǥ������ν������꤬������Х�Х�ˤ���Ƥ��ޤäƤ�����

�������ϥ��������ʸ�Ȥϴط�����ޤ���ApisitWilaijit/iStock
���������������Ʊ�Τ����Ϥ�����ͳ
����ǥ���������������ȤȽ�������Ʊ�ΤǶ��Ϥ��ƻҰ�Ƥ뤳�Ȥϡ���Ƹ��ۤ��뤿��ι�ư�ᥫ�˥�����ȹͤ����롣��������3���ܤβ�ǽ���Ȥ��ơ���������˽�������¿���Υ����ȸ�����������Ϳ����Ȥ�����̣�⤢�뤫�⤷��ʤ���
������ϼ�ʬ�Ȥϰ���Ū�˰ۤʤ륪���ȸ����Ǥ����Ψ��夲�뤿��ˡ������ΤΥ������������ǽ�������뤳�Ȥˤʤ��������
���������꤬��������Τϡ��㤫������Ω��ľ�������������ΤȤ��ּ���ǹ�פȤ����ﴱ�˥��������Ҥ��ߤ��Ƥ��롣
�������ǽ�������40ɤ�μ���ǹ���齸����Ҥ�����Ҳ��Ϥ���������ʣ���Υ����ȸ����������Ȥ��ڵ������줺��3���ܤβ���ˤĤ��ƤϤϤä��ꤷ�ʤ��ޤޤ���

�������ϥ��������ʸ�Ȥϴط�����ޤ���chokchaipoomichaiya/iStock
�������ȥ�ꥢ�˿��������ҥ���ˤ���ﳲ
�����ߥ������ȥ�ꥢ�Υ�����⥢����ճ������ˤϥ������ߥ��꤬���夷�Ƥ��ޤä����������ϥ��ߥ���䥦�ߥɥ�ν��פʻ�����Ǥ��ꡢ���ޤ줿�ƤΥ����ҥʤ�����˹��⤵���Ȥ���ͫθ���٤����֤������Ƥ��롣
���ޤ��Ρ�����ƥ�ȥ�����������ɽ������������ȥ�ꥢ���ˤ���餬�˿����䤹���Ķ������ꡢ�����ˤ������ַϤ����Ǥʤ������ͤ������ⶼ�����Ƥ��롣
�����10ǯ�֤ǡ��������ߥ����к��Ȥ�����311���ߤ���䤵��Ƥ�����������ˤ��������Ƥ��餺���ʹ֡���ʪ���������ؤ��ﳲ��ǯ����1240���ߤ��»���������Ƥ���Ȼ����Ƥ��롣
���������夷���ҥ�����䤹��Τ��ưפǤϤʤ�����ݤǿ����ߤ�뤳�Ȥ����ڤǤ���Ȥ褯�狼��������
�����θ���ϡ�Scientific Reports�٤˷Ǻܤ��줿��
References:Cannibalism helps fire ants invade new territory/ written by hiroching / edited by parumo
���碌���ɤߤ���
 �ä��٤��ϥꥱ�����к������祤��������夲��άŪ��ư��Ϥ��ҥ��ꤿ��
�ä��٤��ϥꥱ�����к������祤��������夲��άŪ��ư��Ϥ��ҥ��ꤿ�� ���곦�ˤ����ʼ���������ޥ��٥쥢��Ͻ��Ĥ�����֤��Ť����������Ƥ������Ȥ�Ƚ���ʥɥ��ĸ����
���곦�ˤ����ʼ���������ޥ��٥쥢��Ͻ��Ĥ�����֤��Ť����������Ƥ������Ȥ�Ƚ���ʥɥ��ĸ���� Ư���������40��Ϥޤä���Ư���Ƥ��ʤ���������ˤϤ������ͳ�����ä����Ƹ����
Ư���������40��Ϥޤä���Ư���Ƥ��ʤ���������ˤϤ������ͳ�����ä����Ƹ���� �����Ǿ������ƹ�ư���Ѳ������뤳�Ȥ�����������Ū�ˤϿʹ֤ˤ���Ѳ�ǽ�Ȳʳؼԡ��Ƹ����
�����Ǿ������ƹ�ư���Ѳ������뤳�Ȥ�����������Ū�ˤϿʹ֤ˤ���Ѳ�ǽ�Ȳʳؼԡ��Ƹ���� ������Ρְ����Ҳ��ѥ���פǡ�����ʣ���ʺ���Ҳ�οʲ�������������Ƹ����
������Ρְ����Ҳ��ѥ���פǡ�����ʣ���ʺ���Ҳ�οʲ�������������Ƹ����









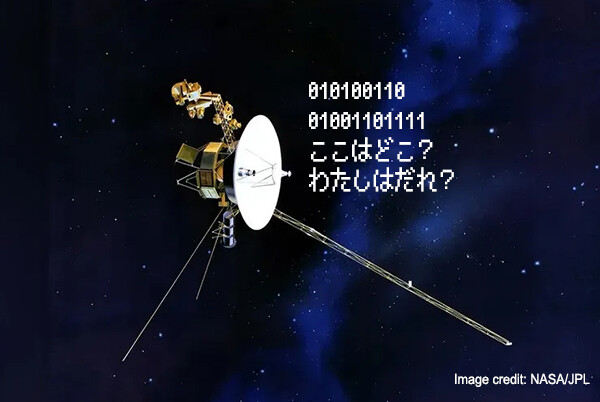
 6175
6175 313
313 11
11 37
37



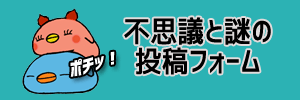





























































������
1.
2.
3. ƿ̾������
�ͤ��������ߥ�����ä��鴰���˿����Ƥ����������ʤ�������
�ʹ֤Ǥ褫�ä�������
4. ƿ̾������
�ʹ֤����Υ���ȥ����ˤʤä��Ȥ��������ˤ⤪���ޤ����ۥ顼�Dz�ˤʤ��
5.
6. ƿ̾������
2���ܰʹߥĥ८����μ̿���
7. ƿ̾������
���ꥯ�� �ä� �ҥ���� ���٤ʤ��Τ��ʡ�
8. ƿ̾������
�������鿿���ܤ�Ư���ޤ����⤰�⤰
9. ƿ̾������
>>7
���٤�衣
���٤뤱�ɡ����ꥯ���ϱ¤ˤʤ�¤θ��ο���ݻ����뤿��ˡ���������ε��ͤ��龯�����Ŀ��٤뽬�������롣
�Ĥޤꡢ���ꥯ�������Ƥ�ҥ���Ϻ���Ǥ��ʤ���
10. ƿ̾������
�ϥ��ϥ��Υ���饢��Ȼפ��Ф���
11. ƿ̾������
�����ΤΥ������ɤ�����Ƚ������������
12.
13. ƿ̾������
��9
���ꥯ�������ʤ�
14. ƿ̾������
�����Ω���ʤ�̿�ʤ�Ƥʤ���❤�פäƤ��ȤǤ���ͤ狼���s
����Ȥ��ϥ��μҲ�äƤۤ�äȤ褯�Ǥ������Ƥƶ�������
���Τޤʹ֤��֤�����������Ǥ�����Ǥ�ǥ����ȥԥ������Dz褬�Ǥ���
�Ĥ���¿�����Τ��������ˤ��褦�Ȥ����ͤ�����ޤ�����ǡ������μ¤ˤ��ä��Ρֹ��٤�ʸ�������줿�Ҳ�פ��������ͤ����äƤ������ɤ⡢���줬���Ϥ����ä���ɤ��ʤ�������
���Τޤޱ�³����Τ�����ͳ��������μ���椨����������ȿư�Ǹ���Ū�ʼҲ�����Τ��������ιԤ��Ϥ����Ȥ���Ǥ�¿�����Ȥ���̷����Ϻ����Ƥ����Τ���
15. ƿ̾������
�����ΤΥ����������Ϥο����Ԥ����餫����Ʈǽ�Ϥ��С����ꤷ���˱ɤǤ���¸�ߤȤ��ƽ��Ѥ������¦�ˤʤ��Τˤ�
̵�̤ˤǤ����������㡢���Τޤޱ��ܤˤ���뤷���ʤ���
16. ƿ̾������
�۴ķ��Ҳ�
17. ƿ̾������
���ܤǤ��к����Ƥ�Τ���
18.
19. ƿ̾������
�ޤ�����δĶ��б��ϤäƤ��������
��Ĥ��Ƥ�櫓�Ǥ�ʤ��Τ���ǽ�����ǽ��Ĥ���Ū�ռ������줵��Ƥ��������ԻĤ���
20. ƿ̾������
�̾ﳰ���齸��Ƥ���������;�ä���ΤϤ��줾��θ��Τ˻��äʤɤη����ߤ����ꡢ���Τޤ����ߤ����ꤹ�뤱�ɡ��Ҷ��ߡ���������Ȥ�����ˡ�⤢��Τ���
���äˤ���ȸ��Υ��������礭���ʤ�dz�����ʤ�ǥ��åȤ������Τޤ����ߤ�����ˡ������ʪ��ʬ��Ʊ��ܲ��������ǥ��åȤ�����
�Ҷ���¾����ʪ�˿��٤��Ƥ��ޤ����������뤱�ɡ�����ʤ�Ф��δ����Ͼ��ʤ��Τ�ͭ�Ϥ������ˤʤ�Ȥ������Ȥ�
��ǤϤʤ������ˤ�����䤬������Τϥ��������¤�����Ȥ��⤤�Ȥ������Ȥ�������
21. ƿ̾������
��������ѻ����Ƥ�Ƚ������꤬���������㤫��Ф����ˤʤä��������꤬����ƤƤޤ������˰��ù�����ꤷ�Ƥ� ����������ȤäƤ����ʤ��äƤ���ߤꤷ��
22. ƿ̾������
�뺧���ʤ��ä���˪�⥨����Ϳ����줺
�㤫����Ƥ����
23.
24. ƿ̾������
����Ω�����ǡ����ΤФ���ǥ����ơ�����Ӥ�����
���������������������ˤ���
25. ƿ̾������
>>3
������衢���ߤ������ä��ʡ�
26. �̤ꤹ����
>>15
�¤���ϥȥ�ͥ���ȹͤ���Ȥ����ǥ��������Ǥ�ƻ��ɤ��ˤϹ��Թ�
���������Υȥ�ͥ���̤äƤ�äƤ��뿯ά�ԤϾ��ʤ�
��˥����Ȥ��Ƥ�褦�ʥ��ꥯ�����Ͼ夫���˲����Ƥ������ͤ���������Ĥ��Ѥ��ʤ����Խ�ʬ
27. �̤ꤹ����
>>16
�����ޤǰ�Ƥ������ε¤λȤä������Ʋ�����Ƥ�ΤǤϤʤ���������Ϥ��뤬
�˿����˥�����ɬ�פʥ����ߥȿ��Ȥ�˳���������Υ����ߥȤΥ���ˤ�äƤ����ˤ�����¢�ˤȤ��Ƥ����Ϥ���ޤ���
�����̤ιͤ����Ǥϥ��������äƤ���ƤǤ����ǽ��������ޤ�
28. �̤ꤹ����
>>20
ʢ����ʬ���ߤ���¾�ε¤ˤ���뤷³����褦�ʵ¤��ޤ���
�¤˶ᤤ��ˤ�˪������������˥��ͥ륮���뤹������ǽ�Ǥ�
�������������ο��餷�Ƥ�褦�Ǥ���
�����������μ��������Ѥ�����ʣ��������ǽ餫�黺��ʬ���Ƥ����ꥳ��ȥ����뤬��ǽ�ʻ��˿����椬���ޤ��
29.
30. ƿ̾������
>>19
�ʹ֤˴�¬�Ǥ��벻������ꤸ��ʤ������ǡ����줳�������Ȥ��ǥ��ߥ�˥���������ΤϤȤꤢ�äƤ��ʤ����ʡ����֤�
����˪��ɤ����������Х�Х�ˤʤäƤ뤳�Ȥ����롢�Ƥ����Ρ�˪����������Ȼפä�
31.
32. ƿ̾������
����������ʾ������ΤΥ����ΰ���������ʡ�
33. ƿ̾������
���⤽�⥪����Ư���ʤ����٤��Ȥ��ƿʲ����Ƥ���Τϲ��Τʤ����
�����������ʳ��λŻ��Ǥ�Ư���褦�˿ʲ������������Ω�ä����ʤΤǤϡ�
34. �̤ꤹ����
>>33
Ĺ��Υ�����Ԥ����Ῡ�Ԥ��⾮���ʥ��õ���Ƹ�������̵�������ô�äƤ���
���ο���̵����ꤳ�ʤ��Ƥ�Τ��Ȼפ�����¾�ε�ǽ����ܤ�����ǹ�³��Υ���㲼�����ꤹ�뤫�⡩
�㤬�ᤤ���ǤϹ�³��Υ��û���Ƥ�����ˤʤ�ʤ����ɿ峲�ǹ��ϰϤε¤����Ǥ����Ķ��Ǥ���Ω�����αƶ��Ͽ������ˤϷ��Ԥο��˸����Ȼפ�
35. ƿ̾������
>>33
�ʤ������ñ�̤ǰ�Ĥ���̿�Τߤ�������͡�
�����ϡ��å��������Ǥ��ʤ������Ư�������Ǥ��ʤ������������ष���Ǥ��ʤ���
���ʤ����ɤ��ɤ������ʸĤ��������˦��ǡ������
��̿������ʤ�Ƥʤ�����Ȼפ蘆���衣
36. ƿ̾������
��27
�����ˤ�����¢��
Ʊ����ʤΤ�Ʊ˦����←�Ȥ������ޤ�ƻ�̱�̿�äƿʹ֤δ���Ū���ܤǸ���Ȥʤ�Ȥ⤤���ʤ��ʡ�
�Ǥ⡢��35 �θ����褦��¾�Υ��������äƤҤ������Ĥ������������뤿������������ƻ�̤������
����ΰջ֡ʤȤ���ɽ����Ŭ�ڤǤʤ����⤷��ʤ����ɡˡ���ΰջ֤Ȥ�����ΤϤ��äƤ�Ĥʤ�Ƥ�ΤϤʤ����������
37. ƿ̾������
������Ƥϥ����ȤʤΤ�
38. ƿ̾������
�ߥĥХ����ä��ߤ����ˤʤ�ȥ������㤫���ɤ��Ф��������ˤ��뤫�顡�¤������äƤ��ԻĤ���ʤ���
39.
40. ƿ̾������
>>30
�¤ⲻ�ǥ��ߥ�˥��������ȤäƤޤ��衣����ʢ�δ֤˥��������Τ褦�˻����碌�Ʋ���Ф��ﴱ������Ԥ�����褦�Ǥ���
����Ȥ��ƻȤ��Ƥ�������ꤵ�줿ʪ��40����ʾ���ä����ȵ������Ƥ��ޤ�
�ϥ��ꥢ����Ȳ���Ф��ʤ��褦�������롼�פϥե�������Ȥ��ʤ��������롼�פ���٥��Υ����ݤ����ä������ˤʤꥫ�Ӥ�������ʤɺ��ݤ��Ƥ��륭�Υ����������ʤ��ﳲ���礭���ä������Ǥ���