 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る我々はどのように記憶し、どのようにその記憶を忘却するのか?アメリカ・フロリダ州にあるスクリプス研究所の研究チームは、ミバエを使って、脳の記憶に関する研究を行っている。
彼らがシナプスという神経細胞同士の接合部分の変化を解析した結果、たった1つの神経細胞が記憶に関する学習プロセスと忘却プロセスの引き金を引いていることが明らかになった。
「このシステムは、重要性が低く、かならずしも長期間保持している必要のない記憶を削除するためのものだと考える」とスクリプス研究所のジェイコブ・ベリー氏。
「このすべてを同じニューロンでやるのだから、エレガントである。」
ドーパミン神経細胞が記憶に関与することが明らかに
ベリー氏率いる研究チームは、特定の臭いで電気ショックを連想するようにミバエを訓練した。
すると、ミバエはその臭いを避けるようになった――これは記憶が作られたことを意味する。
そのときの神経細胞の活動を解析した結果からは、学習プロセスでシナプスの変化を助けるドーパミンが、逆に作用して行動記憶を劣化させていることが判明した。
このことは、単一のドーパミン神経細胞が新しい記憶を形成し、さらに古い記憶を劣化させるよう作用していることを示している。
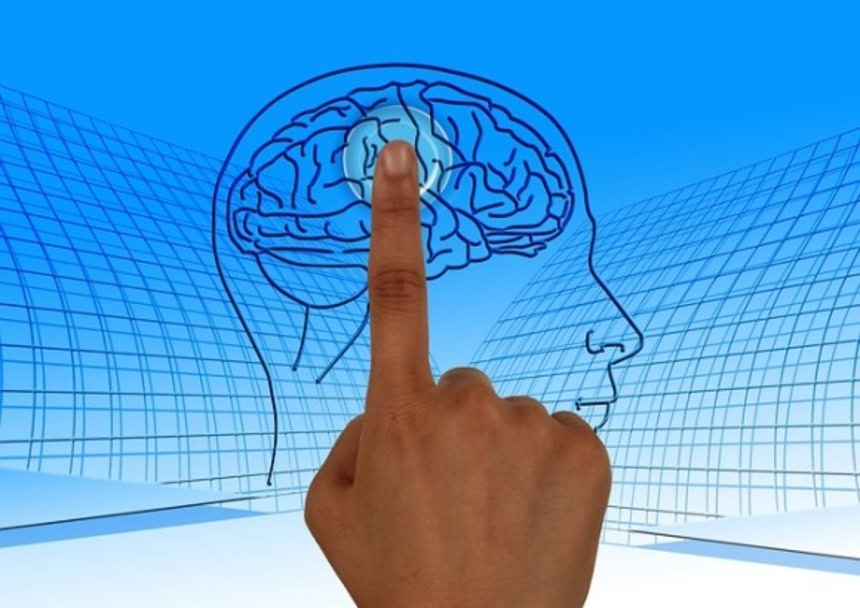 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る積極的な忘却の重要性
積極的に忘れるよう仕向ける機能は、最近になってようやくその重要性が専門家によって認識されたものだ。
ベリー氏はこうしたプロセスついて、「バランス作用」と表現する。
何か新しいことを学習すると、新しい記憶を形成しつつ、同時に古い記憶に干渉し、消去している。
これは抱えきれないほどの記憶が形成されないようにする非常に重要な作用だという。
実験結果はミバエに関するものだが、人間のような高度な生物にもあてはまるだろうと研究チームは考えている。
この研究は専門誌『Cell Reports』に掲載された。
References:eurekalert/ written by hiroching / edited by parumo
追記:(2018/12/8)本文を一部訂正して再送します。
















脳とかいう永遠の謎。
抱えきれない程の記憶を消してうんたらかんたらがバランス効果と申すが、拙者が聞くにパーフェクト脳の人は記憶を忘れられずに膨大な記憶があると耳にしましたでござる。
容量の『バランス』なのかはこの実験ではわからないでござるな。
学習にしろ忘却にしろ、記憶の仕事は一つの神経細胞に任せた方が合理的だもんな
資格の勉強しても全然頭に入らないワイ
必要としてないからってのがあるんだろうし
記憶をとどめて置いたりできないからつらい
忘却ばかりで辛いわぁ
忘却すべきことを記憶し
記憶すべきことを忘却する
この理不尽な脳の構造は何処で間違えたのか
記憶には感情が密接に関係しているのは
ゼミの教授がいっていた
ミドーパミンって見出しに書いてますよ。
頭の「ミ」はとったほうがいいかと。
>>9
ドーパン
※11
だから、「ミ」ドーパミンの頭のミを取れって話。
もう取れてるけど。
しかし、この記事は、ドーパミン自体というよりも、ドーパミンを出すA10神経の活動の問題だと思うけど。
A10神経は記憶や学習のルートを通ってるし。
覚えていなければならないことは忘れるのに
しょうもないくだらないことは覚えてる理不尽
私の中の消しゴムと鉛筆は同じものだったのか。
この辺うまくいけばPTSDの治療に使えそう
※14
嫌な記憶は強制的に消す
荒治療だな。ロボトミーを思い出す。
ものの本によれば記憶は憶えていることをレコーダーのように再生するのではなく、その都度覚えている情報をつないで作り出しているらしい。そのメカニズムのために記憶違いや風化が起きるんだと。その細かな情報を憶えるには当時のエピソードや感情が関わってくるともある。
そりゃ情報を羅列するよりも筋道立てた方が「覚える」わなって話。
ああ、たった一度の事で過去の経験則を消してしまうのが早とちりの人なのか。
むずかしいお話はよくわかんない頭をしているんですが
ニューロンにエレガントっていう形容をするのはクールやなとおもいました
1つの神経細胞が司っているなら事故などでそれが消滅した時はその機能も消滅してしまうのか?
これは「おばあさん細胞仮説」でも批判的な見地から言われたことだけど、最近の脳神経回路を模した(不完全ながら部分的な脳シミュレーションとも言える)AIのディープラーニングでは「おばあさん細胞」と思しきノード(神経細胞に当たる)現れた。この件は「グーグルの猫」として有名。
ただ、ディープラーニングあくまで不完全に脳を模しただけなので、そのまま人間などの脳に当てはめる訳にはいかないけど、例えばディープラーニングのおばあさん細胞のノードを消去したらどうなるかなど、これからは実際の脳研究と生身の脳ではできない研究を行える(より正確な)シミュレーション脳を比較研究すれば飛躍的に脳活動の理解が進むはず。
脳の仕組みが完全に解明される日は来るのだろうか