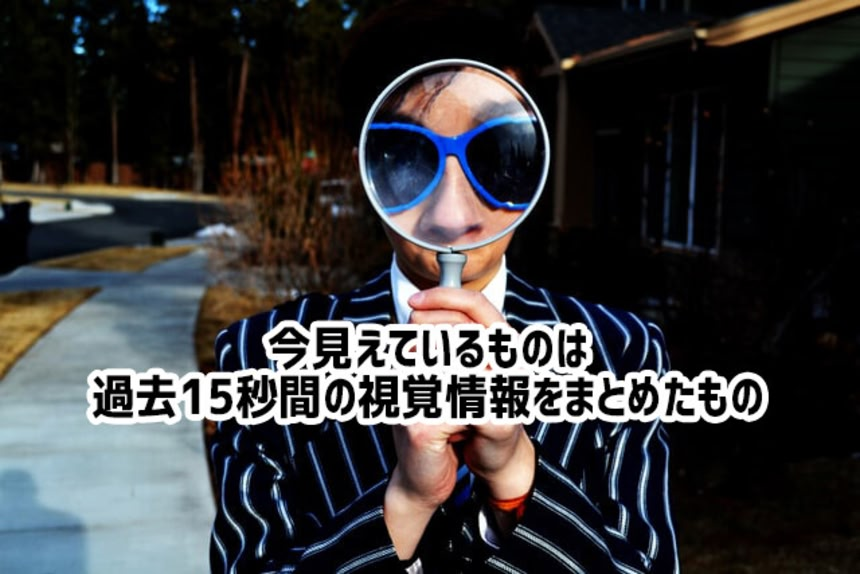 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見るアクション映画の危険なシーンは、俳優のかわりにスタントマンで撮影されることがある。だが公開されたそのシーンを目にした観客が、俳優が入れ替わったと気づくことはほとんどないだろう。
一体なぜ誰もそのことに気がつかないのか? 言われてみれば不思議なこの現象の裏には、驚愕の事実が隠されているようだ。
カリフォルニア大学バークレー校の研究グループによると、私たちがたった今、目にしている世界はリアルタイムのものではなく、過去15秒までの視覚情報を脳がまとめて平均化したものなのだそうだ。
視覚情報を処理するのは脳にとって大変な作業
普段意識することはないが、脳にとって「見る」という行為は、刻々と変化する膨大な視覚情報を処理せねばならない大変な作業である。
その大変さを味わうには、スマホをすぐ目の前に掲げつつ、歩きながら周囲にあるいろいろなものを動画で撮影してみよう。出来上がった映像は目まぐるしく変わる乱雑なもので、それを観ているととても疲れてくるだろう。
あるいは以下の次の動画を見てみよう。画面右側の白い円は眼球の動きを表し、左側は眼球に映った風景を表す。視線があちこちに跳び回るおかげで、眼球に映る風景も瞬間瞬間に切り替わる。脳が処理しているのはそうした視覚情報だ。
脳は過去15秒の視覚情報をまとめて認識している
こうした目まぐるしく変化する膨大な視覚情報を安定して処理するために、脳はあるトリックを考案した。
目に映った風景をリアルタイムで私たちに知覚させるかわりに、過去15秒の平均をまとめて、それを「見た」と知覚させるのだ。
これを証明するために、『Science Advances』(2022年1月12日付)に掲載された研究では、次の映像を使ったとある実験を行なっている。
以下の動画を見てほしい。
映像の画面左側には、女性の顔が映っている。実はこの映像が進むにつれて、女性は少しずつ歳をとる。およそ30秒の間に11才老けていくのだ。
だが、これを見ても、その変化はほとんどわからない。年齢による顔の変化が、実際の映像よりもずっとゆっくり進んでいると錯覚されるからだ。
この実験では、映像を見終わった参加者に女性の年齢を質問してみたところ、ほぼ一貫してその時点から15秒までに見た顔の印象に基づいた回答が返ってきたという。
映像を見ているとき、脳は10~15秒前までの映像を処理したものを私たちに見せている。そのため、私たちの認識は常に過去に偏っているのである。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る脳はリアルタイムで処理せず先延ばしする
研究グループによると、脳のこうした働きは基本的に「先延ばし」なのだという。
目から入ってきた情報をリアルタイムで処理するのは面倒だ。加えて、視覚情報を逐一処理しなくても、ある一時点から未来を予測すれば十分うまくいく。
だから脳は常に約15秒前までの視覚情報をまとめる形で情報を更新しながら、私たちに目で見た世界を認識させている。こうすることで、視覚情報をより少ない労力で、より効率的かつスピーディに処理することができる。
こうした過去の映像に基づく視覚的な認知を「連続野(continuity field)」という。私たちの視覚は、周囲の世界で起きている物事をスムーズに認識するために、あえて正確さを犠牲にすることがあるのだ。
だから映画の微妙な違いがわからない。俳優とスタントマンが入れ替わったことに気づかないのもそのためだ。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る過去15秒までの視覚情報処理のメリットとデメリット
こうした視覚の処理メカニズムには、いい面も悪い面も両方ある。
いい面はすでに述べたように、それによって膨大な視覚情報に振り回されることなく、スムーズかつ安定した世界を認識できるようになることだ。
一方で、正確さが重要な場面では、それが命取りになることもある。
たとえば放射線科医は、数百枚というCT画像に映る異常を見つけて、病気を診断しなければならない。
人間の視覚情報処理がリアルタイムでなく、常に15秒前までの情報だけを見続けるのだとすれば、それは重大な病気を見逃すことにもつながるだろう。
私たちの視覚は、想像以上にゆっくりとしか更新されておらず、そのために目の前の小さな変化に気がつけない。
世界が安定して見えるのはそのおかげだが、それは現実の正しさと引き換えとなっているようだ。
References:Everything we see is a mash-up of the brain’s last 15 seconds of visual information / written by hiroching / edited by parumo
追記:2022/02/09:記事の一部を訂正して再送します。
















その15秒間への無意識のリアクションが「哲学ゾンビ」のなんちゃらっていうやつなんでしょ?
脳生理学って面倒くさいな 電話交換手で良いじゃんもう
「お前はもう死んでいる」なのか
つまり世界は5秒前に作られた!!!!!
ΩΩΩ!!!
聴覚の方はどうなのだろうか
机から転げ落ちた消しゴム等を見てから「あ、まずい」と空中キャッチするのだけど、同様に何某かの乗り物を運転中とかどう考えてもリアルタイムで視覚情報を並列処理していないと大惨事ひっきりなしだろうし、そんなの状況に因るんじゃないの?
※5
まあスポーツとか格闘技とかも15秒もズレてたら間に合わないもんな
動体に関しては別で詳細な画像認識は15秒遅れだったとしても
今度は「書かれている数字や色が1~2秒ごとに変化するがそれを正確に識別する」のも15秒前の状態の数字や色を認識してないとならないことになる
日常生活でもこうやって文字を打ち込んでるのも実際にキーをタイプするのと画面の表示を目が認識するのに15秒ズレが発生してるって理屈になる
よく考えなくてもおかしいところだらけの学説だな
それから俳優とスタントマンの入れ替わりはそもそも入れ替わった別人だとわからないように身長・体格・髪型なんかを可能な限り合致させなおかつ顔は極力映らないようにしているのであって
正面から大映りしてるのに一瞬後に明らかに別人の顔になってるのに観客が気付かないなんてのは無い
この研究の場合の被験者がよほど注意力が低く他人の顔の識別が曖昧な人(主役だけでなく脇役の人間も全員同じに見えて死んだ敵のモブと死んでない仲間がごっちゃになるような)ばかりをサンプルにしたのでは?ってほうが可能性が高くなるような凄い疑わしい話だと思う
※14
私も「俳優とスタントマンの入れ替わりを脳が認識できないのは~」って読んだ時点で
明らかにおかしいと思いました。
それじゃかなり別人の体格でも人は認識できないってことになっちゃう。
コメント欄を見ると、元々の論文は微妙な変化をしていく画像に対しての処理を15秒
区切りでまとめてるという内容みたいですね。
>>14
前半については、対象外の話
後半は、わずかな違いに気が付かない事を実験したようなもの
ただスタントもピンキリなので、説明としては不適切な気がする
>>5
けしゴムのデティールを把握しなくても掴めるからね
具体的な映像として認識するのに15秒かかるという話
運転中でも、突然出てきた標識を読み取ってその指示に従うのは無理だけど、とっさに避けるなどはできるという事だろう
>>18
ゲームで唐突に始まるQTEコマンド入力を考えると
研究論文を読んできた
徐々に変化する映像(目に映る物体の変化など)は、過去15秒まで遡った映像から認識されるという内容
実験では静止画像との比較も行っているし、それの認識に15秒かかるという内容ではなかった
だから映画などには影響するけど、スポーツや運転などでの突発的な変化には影響しない
緩やかに車間距離が変化する場合や道路標識の実際の位置などは、本当なら15秒遅れの認識になるだろうけれど、単純な変化なら予測できるのでその遅れをカバーできる
間違ってたら指摘お願いします
>>5 >>16
翻訳と、その元記事だけからの推測混じりですまんかった
突然飛び出してきたものなどについては、この話はそもそも関係なかった模様
これらと同時に、反射行動やらなんやらとリアルタイム処理もやってるわけだな
しかし格闘ゲームのガチ勢は1/60秒単位で技を刺し合い、FPSのガチ勢は144Hzのディスプレイより240Hzのディスプレイのほうが有利だと主張する。
フラッシュ暗算のスゴい人の脳はどうなってんの?
>>8
この実験は、注視してない場合の話
問題が表示されるとわかってたり、合図があったら、その映像処理を優先できるだろう。その分周りが見えなくなるだろうけど
15秒前の映像で車の運転なんかしたら事故だらけやん
スポーツも全く成り立たなくなるやん
アホなん?
>>9
成り立ってる以上、君の考えが間違ってるということになるで
反射行動など、何かしら記憶にとどまらずに処理される行動があるわけだ
そもそも、脳みそは視聴覚などセンサーの入力に応じて筋肉を動かすための器官で、思考とか記憶とかは後付の機能だらね
※12 いやぁ1論でしかない物を全肯定するのやめとけ、そんな考えや研究をしてる所もあるんだなぁ程度に留めとき(この記事にはどこで誰が提唱して追実験で証明されてるとも書いてないが
実際格ゲーしてる時。反射と同時に思考もして人読みをするし、相手と通話しながらそれらの状況をやり取りしてる。
やたら映画で入れ替わりに気づかないと言うが、映画好きはアクション入った瞬間スタントを疑い、顔が映らないカット割りを多用してるに気づいて3秒で気づくよw
>>34
この実験はそういう話じゃないからね
顔が映らないカットで連続性が切れてるし、それを反証にする時点で理解できてないかと
そして実験対象は新しい話でもない
>>34
も一つ
全肯定はしてないぜ
15秒立たないと認識、知覚できない、というありえない話を実験結果と考える事自体おかしいでしょ、という話
まずは自分の理解の間違いをutagaou
攻殻機動隊に影響されすぎてない?
これ翻訳の仕方が悪いのかな?
平常時、パソコンでいうところの待機状態だと処理速度を使いすぎないようにふわっとしているよってことなんじゃないの?だから注視していないと気が付かない現象があるよってことかな?
>>11
10秒というケースもあるようだし、実験の内容からしてそういうことだとは思う
翻訳については原文の通りっぽいから、記事を書いた人の問題かと
翻訳がおかしいんか?
15秒毎ではなく、過去15秒間のデータを処理してるってことじゃないの
アハ体験だっけ?
一秒未満の視界に映ったモノに対する反応は、どう説明するんだろう
以前、視界の端ギリギリで見えた、棚から落ちてきた一升瓶を片手で受け止めた事あるけど、十五秒単位とかだと絶対に間に合ってない筈なんだけど
>>16
モノの細かい形状を認識する前に行動してるんでしょう
15秒云々は記憶に残る情報の話で、行動を起こすのに15秒かかるという話ではないよ。ごっちゃにしてる人多いけど
脳の処理は平均じゃなくて速い部分も遅い部分もある、大まかな動きや物の位置みたいなのはさっさと更新するが、それに付随する情報、色やら細かい形や模様などは後から付随する形で処理されてて、どうでもいい情報ほど遅くなる、だから犯罪現場なんかで大まかな事は覚えていても色や目鼻立ちなど細かい所が抜けてるのはそういう情報更新のずれがあるからだとかなんとか。
犬やら猫やらの肉食動物系が色覚が少ないのは、重要度の低い情報をあえてオミットする事で脳で処理する情報を減らし、その結果視覚の処理速度が上がる事で動体視力が上がってるとか。
時速100kmで走行中の皆様、現在お見えになられている景色は15秒間を纏めたもので御座います。
まあ、この説は間違いだなあ。
>>23
同感。今が旬の例えならアルペンスキーのダウンヒル種目なんかコースによっては時速110kmに達する。瞬時に雪面状況の把握と肉体の機動制御しないとレースにならない
この記事はツッコミ待ちの意図的な「ボケ」を拾ったのではw
>>23
見え続けている標識は15秒前からの予測
それにリアルタイムで大きく更新された映像、例えば飛出してきた車などの情報が差し込まれる
間違ってる事を証明はできないだろう
※29
100km/h×1000=100000m/h
100000m÷3600sec=27.7m/sec
27.7m×15sec=415.5m
415m走行する間の視覚情報を脳の視覚情報更新単位で連続して処理しているとなるよね?
自動車を高速道路で運転した経験が無いことがわかるかな。
この話は、TV番組でクイズにしていた“アハ体験”の話だよ?
サッカーのゲームで15秒経ってると、ゴールされちゃう。
ノーマルヒル飛んでると飛び終わっている。
こういう話で証明の代わりになりませんか。
>>41
ならないです
15秒間の入力をまとめて処理するもので、15秒経過しないと認識できないという話じゃないからね
だからスポーツやゲームを引き合いに出すのはある種の勘違いなの
わざわざ脊髄反射なんて仕組みあるのも、認識し考えてから動くんじゃ遅すぎるからか
スポーツの世界とかでも体は頭じゃなくほぼ感覚で動かしてると聞くし、軍隊でも訓練された動きはほぼ考えず反射的に出来る様になると聞く
手が、身体が覚えてるって多分こういう事なんだろうね
多分この15秒って「直前15秒間の記憶に基づいて現状を解釈し行動する」て意味じゃない?
人間の認識って割と時間かかってるんだよね。
これと違う話で、人間が何かを無意識で決断して実際に行動へ移すラグが「7秒」って研究があった。
脳の動きを観察すればその人の7秒後の行動が予測できるらしい。
俺も10年ぶりにあった知り合いから全然変わってないって言われたわ。
不意に時計に目を向けたとき、秒針が1秒より長く止まっている気がするってやつの仲間かな
あれも視覚情報を脳が勝手に補正した結果だとかなんとか
>>33
成程
あれはどう考えてもいつも1秒より長いと感じてた
知覚できる物しか感じられない凡人の脳では理解はしても納得はできないけど
>映像を見終わった参加者に女性の年齢を質問してみたところ、ほぼ一貫してその時点から15秒までに見た顔の印象に基づいた回答が返ってきた
それって視覚処理うんぬんでなく、「初めて出会った小学校高学年の子はもうしっかりして見えるけど、赤ちゃんの頃から知ってる中学生は いつまでも幼児のイメージ」みたいな、親戚のおじさん現象じゃないの? 記憶の中の顔形が更新されていくまでには、5年や10年 平気で遅れる。最初に形成された第一印象を塗り替えるのには時間が掛かるという、先入観の認知の問題。
「前もって下見とか予行演習やっとかないと脳は対応できない」
でOKなん?
正直この記事のタイトルと内容では誤解を招くと思う
原文読んでくると全然違う
15秒ラグがあるとかそういう話ではなく、視覚情報の認識が過去の情報に引っ張られるという話
TVのバラエティー番組でモーフィング使った間違い探しってわかりづらいな、と思ってたけど、こーいう原理からかねえ
ピッチャーが投げたボールを本人含め周囲が認識するのは最大で15秒後の事なのか…
思った以上に滞空時間長いんだな
スポーツとかで考えるとおかしなことになるけど、これは第一印象がなぜ大事かの説明だと思う。最初に嫌な感じの人だと思われたらその後何しても挽回できないのと同じで、最初のイメージで処理してしまってその情報を更新するのは脳が省エネしてサボってるから。
百聞は一見に如かず、一見は真実に非ず。
処理に15秒もかかったら車なんか運転できんな
認知する と、意識に残る
のを取り違えてないか?
意識に残る=記憶
見た物を記憶しなくとも、道路標識などは過去の記憶に基づいて判断する事=認知は出来るじゃない?
だから運転などは、過去記憶+反射で認知して回避は可能でしょ。
記憶の問題をこの論文では書いてるだけだろ。
まあ、いわゆるアハ体験(を支える原理)だよな。
この脳みそ、1500グラム弱の肉塊ていどでは、明らかに情報処理能力には限界がある。エネルギーだって無制限に使えるわけじゃないし。
その物理的にショボい情報処理装置で、生存のためにいかに効率よく情報を処理するか、って40億年かけて試行錯誤して、いまの、最新バージョンがこの1500グラム。
視界内の全要素の全情報、ほんの僅かの違いさえを常に確認し認識し続けるのは、明らかにエネルギーの無駄。今の今まで見てた役者が、急に別人になるなんて普通はありえない。
そんな細かいことを常に気にする奴は早死にするに決まってるし、実際そうだったんだろうね。
現世に生きている人間の脳は、本当に重要なところだけにパワーを投入し、やらなくていいことは執拗かつ徹底的にやらずに済ませる、有能な怠け者。
そんなヒトの生存アプローチの中で、15秒程度が、全体情報をざっくり更新する、ちょうどいいくらいの時間なんだろうな。
それ以上長いと事故で死ぬし、それ以上短いと飢えて死ぬ。
まあ、個人差はものすごく大きいだろう雰囲気はあるけど。
>>54
情報の取捨選択、平たくいえばテキトー化出来るのが機械処理やAIと比べた時の生物の強みだよね
しかも学習によって意識下ではなく意識外の処理になる
今は生物と機械のハイブリットが産み出されつつあるので両方の強みを持ったモノに進化できるかも
スタントマンに変わったと気付かないのは普通にカット入ってるからじゃないのか?
それともこれの効果で不自然なカットにも気付かないってこと?
スタントマンの入れ替えに気づかないのはある意味当然。
映画視聴者の目的は「作品に没入したい」のであって「間違い探し」ではないw
つまり人間の「意識の有り様」によって見た対象の処理速度が変化する。
スポーツマン、(カー・競馬・競輪・バイク・・)各種レーサーなどは瞬時に視覚情報を処理して肉体制御しなければお話にならない。
一方、映画とかの興味はストーリー展開だったり画像の美しさ新鮮さに心を奪われているわけで、見飽きるぐらいリピートしていない限りディティールの細かな違いに関心が移らないだろう。
映画では視聴者はむしろ「あえて15秒前の情報を残す=騙されたがっている」のだw
要はケースバイケースってこと
自分の感じている「今」という感覚が、実際の今とはずれているという事には前から自分も気付いてはいたよ。
でも人間は投げたボールをキャッチしたりバットで打ったり出来る。どうやって整合性を取っているのか不思議だ。
「自分は何を見たのか」の判断を過去15秒程度の平均から割り出してるって話か
この記事の論理だと野球という運動は存在できないんだけどな
この映像に続きがあって、ゆっくり元の顔に戻っていったらどうなんだろう
逆にもっと短いものとか、比較対象がほしい
最初の動画は、視野が違うように思う。
180度以上もの視野と、あの狭い視野は、ただ比べられないと思う。
狭い視野の場合は、前後のコマでまるで違う映像にもなるが、
広い視野と処理速度があれば、前後のコマが全く違うとまではいかなくなる。
その差は、大きいように思う。
二つの顔の動画について、
そもそも2つの顔が並んだ状態で見ても、
あんまり違いがないように感じた。
顔の周囲を消しているのも影響していると思う。
15秒間の景色の変化を「平均化」して処理すると記事に書いてあったと思うけど
つまり経時15秒のうちに視野の中で重大な変化があればそれも当然ズギャンと視覚認識はされるけど、急なら当然描画はブレたりして処理は適当 でも認識はしてる、てことだろか
それにしても論文のスタントマンの例は適当なのかな 映画ってそもそも視覚的な工夫をこらして撮るだろうし