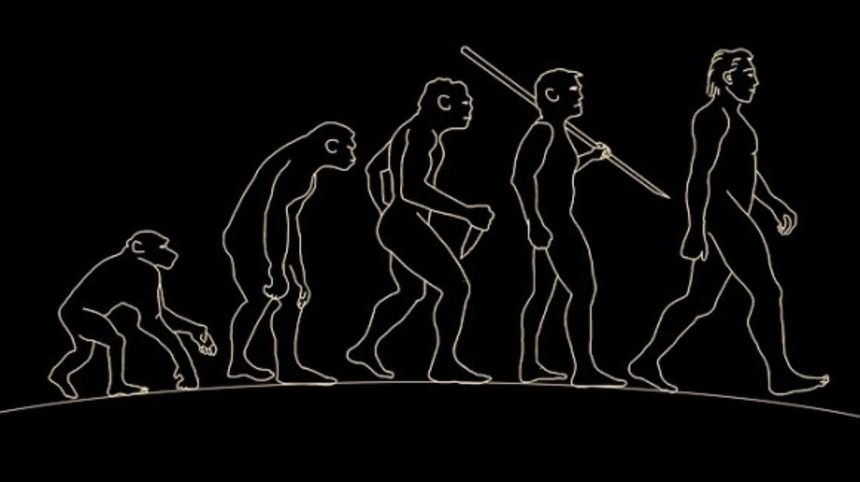 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見るアフリカを闊歩していたヒト族の仲間は、ずいぶんと多彩な生活を送っていたのかもしれない。
南アフリカで発掘された2種のヒト族の骨を調べたところ、2本足で歩いて生活していた種がいた一方で、相変わらず木の上で暮らす種もいたらしいことが判明したそうだ。
進化による変化とライフスタイルによる変化
過去数百万年のほとんどの間、私たちの祖先は他のヒト族の仲間と共存してきた。彼らの多くはある部分ではよく似ていただろうが、もちろん大きな違いもあった。
どのヒト族の化石にも、ヒトとしての特徴とどちらかというと類人猿的な特徴の両方が見受けられる。これらは環境とライフスタイルによって形作られたものだ。
中には、どの種が私たちの直接の祖先で、どの種が親戚なのか完全にはっきりとしていないケースもある。こうした複雑さのおかげで、ヒト族が木からぶら下がるのをやめて歩き始めた正確な時期の特定は簡単ではない。
それを突き止めるヒントは、さまざまな骨の大きさと形を知ることで得られる。たとえば、大腿骨の形状は、何世代にもわたって二足歩行に一番有利な特徴を選び続けてきた進化の産物だ。
一方、一生のうちに送られたライフスタイルの産物もある。それは日々加わる負荷によって変化した骨の密度だ。高い負荷がかけられた部分ほど骨密度が高い。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る200万年以上前のヒト族の大腿骨
ケント大学(イギリス)の古人類学者グループは、初期ヒト族2種の大腿骨の密度をCTスキャンで調べてみた。
特に注目されたのは、骨盤に収まって股関節を形成する「大腿骨頭」の部分だ。ここは体重の大部分をそこから下の骨に分散させるところで、ここの骨密度が分かれば、その個体が歩いていたのか、それとも木登りをしていたのかを推測することができる。
大腿骨の1本は、およそ218万年前に生きていた、おそらくは「パラントロプス・ロブストス」か初期の「ホモ属(ヒト属)」の仲間のものだ(どちらかかははっきりしない)。もう1本は、280万~200万年前の「アウストラロピテクス・アフリカヌス」のもの。
両者が生きていた時代には数十万年の隔たりがあるが、生きていた場所は同じ、スタークフォンテイン洞窟(現在の南アフリカ)だ。
形状を見る限りは、どちらも足で立って生活していたように思われる。どちらも私たちの骨によく似ており、大きな大腿骨頭と長い頸部、平たい顆部(膝関節を形成)を特徴としている。これはおそらく、ほとんどの時間を歩いて暮らしやすいよう進化したものだ。
だからといって、彼らが日々歩いていたとは限らない。たとえば、私たち自身もほとんどの時間を歩くよう進化してきたが、実際に四六時中歩いている人は少ないだろう。むしろ、歩く時間よりも座っている時間の方が長いに違いない。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る一方は現代人に、他方は類人猿に近い
研究グループが立てた予想は、A. アフリカヌスの骨の内部構造は、現代人よりも現代の類人猿に近いというものだった。ところが意外にも、その280万~200万年前の大腿骨の密度は、現代人のそれと同じだった。
逆に、正体がはっきりしない218万年前のヒト族については、骨の形状が示すように、ほとんどの時間を歩いていただろうと予測された。ところがその内部は、はるかに類人猿に近かったのだ。
二本足で歩いた骨と木登りをした骨
かなり最近まで、現生人類は幅広な股関節でもって、ほとんどの時間を立つか、歩くかして過ごしてきた。
このため股関節には後ろから圧力が加わり、その結果として人間の大腿骨頭で一番密度が高いのは後ろ側となっている。中ほどから頸部にかけて、密度の高い柱で補強するような感じになっているのだ。
他のほとんどの類人猿の場合、木の上で生活するために股関節が曲がっており、体重はさまざまな方向で支えられる。その結果、大腿骨頭で一番密度が高いところには、柱のペアが形成される。
1本は木登りで股関節が曲がったときに一番負荷がかかる部分、もう1本は歩くときに股関節がほんの少しだけ曲がることで負荷がかかる部分だ。
こうした密度の高い部分は、移動方法や生活環境に応じて、類人猿でも若干の違いがあり、ここから種を特定することまで可能だ。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る同じように進化した骨を持ちながら、ライフスタイルは大きく異なる
南アフリカの大腿骨は、どちらもほぼ同じ形で、私たちの骨とよく似ている。しかし進化よりも生活習慣によって形成される内部構造について言えば、218万年前に生きた種がはっきりしないヒト族の大腿骨は、現代人よりも類人猿に近い。
この種について確かなことが分からず、それが系統樹のどこに位置するのかも定かではないため、これが意味するところをはっきりと述べるのは難しい。
だが、ヒト族の中から二本足で生活する者が登場してから数十万年が経過してもなお、同じ場で多少なりとも木登りをしながら過ごしていた者がいたことも間違いない。
この2つの種は、明らかに似たような生活を送れるよう進化しているのだが、実際にはまったく違うライフスタイルを選んでいた。私たちの初期の親類らは、肉体的にも行動的にも、これまで考えられていた以上にずっと多様なグループであるということらしい。
この研究は『PNAS』(3月30日付)に掲載された。
References:Long after some hominins were bipedal, others stuck to the trees | Ars Technica/ written by hiroching / edited by parumo
















何にしても、全て屠った結果が我々である。
※1
そうとは限らないぞ。
・俺らは何もしてないけど、他の人類は
環境変動などで勝手に絶滅していった。
ていうか、何なら
ギリセーフだっただけで、今の人類も危なかった。
・特に武力衝突があったわけではないが
適者生存で今の人類のほうが勢力範囲を広げていき、
最後 少数になった他の人類は、交雑で吸収され跡絶えた。
いろいろな考え方があるし。
猿回しの猿も幼少期からの二足歩行習慣の結果骨格が変形して人間みたいな背骨になる。現代人でも生活習慣の違いから骨格に変化が生じたら遠い未来に化石が発掘されたとき別種と判断されるかもしれない。
うちの親父がこのタイプだわ
とはいえ現代人と大差ない骨格なのに樹上生活してた方は不便だったろうな
発達した脚は逆に邪魔だったろう
慥かに足短めな黄色人種は木の上生活少し長かったのかも知れないな
環境的に平原が多いか森が多いかが分れ目なんじゃないか?
※5
それならほぼ森と山と東欧の沼地以外の地形がないヨーロッパ人のほうが足が短くなるんじゃ
陸上生活のほうが建設が簡単で食料資材を大量に溜め込めるって利点があるけど、陸上生活者が出た後に樹上生活を続けた原動力は何だったんだろう
※6
200万年前とか、そのレベルの昔だろ?
建設だの食糧備蓄だの、そんな段階じゃ全然なくね?
・樹上のほうが猛獣の襲撃を避けやすい
(猿人時代の人類は、被捕食者の立場)
・森林は果実など食べ物が豊富
・日蔭や柔らかい葉など快適な寝床
気候変動で森林が減って仕方なく地上へ降りることが増えたのが二足歩行の始まりと云われたりするし、二足歩行に適応可能になった後も、まだ豊富な森林にアクセス可能な“勝ち組”なら、樹上で採集する生活を選んでも不思議ではないんでは?
そりゃ現生人類だって日常的に木に登っている人もいるくらいだしね
大後頭孔の位置でわかるよ
二足歩行、脳肥大、道具の使用、どれが先だろうな
適者生存というのがそれほど単純じゃないという例ですね。多分、二足歩行ができる樹上生活者は、当時の勝ち組だったと思う。猿人同士で群れ同士が抗争する場合、チンパンジーのように地上で戦うと想定すれば、移動力がある大腿骨が強い方が勝つだろう。勝ったら、祖先から住み慣れた樹上を独占したかも知れない。追い出された方は、仕方なく地上で暮し人類の祖先になった、という考え方も出来るね