
Lindrik/iStock
�������ΤΥ�����������ʥ�ѡ��̥��ˤˤϡ����̤��Ϥ�����¤Ħ�郎�����̤���������¤�Ǥ��롣�����ϥ⥢���ȸƤФ�Ƥ��ꡢ��¤������֤��줿��Τ�ޤ�����900�Τ⤢�롣����ɴǯ��δ֡�������ʤĤ�³���Ƥ����⥢�����ϡ��������ä��ݥ�ͥ����Ҳ�ν�����������ޤᡢĹ���֡�����Ԥ����δؿ���椭�Ĥ��Ƥ�����
������ۤ����̤Υ⥢�����Ϥ��ä������Τ���˺��줿�Τ���������ħ���Ƥ����Τϲ������͡����⤬�����⡢������ϴ����˲�������Ƥ��ʤ���
������������ο����ʤ�ȯ���ϡ��⥢�����˴ؤ���������礭���Ѥ��뤳�Ȥˤʤ뤫�⤷��ʤ�����
�⥢�����κ��о���ھ���ʬ��
���⥢������90��ʾ�ϡ���Ρ���饯�Ȥˤ�����о�Ǻ��줿�������������Τ�1��ˤ������ʤ��ų���ǤǤ����л���ʮ�и�����������ʥ⥢�������뤿������̤��ФϤ��٤Ƥ�������ΤߺΤ��Ƥ��롣���������ھ���ʬ�Ϥ����ƥͥ�������������ؤ��ϼ��ųؼԡ����顦���㡼���åɤϡ���Ρ���饯�ˤ���Τϡ��Ф����Ǥʤ��ȸ�����
�������ڤϡ��ճ��ˤ⥫�륷��������ʤ�˭�٤Ǥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ������Ĥޤꡢ�������ھ��ˤϡ���ʪ����Ĺ�䤽�μ����̤���뤿��ˡ�������ʬŪ�˽��פ����Ǥ������äƤ��뤳�ȤȤ������ȤʤΤǤ�

abriendomundo/iStock
�⥢�����κ��о줽�Τ�Τ������ʾ����ä�
������ޤǤϡ����κ��о���Ӥϡ��⥢��������������Ǥ��ꡢ�������Τ����餳����˱��֤���ΰ��Ū���֤�����ä��Ȥ����Τ�������ä����������������κ��о�˻Ĥ��줿400�ζᤤ�⥢�����Τ����Ĥ����ڤ�����졢�֤Τ褦�ʤ��ä��ꤷ����ι�¤ʪ�ǻ٤����Ƥ��롣
�������Υ⥢�����Ϥ�Ȥ�Ȥ��������֤���Ƥ�����ΤʤΤ������о켫�Τ���̱�ˤȤäƿ����ʾ��Ǥ��ä��Ȥ������Ȥ��Ƥ���Ȥ�����
��Τۤ��ξ����ڤϡ���®�����������ष�ơ���ʪ��ɬ�פʱ����Ǥ��ʤ��ʤäƤ��ޤäƤ��ޤ�����
�Ǥ⡢���κ��о�Ǥϡ����к�Ȥβ����ǽФ���ξ����ʤ����餬���������ि�ᡢ��ʬ�伫���������������Ǥ��ե����ɥХå�����륷���ƥब�Ǥ������äƤ���ΤǤ�

Easter Island Statue Project
˭�����ھ�����ĺ��о�����Ȥ�����
���ھ���˭�����⤵�뤳�Ȥʤ��顢�μ襵��ץ����˥Хʥʡ��������⡢���ĥޥ��⡢�����Υ��ʤɤθ���κ�ʪ�κ��פ����Ĥ��ä����������ξڵ�Ϥ��٤ơ���Ρ���饯�κ��о줬�⥢���������Ϥ��ä������Ǥʤ��������Υ�ѡ��̥��Ҳ�ɬ�פʿ�ʪ���Ƥ뤿��ˤ�����˭�����ھ�����Ѥ��������ʤ�ϫƯ�Ϥ��������ι⤤�̺��Ϥ��ä����Ȥ��Ƥ��롣
���������ǡ����䡢��Ρ���饯�ε����������Фΰ��縶���ϤǤ��뤳�Ȥ�ͤ���ȡ������ʿ��⤬�ФƤ��ޤ���
�������ھ�������ʪ���Τ������ʤ��ƤϤʤ�ʤ����Ť�ɬ���ʤǡ��������θ����ɬ�פȤ������Ϥ�˭���ˤ��뤿��ˡ���Ρ���饯���餬�ڤ����Ф�Ƥ�����ǽ��������Ȥ������ȤǤ�
�⥢�����Ϻ��о��äƤ���
������Ǥϡ��ʤ����⥢������줿���Ǥ���֤η�˷��Ƥ�줿�Τ����������⥢�����ϡ������Ū��Ω�Ƥ�졢˭���ε����ȴط����Ƥ��Ƥ���Ȥ����⤬���뤬������θ���Ԥ����θ���Ĵ�������ʳؤ˴�Ť����ڵ�����Ƥ���Ȥ�����
���֤Τ褦�ʷ꤬�����Ƥ����Τϸ����ޤǤ�ʤ����⥢������������˭���ʳڱ��뤿��˷��Ƥ�줿��ǽ�����⤤���Ȥ��Ƥ��롣

abriendomundo/iStock
���ֺ���θ����̤ϡ���Ρ���饯�ˤ����������٤ơ����ڤ�줫�鱿�ӽФ����Τ��ԤäƤ����Ȥ�������Ū���Ѥ��ޤ���UCLA�ιųؼԥ��硼������͡��ե��ƥ���֥�դϸ�����
��Ρ���饯���֤���Ƥ���⥢�����ϡ����о줽�Τ�Το�����������μ¤ʤ�Τˤ��뤿��ˡ������ˤ��Τޤ��֤��줿�ΤǤ��礦�������θ�����ʸ�ϡ���Journal of Archaeological Science�٤�ȯɽ���줿��
�⥢����˭���Ȥ����ͤ����濴�ˤʤ��Τǡ���ѡ��̥��Ǥϡ��⥢���������ˤ��������ʪ�������ˤ����ƶ�������ȿ������Ƥ����ΤǤ�
References:foxnews / sciencealert.�ʤ�/ written by konohazuku / edited by parumo
�ɵ�����2020/1/20����ʸ������������ƺ������ޤ���
���碌���ɤߤ���
 ���Ū�ߥ��ƥ�����ȡ���إ���⥢�����ޤǡ���˳ؼԤ�̤���˲�������ʤ�5�Ĥθ����ʪ
���Ū�ߥ��ƥ�����ȡ���إ���⥢�����ޤǡ���˳ؼԤ�̤���˲�������ʤ�5�Ĥθ����ʪ �⥢������Ƭ�����ǤϤʤ����ϲ�������줿�ܥǥ�����̩
�⥢������Ƭ�����ǤϤʤ����ϲ�������줿�ܥǥ�����̩ ����������ӥ�����ᤤ���Фη�¤ʪ��¿��ȯ�������
����������ӥ�����ᤤ���Фη�¤ʪ��¿��ȯ������� �л����ä���˺��夲�����ס��ڥ롼�ε����¤ʪ�֥��롦�ܥ륫��פ���
�л����ä���˺��夲�����ס��ڥ롼�ε����¤ʪ�֥��롦�ܥ륫��פ��� ��������ԥ�ߥåɤȸ�®�٤ο��ͤ��������פ������ȡ������奨���ץȤ�����Ի�
��������ԥ�ߥåɤȸ�®�٤ο��ͤ��������פ������ȡ������奨���ץȤ�����Ի�







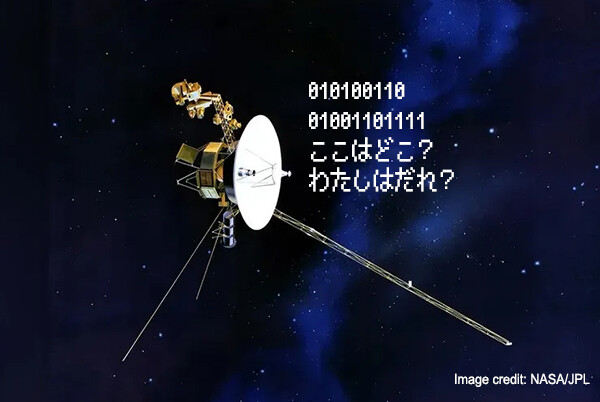
 6175
6175 313
313 11
11 37
37



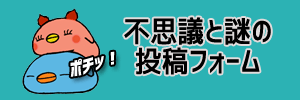





























































������
1.
2.
3. ƿ̾������
��ɤνꡢ���Υ⥢���η��ˤʤä��Τ����Ϥޤ�ϰ��β��Ǥ��ä��Τ��������ʤ����
ʸ��Ū��ͳ�����������������Τ�������
4. ƿ̾������
̵�������Ȥ�����ȯ����⥢���ο���˵������ƥݥ�ͥ��������ȳ�̿�������Ȥʤ��⥢���ȶ�����ˤαƤ�����Ƥ��ä������
5. ƿ̾������
�褯�狼��ʤ���
�֥⥢���������⤤���פȤ��������顢Ω�̤ǰ�ư�������¸���������������
�ֳ��Τۤ��������Ω�ġ���ͳ�������餯��ĥ��Ǥ��ä�����
���뤤�����ΤȤϰ㤦�Ф�˹�Ҥ��ܤ�����Ƥ�����Ū
�����ˤĤ��������ʤ�����ʤ�����
6. ƿ̾������
�⥢���ä��ˤʤΡ����ʤΡ�
7. ƿ̾������
���о���Ф�衼��Ĵ�٤Ƥ����500�����ߤ�������פäƤ����������ΰ�ԤνĤ�����ʸ�����äȤ���衣
8. ƿ̾������
���Ȥ˴ؤ��ͭ��Τ�
���㤢����ưʪ���Ф���ƻ���Ū�ʰ�̣�礤�Ȥ��Ĥʤ���
ή�Ф˿ͤˤϸ������ʣ�
9. ƿ̾������
�ʤ����ɤ����ơ��⥢��������WHY��
10.
11. ƿ̾������
�ޥꥪ�Ȥ��ѥ��ǥ������Ȥ�
���⤷�Ƥ���⥢����
�ΤϷ빽�������ɺǶ�Υ⥢����
���⤷�Ƥ��ʤ��ʡ�
12. ƿ̾������
��3
�⤦���ۤܲ������Ƥ��
������������˽���Ǥ���ã������ϡ����������Υ��桼��Υ���²���äƻ���ʬ���äƤ롣���ΰ��������ҥ����̤��Ϥäƥ�����������ˤ��ɤ��夯��DNAĴ����Ƚ�������Τ衣DNAĴ���ä������͡�
����Υ��ҥ��ˤϥƥ����Ȥ�����¤�����äơ��⥢�����ν���η��Υȥ����ȥ���θ��ˤʤä����ƥ������Τ������¤�����¤�ǡ��ȥ����ȥ���ˤ������롣�⥢����13�������Τ�����¤����Ϥޤäơ�14�����ˤϴ�Ⱦ�Ⱦ�Ȥ����ˤʤäơ����θ���粽���Ƥ�����
�ޤ������Ƽ������Ǥ���
����¾�ξ����ܤ���Ĵ�٤Ʋ��⤷�Ƥ�Τǡ�����̣������С�Ķ�︽�ݤ���פȤ��������ȤΥ�����������Υ⥢�����ι����ɤ�
13. ƿ̾������
�ط��ʤ����ɡ�����쥬����ห��Ȥ����פ��Ф���
14. ƿ̾������
�⥢���α��¤Τ���δ������ǿ��Ӥ��ʤ��ʤäƼ����˲����ʤ���ʤ����⤢�ä����ɵդäƤ��Ȥ�FA��
15. ƿ̾������
��12
����Ⲿ��ΰ�Ĥǡ��ۤܲ����ϸ�����ʤ�ʤ�����
Ƚ�������Τϡ��������������ʿ�ηϤ�̱²���������Ƥ����餷���äƻ���������Ρ�
�������ǽ�������ԤǤ��ä������ˤϤʤ�ʤ��������Ƥ������ϰ�ˤ������������������������β�����ǽ��ʸ����ͳ��ˤĤ��Ƥ���ڤ���Ƥ��ʤ����顣
16. ƿ̾������
�⥢���Ȥ����ȡ��Х�������⡼������
�ӥǥ����ʤκǽ�˽Ф����⥢���������פ��Ф����
�Ի��繥���äƵ������ϡ��������äƻ���������Τ�
17. ƿ̾������
��12�ؤ���
����������ȥ���ʤΤ������
�������ʤΤϥ����Ȥ����ǡ����⤷�������Ȥδ����Ԥ���Ϻ٤��������������ä�Ĵ�٤Ʋ��⤵��Ƥ뤭����Ȥ��줿���Ǥ���
18. ƿ̾������
�桼�⥢���ݤʤ�ʤ����ȡ�
19. ƿ̾������
¿���Υ⥢�����ϡ������äƤ���ư��������ʤ���
�Ф�ư���������֤��Ƥ��������ä���ʤ�����
20. ƿ̾������
��12
�����ɤɤ�������ͳ�Ǻ��졢���οͷ��ʤΤ��������ˤϤʤäƤʤ��ġ�
21. ƿ̾������
��6
�������Ȼפ���
���Ȥμ̿�������ΤĤ��⤽������
����ˤ褯����ȸԴ֤ΤȤ����ˡɲ����ɤ��夤�Ƥ��Τ⤢��
�������ܤ�ô�äƤ�Ȥ����Τʤ���������������ʤ�������Ȼפ�
22. ƿ̾������
���ʤ궽̣����������Ȼפä���
��¿���θ�����𤫤顢�⥢���η��ߤ����ʤ��Ĺ�����Ϥä����ȤϤְܴۤ㤤�ʤ������������������Ū���äƤ����¤�����֤��줿�⥢���⤢���������
����β���ϡ����κǽ������Ū�䵡ǽ�ο仡�Ȥ��ơ��礤�˹;ڤ�;�Ϥ����ꤽ������
23. ƿ̾������
��19
�������ʤ������ƤǤϤʤ��Τ����Τ��
���ڤ�����ˡ������������֤�Ⱦ�������֤ޤǺ���ơ�
���ߤ˻��ޤ����֤���³���Ƥ���⥢������ͭ��Τ�����
�������¤�Ǥϡ��Ĵ��������Ƥ������֤�����˱������
�ʤΤ����ɤ͡����㳰��ͭ��Τ����Τ��
24. ƿ̾������
��7
�ޥ�����ץ쥹���������ʣ�
25. ƿ̾������
�ʤ�Ȥ����������ɤ��ܤ��Ȥ������餻�٤ä����Ϥǰ餤������Ƥ��ä��äƽƤ����餽���פäƤ����ɤ�äѤ��������ɤޤʤ��Ȥ������
26. ƿ̾������
�⥢���α������ϼ¾ڼ¸����Ԥ��Ƥ��뤾
������դ��Ƹ�ߤˤ��餷�Ƥޤ���⤫����褦�ˤ��Ʊ���
27. ƿ̾������
>>6
�ܺ긩������Ԥˤ���⥢����Ѥ˹Ԥä��������뤬���Դ֤ΤȤ����˥��줬���ä��������äƤޤ�����
28. ƿ̾������
�����ʾ��ͤ��ĥ�����������Τ��Ȥ褯�狼��ɤޤ����ε���ʥ⥢�����ޤ��äƤ��ΤϤ������Ȼפ���
�ݥ�ͥ����ǻפ��Ф������ɥ⥢�ʤ�����γ�����������ǡ�
29. ƿ̾������
��22
�ǽ��?
�⥢����äƤߤ������⥢�����Ⱥ�ʪ���褯��ġ����褷�⥢�����³���褦��
�ष��������㡩
���ܤǤ��뤬�Ĥ���Ƥ��褯��Ĥ��Ȥ��ΤäƤ����ΤǤ��θ����ʤȸƤ�Ǥ�����������
�ɤ��ι�Ǥ��ʪ����Ĥ��Ȥˤ��Ҵ��ʤ褦�ǡ�
30. ƿ̾������
�Ƥä���⥢����̵��������˭�٤˴ޤޤ�Ƥ����Ȥ������Ȥ�����Ω�Ƥ뤳�Ȥ���������Ϥ˳Ȼ���������ô�äƤ����Ȥ������Ȥ��Ȼפä���ä��衣
�⥢�����ȤϤ������Ф�����äѤꡣ
31. ƿ̾������
���ܤˤ���ФȤ����⥢����Ʊ���Ȼפ�������������Τ��ä��ä���
32. ƿ̾������
��26
������ͭ̾�ʼ¸������ɡ�
��������������Τ˼ºݤˤɤ���äƵ錄���������ʤ�����
�����إ⥢�����ϼ����⤤���٤Ȥ�����������˻ĤäƤ��ơ�
����ˤ��ƹͤ���줿���ڼ¸����ä�����
33. ƿ̾������
����ޤǤϡ��⥢�����ϡ��¤������Ѥ�����(̵������)���ä��Ȥ������������ʤ��ȴ��Ԥ��Ƥ�������ɡ��ʤ�����Ǹ�ϡ������Ƿ���뤱����ä���
34. ƿ̾������
(º﹃º )����Ū�ʴ�����Ȫ���������˭��ꤹ��٤Υ�Ρ�
�Ȥ��������Ƥ����ɷ�ɲ������������Τ����褯�狼���
���ڵ��Ǥ�˭����ä���̿���ͥ륮���ξ�ħ�Ȥ����ưʪ�η��Ȫ�˻���
���������ä��������ä��ɤ�����Ȥ����äƤ�����ʤ餢��������ʡ��Ȼפä���
����äƤ��äƤ����Τä���θ���������Ѥ�äƤʤ��㡦������
35. ƿ̾������
�⥢�����⤤����
�ݤ줿�⥢�������ھ줫�鳤�դ�ž�����
������������
���줬����ʸ�������ΤϤ��ޤ�Ǥ���ġ�
36. ƿ̾������
��20
�ƥ�����Ʊ���ʤ�ʤ��Ρ�
�פ���ˡ�¼�μ���Ū��ʪ�Ǥ��ꡢƱ���˶�Ʊ�Τ���«��Ǥ��٤Υ���ܥ롣
�ͷ��ʤΤϿ��ͤ��Ϥä����顣
37. ƿ̾������
>>35
����ʸ���θƾΤθ촶��ä��㹥����
38.