
����ȯ�����줿���ΥǥХ����ϡ�Ķ�ƿ����Υե��륿���ڡ��ѡ��ȸ���ۼ����륫���ܥ�ʥΥ��塼�֤��ؤ��Ȥ߹�碌�������ʥǥ��������Ѥ��Ƥ��롣
��������ư������ˤ�����������Ф褯������Ǥ��Ƴ��夫��ۤ�100�ѡ�����Ȥα������뤳�Ȥ��Ǥ���ä��ν����Ϥ���������
�������ܤ��ǡ��������Υ��äݤ���������夬�ä���Ϥ�������̣�������ळ�Ȥ��Ǥ���Τ���
Supplementary Video 6
�������Τʤ���ξ�α
���츫�ϥ��ƥ��β��Τ褦�ʥǥХ����ˤ�פ��뤬�����λ��Ȥߤ��Τ��餢���Ρ�Ǯ�ǿ���ȯ�����������ƺƤӿ���᤹���Ȥǡ��Ϥ��Ƥ����Խ�ʪ��������Τ������פϾ�α�Ǥ��롣�����ǥХ����Ǥϡ����ۤΥ��ͥ륮���ǿ���ȯ�����롣���Τ����������Ǯ�˸�Ψ�褯ž���������������Ǯž���Ǻ�פ��Ȥ��Ƥ��롣
����������ʬ���ȯ���������������Ǯž���Ǻब���η뾽�Ǥ������Ƥ��ޤ��С����ͥ륮����Ǯ��ž���Ǥ��ʤ��ʤäƤ��ޤ���
�������ǡ��夬��ȯ������ȱ����뾽�������������ޤ��뾽�������������Ϥ������褦�߷פ˹��פ餷��������ˤ�ä�600���֤�Ķ����Ϣ³���Ѥ���ǽ�ˤʤä���
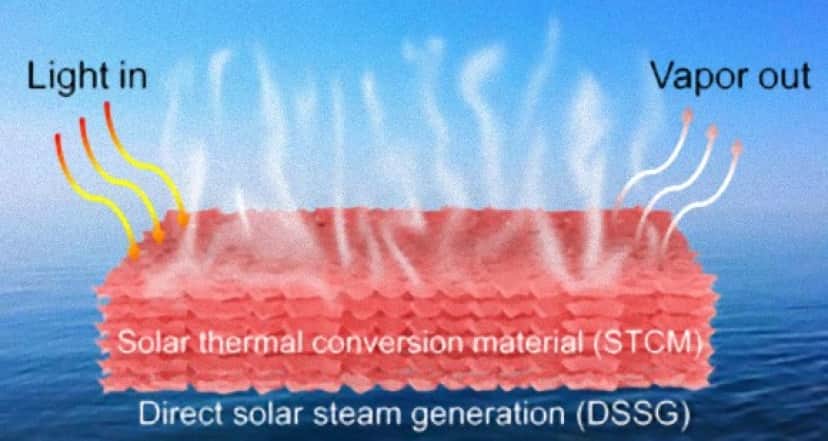
Monash University
�¤�����ΨŪ�ǡ��ѱդ�ʤ�
���������ȥ�ꥢ����ʥ�����ؤβ��إ��˥��������������ˤ��С��¤����ŵ��⤤�餺����ΨŪ�ǡ��������ѱդ����Ф����Ȥʤ��˳��夫��������Ǥ���Ȥ����Τ������礷����Τ������������ο͡�������ǰ����ʿ���Ϥ��롢���ͥ륮����ưŪ����ˡ��ȯ���븦���������ˤʤ�Ф����Ȼפ��ޤ����Ѵ�ʪ�δĶ�����ѥ��Ȥ��Ѵ�ʪ�������������ˡ�ˤ���������뤳�ȤǤ��礦����
���¸��Ǥϡ����ΥǥХ����������ۼ���Ψ�ϡ��ɤΥ��ڥ��ȥ�Ǥ��äƤ�94�ѡ�����Ȱʾ��ã����Ȥ�����̤������Ƥ��롣���Τ���ˡ������ξ��֤ˤ�����餺ͭ���˵�ǽ���Ƥ����Ϥ�����
���ޤ��������Ǥϡ�1ʿ����ȥ�ο��̤��Ф��ƻȤ��С�1��������6��8��åȥ�ο������Ф����Ȥ��Ǥ��롣�������ˤĤ��Ƥϡ��ޤ��ޤ�������;�Ϥ�����餷����

Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay
���Ťʿ�������ο͡���
�夬˭�٤����ܤˤ���Ȥʤ��ʤ��´��Ǥ��ʤ����⤷��ʤ����������ʿ�γ��ݤ�21������������ľ�̤��Ƥ����礭�ʲ����������������ȸ������ϵ�Ǥ��뤬������97.5�ѡ�����Ȥϳ���ǡ�ø���2.5�ѡ�����Ȥ����ʤ���������ø��ΤۤȤ�ɤ���ˤ��̶ˤ�ɹ���뤤���ϲ���Ȥ���¸�ߤ��롣
�����Τ���ˡ����������ѤǤ��������ΤΤ鷺��0.01�ѡ�����Ȥ���¸�ߤ�����������������ä䲹�Ȳ��Τ���ˡ�����������Ϥ���˵��Ťʤ�ΤȤʤäƤ��롣
���Ķ������Ĥ��뤳�Ȥʤ�����������Ѳ�ǽ�ʿ���Ѥ��뵻�Ѥ������Ƥ���ΤϤ��������櫓����
��Ĺ��³�����߱����Ǥ���Ȥ����ͤ⤿������������������ĤϤ����äߤ��Ȥ������ȤΤɤ�����α��Ƥ����Ȥ����������
�����θ���ϡ�Energy & Environmental Science�٤˷Ǻܤ��줿��
References:Water solutions without a grain of salt - Monash University/ written by hiroching / edited by parumo
���碌���ɤߤ���
 ���ε����鷺��120ǯ��ø���Ŭ���������ŪĶ�ʲ���뤲�����Ƹ����
���ε����鷺��120ǯ��ø���Ŭ���������ŪĶ�ʲ���뤲�����Ƹ���� ���������ǰ��߿��99.9�ѡ�����Ȼ��ݤ��Ƥ����Ķͭǽ�Ǻब�ͰƤ����
���������ǰ��߿��99.9�ѡ�����Ȼ��ݤ��Ƥ����Ķͭǽ�Ǻब�ͰƤ���� �٥륮���ξ��ؾ��Τ����Ф��Ƥ���Ǣ�����̤˰���롪���ե�å���ʰ����Ѥο�ƻ�夬���ή���ˤʤäƤ�����
�٥륮���ξ��ؾ��Τ����Ф��Ƥ���Ǣ�����̤˰���롪���ե�å���ʰ����Ѥο�ƻ�夬���ή���ˤʤäƤ����� ����������������Ф������ʽ�Ŷ�ܥȥ롢�ե�����ǯ��ˤ�����ͽ��ʥ������ȥꥢ��
����������������Ф������ʽ�Ŷ�ܥȥ롢�ե�����ǯ��ˤ�����ͽ��ʥ������ȥꥢ�� �����ҡ����ӡ��롢�����顣���ߤΰ㤤��̣�а����ҤǤϤʤ���������ʬ�˴�Ϣ��������Ҥ��������Ƹ����
�����ҡ����ӡ��롢�����顣���ߤΰ㤤��̣�а����ҤǤϤʤ���������ʬ�˴�Ϣ��������Ҥ��������Ƹ����


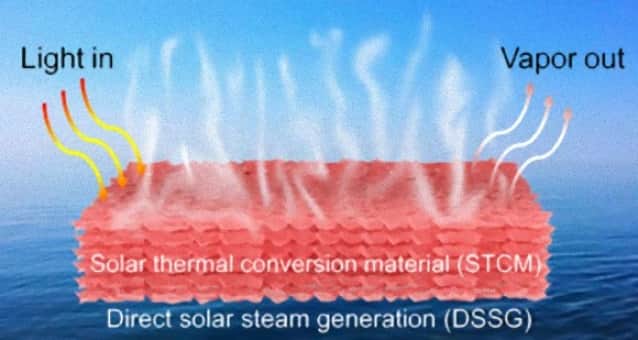


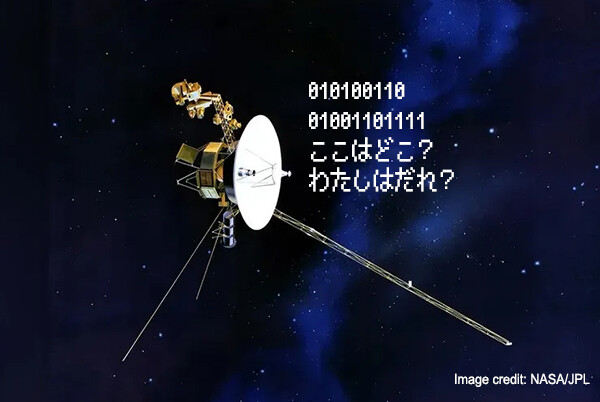
 6175
6175 309
309 10
10 37
37



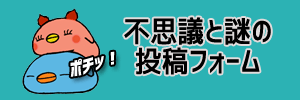





























































������
1.
2. ƿ̾������
����㤹������
����ʤ��Ƥ������������ѥ���������������줽��
���ܤϿ���¿������Ȥ�����Ͼ��ʤ�����������
3. ƿ̾������
����ǽ�������Ϥɤ����롩
4. ƿ̾������
������٤˻Ȥ��뤫���
5. ƿ̾������
��夬˭�٤����ܤˤ����
����Ĵ�٤��ʬ���뤳�ȤǤ��������ܤϷ褷�ƿ夬˭���ʻ�Ǥ�ͭ��ޤ���
���������˴�������Ȥष����ʤ��ΤǤ���
���Ǥ��뤳�ȡ����ڤ����ǰϤ��Ƥ��뤳�Ȥǿ夬˭�٤Ǥ���Ⱥ��Ф��Ƥ��ޤ������Ǥ����������ѿ�������ѿ�ʤɤλ��Ѥ�ޤ�ޤ��ȡ�����ɤ������ʤ��Τ����⤭Ħ��ȤʤäƤ��ޤ���
����Ū�ˤ����ܤϿ�˴ؤ��Ƥϰ¿��ʤɤȡ�̴�ˤ�פ�ʤ�������̿�Ǥ���
6. ƿ̾������
���ܤ�夬˭�٤Ȥ��������߱��̤ϤȤ⤫���Ϸ�Ū�ˤ��äȤ����֤˳���ή��Ƥ�������Ȥ����Ȥ�����̣�Ǥϼ¤Ϥ����Ǥ�ʤ������͡�
���ۿ���͢���̤������Ǥ�졢����褦�̤���
7. ƿ̾������
����������������
��ͭ�뵻�Ѥ�����ˤʤ�Τ�����������
�ʰ�Ū��ʪ�Ȥ��ƽ���ʬ���Ͻ��褽������
8. ƿ̾������
�����ɤ����¿���οͤ��Ȥä��鳤�ο夬�ϳ餷�Ƥ��ޤ��ΤǤϡ�
9.
10. ƿ̾������
Υ��������������Ӥγ��ߤʤɡ��Ȥ������¿������
11. ƿ̾������
�����ˡ����������ƽФ����Ϥɤ������������� �����ƺ�褵��³�������Ϥɤ��ʤ��������� ���ˤⳤ�ν���(��ʪ)�����������ɡ�
12. ƿ̾������
�������Ф��������䤷�ƿ���᤹���Ȥߤ��ɲä�ɬ�פ����
13. ƿ̾������
���֤����ʤ��¤���С����ɤ�觤�����
14. ƿ̾������
���������Ρ��Ѥ���
15. ƿ̾������
����äơ��դ˹ͤ���ȡ��������פ��ˤ�ƴ�ñ�ˤǤ���Ȥ����ä���
���������äơ����ʤ�������ȥ����Ȥ�����Ϥ������ɡ����Υ��Υ����ΥǥХ�����Ȥ��С��������������ʤ��˾���˳��夫��ֱ��פ��Ǥ��Ƥ��롣�ȡ�
16. ƿ̾������
�ष��������Τ��ŵ�������ʤ��ʤ�Ȥ��äƴ����ǻȤ��������ʡ��������������ѤȤη�礤�⤢�ꤽ��������
17. ƿ̾������
������뤫�������Ļ����
18. ƿ̾������
�����Ϥ�ŷ���ˤ�äƸ�Ψ������뤫�⤷��ʤ����ɡ������餷��ȯ�����Ȼפ���
19. ƿ̾������
ư�Ϥ�ɬ�פȤ������Ǻ�ι�¤���������Ѥ��Ƥ���꤬�����Ǥ��͡���ȯ������ʬ�⡢���餫����ˡ�ǤǤ���¤����Ǥ���С�����ʤ��Ψ�������ԤǤ�������
�����ϰ����ͽ�������֤Ǥ��롢�����������Τ褦��������ˡ����ڤ���Ȥ����Ǥ��͡�
20. ƿ̾������
>>8
����櫓̵���Ǥ���
�����������Фο������Ƥⳤ���3��ˤ�ڤФʤ��Τˡ�
���ȿ�Ȥä�����äƿ夬�ä���̵���ʤ�櫓����ʤ�����͡��Ϥ˴Ը�����Ƥޤ���Ȥʤ걫�Ȥʤ������
����Ѥˤ����ꡢ���ˤ��Τޤ��֤��Ʋ�������ʤ���
21. ƿ̾������
ư��Ǥϱ��夬�ɤ����鶡�뤵���Τ���������β����ˡ������
�ʤ�������
22. ƿ̾������
��11
��Ф��줿���ϡ����ߤ��ƿ�����Ѥ���Ф�������
���ϱ��ǵ��Ťʻʤ����
���äơ����������Ȥ��롩
������κ��?��۴Ĥä��ΤäƤ�?
���Ϥɤ�������¸�ߤ�³���ơ�����¸�ߤ�³����
ͷ�����ƤǤ���Ȥ���ʤ��¤�Ϥ�
����Ⱦ嵭���̤ꡢ�������Ѳ�ǽ�ʿ�����Τ�0.01%�Ǥ����ʤ�
�褷���10�ܤˤʤ����ȳ��Ϥɤ���ʤ�ʤ��������Τ�ͧã�ˤϲ��αƶ���̵�������
�狼�ä���
23. ƿ̾������
����ϥ����饨��ε��Ѥˤ�ɤŨ�����
�������ȥ�ꥢ��뤸���
24. ƿ̾������
�������������ʪ������˻Ȥ��ʤ��Τ���
25. ƿ̾������
��22
���ƤϤȤ⤫���ʤ�Ǥ�����Բ���ʸ�Ϥ��Τ�
���������Τ��ǽ�ʤ�
26. ƿ̾������
�߿ݤθ�Ψ���ɤ�ʬΥ��ˡ��ï����ȯ���Ƥ��줨
�ɤ�ʤ�����Ƥ�����Ĥ�����ũ��ũ�Ȥ��������㸺��ʤ���
���Ĥ������ȱ��Ĥ����ʤ��Τ���
27.
28. ƿ̾������
�������ˡ�Ǵ����ʾ�α��ϡ�̵���������ޤ�������Ǥ⡢����ʤ�ˤ���ˤ�Ω������������
29. ƿ̾������
�����Ѥ��Ȥϻפ�����ȯ������β���Ϥɤ���äƤ������
��ʬΥ�äƤ���������֤δ��ó�ȯ�äƴ�����
30. ƿ̾������
�������ζ���ȿ���β���Ϥɤ������äƤ�������
ư����������Ƥ�Τ��Ȼפä����ɤ��Τ���������䡹ͯ���Ƥ���Ȥ������Ǥ���Ƥ��������
31. ƿ̾������
ʸ�礷������ʤ����ܿͤΰ����꤬�ФƤޤ��͡�
32. ƿ̾������
��29
����������������ʬ����ֱ��η뾽�פ������鼡��ʨ���Ƥ��ơ����Ȥ��餢�Ȥ��龡����Ѥ�äƤ����ͤϡ�����ͤ�����������λ��פ�����˻��ޤ�Ƥ���褦�˸������������
�ʤΤǡ��ष�����ΥǥХ�����������ʬ��˥��Υ١����������Ȼפ���
33. ƿ̾������
��12����29
�褯ʬ�������ȯ������ΨŪ�ˤ����Ƥ��ޤ���
���Ȥϴ�¸�ξ�ί��Ʊ����ˡ�ʤΤǤϡ�
�褯�����줾��������Ǯ���������Ѥäƴ�����
��̵�����ɺ�夷�ƿ����������ˡ�פߤ����ʿ�
�����������γؽ��ɤ�ʪ��������Ƥ����ꤹ�뤱��
(���ͤ˷귡�ä��ƴ���֤����ӥˡ��륷���Ȥ֤���Ϥ�)��
�פϡ���ȯ����̩�Ĥ���ŷ��˷��Ф�
�䤨����ũ����ս�˽��ޤäƤ���褦�ˤ�����ɤ����ȡ�
34. ƿ̾������
���α��϶줽����
35. ƿ̾������
��25
�ͥ��ƥ��֤˥��饿��ʸ������οͤ��ⶵ�������ʤ뵤������ʬ�����
36. ƿ̾������
���ĤޤǤ⡡����Ȥ��⤦�ʡ��Ƥȶ⡡����������⡡�Ĥ�������ޤ���575 77��
37. ƿ̾������
��8
�ष�������ब���Х��лȤä��Ȳ��ꤷ�ơ��������夬�ä��Ȳ��ꤹ�롣
�Ǥϡ����夬�ä���ʬ�Ϥɤ��˹Ԥ��Τ���
��̡��̤ʾ��˳�������夬�äƤ�������͡�
38. ƿ̾������
����ǤǤ�����äƱ��ĤǺ��褦��ŷ�����äƤ��Ȥ�
�����ष�����ä������˲��ͤ����ꤽ��
39. ƿ̾������
����ø�岽�ץ��ȤǻȤ����������ե��륿�������ߤ��������ܴ�Ȥ��ʴ����Ƥ��Ȼפ����ɡ��ɤ����Ƥ������������Τ������������ʤ��Τ��ʤ�
���礻��ϥ����ޥ����ʤΤ���
40. ƿ̾������
��39
���줬���̿ͤ�̵�����ۤ����ȤǤ�פäƤ�Τ���
���������ǤϤɤ���äƿ����������Ȼפä����ɡ�ư���褯����ȳ����ۤ��夲�륫���ܥ�ʥΥ��塼�֤μ��Ϥ�Ʃ��������ʤ�äƤ��ꡢ�������ȯ�����夬ή������Ƥ��롣
�����ӽФ����Τϱ��ʤ��Խ�ʪ�����ǡ�����ƴ����Ǿ�ȯ���ƴ���������륷���ƥࡣ
��������˲��Ū��������
41. ƿ̾������
��21
��������ä����åפ˥��Υ��μ�����������ʬ���ޤ��Ƥ����ʤ�����
�������鵤�������Ѥ��ƿ夬����ʬ�ޤ����߹���Ǥ���
���������Ѥ��ƿ�ȱ�ʬ����ʬΥ����ʬ�ϻ��α�����߽Ф�
��ʬ�Ϥޤ����åפ��᤹�����äƻ��ʤΤǤϤʤ����Ȼפ���
����Ǽ����������������٤����դ����Ƥ뤬�����֤λ�����⿷��������˼���ؤ��Ƥ롣
�����֤�����ܵͤޤꤷ�ʤ��ǻ��ѤǤ������¸������äݤ���
42. ƿ̾������
�ˤ���ⲿ�⤫��ޤ��������ʤ����̣��������
43.
44. ƿ̾������
̤�褸����
45. ƿ̾������
>>3
���ǤȤäƤ�����鳤��ή���Ф�����ʤ���
46. ƿ̾������
��45
������ȴĶ������ˤʤ��
47. ƿ̾������
��3
�����ѤǤⲿ�Ǥ�Ȥä������������ʤߤ˼��곤�˰Ϥޤ�Ȥ����ܤϤ虜�虜��������̤�͢�����Ȥ���ǡ�
48. ƿ̾������
��21
�����Ǹ��Ĥ���̿���¤�Ǥϥ��饹�Υɡ���֤���Ϫ����ϤDz���ĤǤ����͡�
��Monash Xiwang Zhang�פǸ���������ȥɡ���Ĥ����֤ȶ������Ǥä��̿�����̰����Ǹ��Ĥ����ޤ���
��Monash chemical engineering professor Xiwang Zhang�פ��ȷ�̾�̤�ɽ������ޤ���
ͭ�����������Τؤ����ܤǤ��ʤ����ᤳ�줬�¸����֤ʤΤ��ǥ����ץ쥤�ʤΤ��������Ǥ�������ζ�����ˡ�ϸ������ˤ�Ƥ���ޤ���ľ��1�ߥ���ʻ���ɲ���صۤ��夲�Ƥ���褦�Ǥ����̿����Ȥ⤦�����������ʤΤ����ɡ�����ܤ�����ʬ��ľ�¤ʤΤ��ʡ�
49. ƿ̾������
���Ϥ�Ȥ�ʤ��Ǻ�ư�������֡��Ǻ���Ȥ߹�碌��ᥫ�˥���ι��פǡ��������ͥ륮��������Ư���褦�����֤������Ƥ���Ȥ����Ȼפ��������ιԤ��˶�Ť��Ƥ椯�����ͥ륮������ξ��ʤ��ƥ��Υ������˴��Ԥ��롣
50. ƿ̾������
��37
����������ˡ
51. ƿ̾������
��42
���äƤ����Τϡ����ѤȤ������Ѥ���Τϡ����Το��ѡ���������٤�����ʬ�Ϲ����Ѥ��Ѥ�����Ȼפ�������ɡ�
52. ƿ̾������
�������ʡ�����
���եꥫ�Ȥ�����Ȥ�������������в������ߤ�����
53. ƿ̾������
��25
����������ʬ���ꤲ���֡�����ɤ��äƤ롪��
54. ƿ̾������
���夽�Τ�Τˤ�ޤ��ޤ�̴�������
�Խ�ʪ�ޤ��
55. ƿ̾������
����ư����ȿ�ϲ�����Ƥʤ���ʤ���
�����鳤��ۤ��夲�ƹ���������夬��ȯ���ƿ�ʬ�ʳ����狼������Ƥ�������
�����ϸ���Ǯ���Ѵ������Ψ�������Ȥ������Ǥ�
56. ƿ̾������
>>11
����塢�����ͤΰ��߿�乩���Ѥ˺�褵��³������Ϥɤ��ʤ�����������ˤ���ν���(��ʪ)�����������ɡ�
�ɤ��ˤ�ʤ�ޤ��ɣ���
57. ƿ̾������
>>25
��22����ʤ����ɵ������狼���
�ߤ���ϼ��Τ������Ѥʥ����ȤФä�����������
����ä�Ĵ�٤�������Ư������г�����κ��ʤ���Ѥ��������ƽ���ʤ���
58. ƿ̾������
��50
�ϥ���ϥ���ե�ϥ���ۥ���
�������ʤ�
59. ƿ̾������
�ɥ館���Ϥ��������
60. ƿ̾������
���ˤ�äƤϡ����ब�������ͭ��ʪ�������̤˲�����줽������
�����ʤ�ȿ��ѤˤϤʤ�ʤ������ष�����δĶ�Ĵ���Ȥ��ơ����ǡ��������뤫�⤷��ʤ���
61. ƿ̾������
��24
�Τ����峤�Ǥ���
62. ƿ̾������
������ȱ��ʳ����Խ�ʪ���ޤޤ�Ƥ��������顢����DZ���������Ƥ���ߤ����Ϥʤ��ʤ�
63.
64. ƿ̾������
�ष������α�ʬǻ�٤���ޤäƤ��Ƥ���ΤǴĶ�Ū�˹��Թ�
�ڤ�ְ����ΤȰ��
65. ƿ̾������
��58
�ִ���ϥ�С����ס�
�����Ĥ���ή��˾�äƤ��ޤä���
66. ƿ̾������
��ǧ����������ΤϤ����Ӥ��Τϲ��ʤ��������
67. ƿ̾������
�ϽФ������ä��Խ�ʪ�ޤ�Ǥʤ��Τ��ʡ�
���Ѥˤϰ��ֳݤ��ꤽ����
68. ƿ̾������
���ʿ���� �ν��Ǥ���ʤ� ������Υޥ������ץ饹���å��� ���ο�� �Ĥ��Ƥ��ʤ��Τ��ʡ�
69. ƿ̾������
��5
�褯�����μ���ä�����뤱�ɡ����ܤǤ�¿���οͤ���Ϥ��Ŀͤdzڤ��ߡ�
���˥���Х���Фȥ�����Ȥ��������椤�����˥��Ѥ��äƤ뤳�Ȥ�ͤ���ȡ�
¿�����¤������Ȥ��Ƥ⡢����ʬ��;���̤Ϥ���Ȼפ���
�褯������͢��ʬ�ǿ��͢�����Ƥ��뤳�Ȥˤʤ�Ȥ��������ɡ���������������硢
���λ��Ѥ�����Ϥ䤬���ڤ˴Ԥꡢ���ؤ���äƤ����櫓������
���ιͤ����äơ�����ä�̵�������ʤȤ�פ���
��ɤνꡢ���μ���äȤ����Τϡ����ä���Ȥ����������äФ���ǡ�
���ͤȤ��Ƥɤ����٤ο����Ѥ��Ƥ���Τ������Ƥ���Τ��Ȥ��ä��٤����ǡ�����ȼ�ä�����ȯɽ�Ȥ����ΤϤ���Ƥ��ʤ��櫓�ǡ��ʤ�Ȥ�����ʤ��äǤ���
70. ƿ̾������
��66
�ɤ��ˤ����ƥޥ���Ȥ��ꤿ���ͤ��פ��Τۤ�¿���ߤ����Ǥ���
�ⶵ�������ʤ�Ȥ���������Ǥ��ʤ��ͤ����Ǥ�
71. ƿ̾������
���쳤��˴ޤޤ��ޥ��ͥ�����Ȥ��β���ˤ�Ȥ����ޤ�����
��dz���ޥ��ͥ�����γ�ȯ�������˸������������
72. ƿ̾������
>>45
��ʬǻ�٤����ä������ַϤΥХ����㤯����ˤʤ�ʤ�����
73. ƿ̾������
��50
�ɤ����դ�����ˡ�ʤΤ���