 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見るわずかにズレているかもしれないが、ギザの大ピラミッドは紛うことなき古代エジプトの工学技術の結晶だ。
古代エジプト人がピラミッドを東西南北にほぼぴったりと配置したその方法はこれまで分からなかったが、ついに明らかになったかもしれない。
―答えは、秋分である。
秋分は夏至と冬至の中間で起きる、昼と夜の長さがほぼ同じになるように地球が傾くポイントのことだ。
ほぼ完璧に配置されたギザの大ピラミッド
およそ4500年前、クフ王によってギザの大ピラミッドが建造された。エジプトの三大ピラミッドのうち、最大のものがギザ台地にある高さ138メートルのクフ王のピラミッドで、これは世界の七不思議にも数えられている。
これまでの調査で明らかになったのは、大ピラミッドが非常に高い精度で建造されているということだ。それは1度の15分の1という精度で東西南北にぴったり向けられている。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見るカフラー王のピラミッド(ギザ)や赤いピラミッド(ダハシュール)もまた高い精度で配置されているが、アマチュアの考古学者でありエンジニアのグレン・ダッシュ(Glen Dash)氏によると、これらの3つのピラミッドには同じ間違いがあり、わずかに反時計回りに東西南北からズレている。
過去1世紀以上もの間、古代エジプト人がピラミッドを正確に東西南北に合わせることができた方法について諸説が提唱されてきた。だがダッシュ氏が新たに発表した論文によれば、彼らは秋分を利用したらしい。
コネティカット州で行われた影の位置確認
2016年9月22日に米コネティカット州ポムフレットで行われたダッシュ氏の実験では、「ノーモン」と呼ばれるロッドを木製ステージに設置し、1日を通じて移動するロッドの影の位置に印をつけていった。
すると秋分では、影の先端がまっすぐにほぼ完璧な東西の線を描く。ただし反時計回りにわずかなズレが生じる。
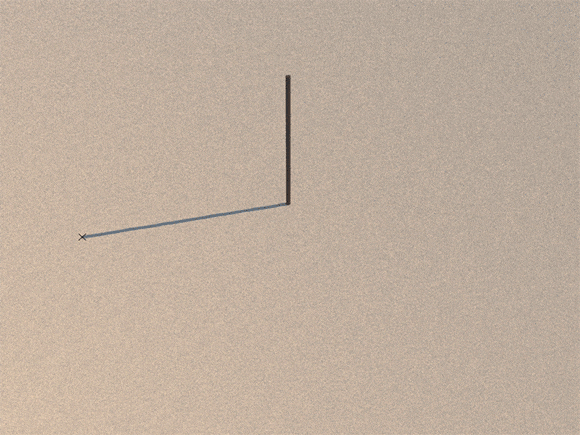 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見るこれは大ピラミッド、カフラー王のピラミッド、赤のピラミッドに見られるズレとちょうど同じものだ。このような影の移動の仕方は秋分における地球の傾きによって生じている。
ダッシュ氏の実験はアメリカで実施されたものだが、エジプトのギザでも同じことができる。これを行う上で理想的なのは、日中のギザのように雲一つない晴天の日だ。だが、たまに雲が出たところで問題なく使えただろう。
 この画像を大きなサイズで見る
この画像を大きなサイズで見る古代エジプト人は本当にこの手法を使ったのか?
実験では確かに上手くいっているようだが、実際に古代エジプト人がこの手法を使っていたのかどうかまでは分からない。
ここ数十年の研究からは、ピラミッドの配置には太陽や星を利用した複数の手法が採用されていた可能性が示唆されている。
残念ながら、エジプト人は実際に採用した手法について現代に伝わる記録を残していない。彼らが寺院やピラミッドを配置した方法について技術的な説明をしてくれる工学的文書も建築計画も、これまでのところ一切発見されていないのだ。
実際に複数の方法が採用された可能性があることはダッシュ氏も認めている。
だが秋分法ならではの利点もある。簡単なのだ。提唱されている他の方法は手間がかかり、より複雑なのが普通だ。
「コンセプトの面でも、実践の面でも、これ以上シンプルな方法は思いつかない」というのがダッシュ氏の見解である。
この論文は「The Journal of Ancient Egyptian Architecture」に掲載された。
References:egyptian-architecture / skyなど/ written by hiroching / edited by parumo
















適切に秋分の日を特定するのもこれまた難しいと思うのだけど。
※1
大抵の大昔の文化圏でそれくらい分ってるよ
昔の人間ばかにしすぎ
棒の影が一番直線的に動くのが秋分の日なんだろう
普通にコンパス使ったんやろ
※3 ※5
磁石の方角と、実際の方角はちょっとズレてるから…
一年間影の記録を取るってものなかなか大変だろうて
普通に地図と方位磁石持ってた可能性
南中の影を記録して南北にするだけではいかんのだろうか
毎日影の長さを測って、最長と最短のちょうど半分の日が春分と秋分だ
天文測量は神官たちの秘事で文書には残さなかったのかもしれないね。
そもそも一個の時に一番効果が出る金字塔を欲張って複数建てた。
失った力を
力の源泉のオリオン座の配置にすれば良いかと言うとそうでは無い。
ピラミッドは(人々のためになる)物理的な変化を起こします。
気象コントロールシステムでもあり暦司が出入りしていた。
ピラミッドは王墓ではない。(古代エジプトに身分制度は無い)
ピラミッドは、それ自体が異星の科学(物理)である。
正しくは「▽」(水=巾=女)・・・不可視の門
金字塔は「△」(火=日=男)
この二つの「kin」三角形を重ねると「六芒星」(✡)となります。
ピラミッドの上には目に見えないゲートが開かれており(北半球でのみ)
本来の役目と別に
環境を変化させ、生命に住みよい環境を作るシステムでも有る。
※9
中の物が腐らなくなるとか結構オカルト的な話多いよね
ファラオの呪いなんかも科学的に結果が判明してるけど、実際それを狙って起こせるなら相当計算が必要になるし。まだまだ古代の叡智はロマンに溢れてる
砂漠のど真ん中にあるのに枯れない水源あるし、東洋でいう風水とかそれに近いものも取り入れてる感がかなりあるね
雨期の季節なら計測してたしこれなら
簡単だと思うけど
むしろもっとものすごいテクノロジー持ってた可能性も高いよね
今わかるのはこれぐらいってだけでさ。
暦を完全に把握していたマヤ文明とか、かなり早い段階でプラチナを加工していたアステカ文明
滅んで行った文明ごとに滅んだ技術がありそう
古代人のテクノロジーのすごさはあきらかにぶっ飛んでるし、
現代から文明人が滅んでセンチネル島の住民が生き残ったみたいな状況が起きたのかなとかいろいろ妄想してしまうわ
エジプトの暦に対する執着は凄まじいからね
毎年ナイルが氾濫する時期が一定っすことを突き止めたり日々の天体の位置の違いにも気付いてた 絶対権力がもたらした功績だよね
日時計 百葉箱 なつかしわぁ
いや、何を今更な周知の仮説の一つだろ、それ。
こういう観測は毎日記録しないといけないと思うんだが
記録が残ってないという不思議
※16
日本のように長い期間一つの民族が、一つの家柄を象徴とあがめてきた土地でも無い限り
民族と王家の入れ替えで、前民族と王家の知恵なんて簡単に損失し、失われていく
そして日本でさえも墳墓の盗掘が後を絶たなかったのに
エジプトならば王家の墓などがどれだけ盗掘されたのかって話にも繋がっていく
※16
記した媒体が破壊されでもしたんだろ
色んな説が出てるけど、ピラミッドの作り方の記述とかが見つからない限り、正解は出ないかもしれないね。
でも、少なくとも宇宙人が指導したとかいうよりは、昔の人の創造力を認めてる点で好感が持てるし、説得力があると思う。
古代人の知恵を現代人があーでもないこーでもないと分析するって面白いね
なんで「秋分と春分」じゃなくて「秋分」限定なんだろ
元ネタの論文(確かに文中に”autumnal equinox”と記述されてる)も読んでみたけど。俺の英語力ではさっぱりわからん
※20
元ネタの文章は、大部分では
春秋を指定しない”equinox”(昼夜平分時)を使っていて、
“autumnal equinox”(秋分)とあるのは、この論文の筆者が
「…てなわけで、どの程度の精度で実用に耐えうるか
実際の技術的誤差を測定する検証実験をやってみました」
のあたりのみだよ。
例えばピラミッドが作る影の先に道路なりモニュメントなりのまっすぐ走っている構造物があったとして、毎年一度の秋分の日にその構造物の上を影がピタリと動いていくと、天文をも従える王権や神権の偉大さをはっきりと指し示すことができる
実際に日時計が使われていたエジプトでは、ピラミッドにそういった天体アトラクション的な役割は当然あっただろうと思う
ギザウレシス!
ピラミッドは未来を予測するスーパーコンピューターだったんだよ!!
古代エジプト人が建築方の一切を残していないのは自分で作ったわけじゃなく本人も分かってないからじゃね?
ピラミッドは太陽神ラーの祭壇でもあるだろうから、太陽の動きを元に設計されたというのが一番説得力があるかな。東西南北に方位が合ってるのも、方位を意識して合わせたからではないはず。あくまで太陽の動きが重要なわけで。そもそもその当時に磁場としての東西南北という概念はなかったんじゃないかな?
まあ、春分とか秋分の太陽の位置を目印にしていた事は予想が付くけれど、棒を立てて影の先端を連続記録する方式を使っていたかどうかは判らないと思う。当時も日時計は有ったと思うので、この様な方式を使っていても不思議はないと思うけれどね。個人的には、春分とか秋分の太陽が出る時に棒を立てておいて、そこから一直線に延びる影を基準にしたのでは?とか勝手に予想していたんだけど、その方法では駄目なのかい?(それで時計方向のズレまで出るのかどうか知らんが)
北極星を目安に誤差も加味すれば真北が出そうなきがするが
それにしても、人間の経験則ってのはすばらしいね。
ヘレニズム期の学者……確かエラトステネスだったか……が、
2地点の影の長さだか角度だかを測定して、地球の外周の長さを出してたな
求めた解も時代もまったく違うけど、エラトステネスが活躍したのもエジプト(アレクサンドリア)で、
太陽の影で天体関連のことを測定する伝統みたいなのがエジプトにはあったのかも
ローマに侵略された時、相当数の書物が焼かれたらしいからなあ…
それらが残ってたら歴史が変わってたかもしれない
※33
案外、アレクサンドリア図書館の未整理コーナーにポンと積まれてたのかもしれないね。
つくづく英知の損失だわ
影じゃなくてどうあの巨石を内部構造を維持しながら組み上げたかが知りたいのです。
四半世紀近く前だが、登頂した。
空撮の様に、頂上から見下ろす。
ピラミッドの謎は建造した石工たちも含まれるんだよね。
彼らは古王国の中期、いきなりスキルカンスト状態で数々の巨石建造群を建設し、
その後、徐々に技術が忘れ去られていく。
それ以前もその後も、石工たちは新しい工法を生み出さない。
これは連綿とした積み重ねによる進歩が普通の他文明に比して特異だ。
顕著なのは土台の基礎部分や重量を支える柱に対する無頓着さで、重量のかかる部分に柔らかい石灰岩を使ったり、基礎部分に瓦礫を放り込んでその上に建てたり、すでに出来上がってる神殿の柱を流用するため抉ったり引き抜いて崩壊させたりしている。
だから、多くの神殿やピラミッドは現在ほとんどが倒壊している。
極めて精緻な計算に基づく設計とは、どうにも不釣り合いな原始性とずさんさが研究者たちを悩ましてきた。
要するに、ピラミッドの建築技術は「借り物」だった可能性が高い。
それがシリアからやってきた支配層の持っていたものなのか、天才によるものか、宇宙人によるものかはわからない。
ただ一つ言えることは、ギザのピラミッドと同じ石積み技術は全く同じものが世界中にあって、どうやらその技術伝播を担う何某かが存在していたことは確実であるということ。
※36
石工といえばふり~め(ry
な、なんでもない
※36
設計もおそらく個人か親子の天才がやっていたんだと思う
3大ピラミッドだけ突出した完成度なのは国力の衰退だけじゃなくやれる人がいなくなったのも大きいと思う
※36
温暖期が終わって海退して九州に匹敵する面積の干潟が出来て
それを干拓して農地にする為に灯台が必要で
「表面に光をよく反射する石を付けたピラミッドを三つ作れば自分が干潟のどこにいるか分かる様になるから工事が進むな!」
って考えられたからギザの三大ピラミッドが作られた説がある(竹村公太郎の仮説。エジプトの博物館の館長に褒められたとか何とか)。
だから三大ピラミッド以降のピラミッドは富の誇示(ステータス?)とか用になって必要性が薄れたから技術が下がっていったんじゃなかろうか。
ちなみに、クフ王のピラミッドも重量軽減の間は失敗して一部崩壊している。
このため、上部は内側に沈み、勾配が下部と違う。
重量計算ができないまま、あの巨大な石を積み上げたというのは違和感がある話だ。
これこそ、その時代の偉大なファラオのなせる業である。
バカですまんが、日の出と日の入りで東西の線てできんのかしらね?
やっぱり朝は太陽が出てると、その方向にうつ伏して礼拝して
夕方も同じように礼拝するんだろうか
日中も棒を立てて影の位置で平伏して礼拝してそう
イスラム教の神様が動いてるバージョンだね
ピラミッド建設時代の北極星ツバン(αDra,HR5291)と同赤経,若しくは 180°反対の星を全天で探すと,この時代にツバンとアンタレス(αSco, HR6134)はほぼ同じ赤経にある。
クフ王ピラミッド(約 3 分の西偏)の推定建設年代(BC2552)頃にツバンは天極から約 1.4°も離れているが,アンタレスの南中時にツバンを見た方位は真北から 1.2 分東偏となる。