
���ʹ֤���⤢�ä��껦�����Ȥ��Ǥ���ۤɤ���ʪ���ߤ��Ƥ�����¸�ߤ���櫓�ǡ���Ϣ�����ˡ��������ϵ�����ַϤ�����äƤ���Ȥ��äƤ����ǤϤʤ���ʪ�����ʤΤ���
������ʿ�ʪ����ˤϡ���ˤ��Ѷ�Ū��ư����Τ�¸�ߤ��롣���ʪ��ޤᡢ�����Ǥ�ư������ȯ��10�ο�ʪ�Ƥ�������
10. ���̥���
Plantas carnivoras, Utricularia.
References:Predator plants: how N.W.T.'s carnivorous vegetation snare their prey | CBC News
���츫ʿ�¤��Ӥ��������̤β��ˤ�����ǹ����̩�ʥͥåȥ����ĥ���餵�졢�����Τ�ʤ���ʪ�����äƤ���Τ��Ԥ������Ƥ��롣
�����ʪ��Φ���Τ�Τ�¿���������̥����ή���˳���������ʳ�ʪ��˭�٤ˤ���������˿����롣����ϸФο�ʪ��������ä���Ȳ���伾�Ϥʤɤذ�ư�������Ǥ�������dz�ʪ��ò�����Ѥ뤳�Ȥ��Ǥ��롣
�����Ϥʤ�������Ū�ʱ��ܤϸ������ȤȤ�������¤���롣���졼�����֥������ȤΤ褦���礭�ʥ��̥������֤��ȡ�ñ�ʤ뺫��侮���ʹó�������ä��礭�ʾ����Υإӥȥ�ܤ䥪���ޥ��㥯������館�뤳�Ȥ�Ǥ��롣
����ξ�˲İ��餷���֤�餫���ơ��ʹ֤��ܤ�ڤ��ޤ������ʴ��ưʪ���������⤹�롣
9. �ॷ������

����ʴ�ϡ�����˸���ä����̤�����ˤ�¿���ϫ�Ϥ��פ��롣�����Ǥۤܥ������ȥ�ꥢ�ˤ���ʬ�ۤ��ʤ��ॷ�������ϡ�����κ�����Ф�������Ū��ȿ��������ʴ�����Ф���Ȥ�����ʴ��ˡ��ȤˤĤ�����
����ॷ�������˾��ȡ��ޤ�ǽ��������뤫�Τ褦�˥����٤��ǤĤΤ�����������Ϻ��������ǤϤʤ���̵������ʴ��ʤ���Ĥ��뤿����������٤��Ǥ��줿����ޤ��̤β֤˻ߤޤ�С�����Ǥ�Ǥ�����ʴ����λ���롣
�������Ȥˡ��ॷ��������Ⱦ������ȹͤ����Ƥ��롣������ʴ�ޤߤ�ˤ�����Ȥ߰ʳ��ˤ⡢�֤�¦�ˤϤ��äĤ��䤹�����Ӥ������Ƥ��ꡢ���֤���о��������櫤ˤ����뤳�Ȥ��Ǥ���ΤǤ��롣櫤ˤϤޤäƻ�����λ��ò��ۼ������������٤α��ܤ�������褦����
8. ���ĥܥ�����

�����ĥܥ������ư�����ꡢ�Ѥ��ä��Ĥ����ꤷ�ʤ�������������͵��Ѥϸ�������Ĺ�����Ӥ��ԤˤϥĥܤΤ褦�ʤ�Τ��������졢��������̣�������ʱ��Τ�ί��롣
�������Ĥˤ⤳�����⤦�Ȥ�������ʪ������Ƥ��ޤ��С����ȤϾò������Τ��ԤĤ����ʤ����Dz�Τ褦�˿ʹ֤���߹���褦�ʤ��ȤϤǤ��ʤ�������������ʪ�ˤȤäƤϴ����ˤޤ�ʤ�¸�ߤ���
���ĥܤ�ί�ޤä����Τϳ�ʪ�Ӥ�������ǤϤʤ����ͥХͥФ��Ƥ��ꡢ�������ʪ��ƨ���ʤ�����Τ�ΤǤ⤢�롣
���ä������Ȥˡ��緿��Nepenthes rajah�ˤ�ʤ�С�����Ф��꤫�ͥ��ߤޤ��Ῡ���뤳�Ȥ����롣
Carnivorous Plant VS Mouse!
�����ˤˤ��뤳�ȤǤϤʤ�����Ӯ����γ�ʪ���緿��ˤȤäƤϤ������ܸ��Ǥ��������ޤ�����α��Τ����Ѥ�ѻ�����Ƥ��롣
7. ����������
References:Sensitive Plant - Mimosa pudica - Care Tips, Picture
����ʪ�Ȥ��Ƥϰ����®�����դ��ळ�Ȥ��Ǥ��롣����ˤ��դ���ʬ�˿����������Ǥ������ͥ�ꥰ���Ȥ�����̾�Ǥ��Τ�졢�桦���Ƹ����Ǥ��롣��¦���դ��Ĥ����ͻҤϥɥ�ޥ��å�����ưʪ�Τ褦�ǡ���Το��ä���ҤΤ褦�ˤ����ޤ�롣
�������줿�ɷ���դ��Ĥ�����������Ū�Ϥ褯ʬ���äƤ��餺�����٤ƿ�¬�ˤ����ʤ���
������Ȥ��Ƥϡ��դ٤��ʤ��褦�ˤ��뤿����Ȥ����Ķ��ǿ�ʬ�ξ�ȯ���ɤ�����Ȥ��ä���ͳ�����Ƥ��롣鮤��ڤʤɡ���ʬ����礭�ʿ�ʪ�β��ǰ�ġ��ǽ�Ϥޤä����Ĥ˿��Ӥ뤬���䤬�Ʋ����礦�褦����Ĺ����Ĺ����1.5��ȥ��ã���뤳�Ȥ⤢�롣
6. �⥦����
References:All About the Sundew Plant
����ʢ�����������ˤȤäƤ����������������ʤ���꤫�⤷��ʤ�����ˤ�������٤Ƥ��ϰ��ʬ�ۤ���⥦�����ϡ��ƤΤ褦�ʤ�Τdz�ʪ�Ӥ��롣
�����ä��ꤽ��˿���Ƥ��ޤ��ȡ��ͥХͥФ������ΤǤ٤ä�����������������ơ��ò�����Ƥ��ޤ����Ԥˤ������������Ӥ����ꡢ����ϱ��Τ�ʬ�礹�뿨���ʤ���Ƥ��롣
���ܤ������ˡ����ʻѤǤ��뤬���������館��ˤ��ǤäƤĤ������Ť�����ʪ���ϳ�ʪ�Ӥ����Ʊ���ˡ���ͤ���ҤȤ��Ƥⵡǽ���롣
�������⤽���ˤϹ��Ǥ��ޤޤ�Ƥ��ꡢ��ͤ��줿������Ϥ���������ʬ��դΤ������ǡ��⥦�����ϸ���������ȥ��饭��ȵ�����
�����Τ���˰�Ƥ뤳�Ȥ����ˤ⤫����餺����ݲȤ���͵��Ǥ��롣���ब˭�٤�190��ʾ�⤢�롣¿������Τ褦�ʻѤ�����3��ȥ�ˤ�Ӥ�Drosera erythrogyne�Τ褦�ʼ�⤢�롣
5. �ॸ�ʥ�
References:The Carnivorous Plant FAQ: Aldrovanda: the waterwheel plant
�����̲��Ǥϡ����ޤ�ʹ���ʤ�ʤ����ʪ����ʪ����館�褦�Ȥ��ä���Ư���Ƥ��롣����Ǻ�ά���餻�뿢ʪ�ϥ��̥�������ǤϤʤ��Τ���
�������Ȥˡ��ॸ�ʥ���դ�����ηԤȤ����֤Τ褦�ʹ�¤�Ƥ��ꡢ��̾�Ϥ���˰���ǥ�����������������ץ��ȡʿ����ˤȤ�����
���ϥ��ȥꥰ���Τ褦�������դǶ��äƤ�����ʪ�ץ�ȥ���Ῡ���롣���եꥫ���衼���åѡ����������������ȥ�ꥢ�ʤɡ��������ϤǸ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣
����־��ι�¤����ü�ˤĤ��Ƥ����դ���¦�˴����Ӥ������Ƥ��ꡢ�����˳�ʪ�������ȡ����ä��դ��Ĥ��롣
������®�٤�®���������˳��������֤����Ĥ���ޤǤ�4ʬ��1�á�2ʬ��1�����٤���������ʤ����츫�ҥ�ॷ������֤ˤ⸫���뤬�����ο�����Ῡ�ԤϤ��ä�ͭ̾��Φ��������ϥ��ȥꥰ���ζ���Ǥ��롣
4. �ޥ��ϥ�
References:Telegraph Plant l Astounding Leaves - Our Breathing Planet
�ޥ��ϥ��ϳ�̾��Codariocalyx motorius�Ȥ�����motorius���ԻĤʱ�ưǽ�ϤΤ��Ȥ�ؤ��Ƥ���Τ��������γ����ϲ�����ů��̵�������ο�ʪ����
�����������줬ư���Ƥ���Ȥ�����С��ܤ�Υ���ʤ��ʤ�����������ĤϤ��졢���������¤���Ӥ뤿���ǽ�ϤǤ��롣
��Ǯ�ӥ����������ǡ��������ܤdz�ǧ�Ǥ���ۤɤ�®�����դ�ư�������Ȥ��Ǥ��롣�ԤϤޤä����˿��ӡ���β֤�餫���롣
���ʱ߷����դˤϤҤ��Ĺ��¦���դ��Ĥ��Ƥ��ꡢ�ޤ�������Ƥ��������פΤ褦�����ۤ�ư�����ɤ���
���٤뿢ʪ�Ȥ��Τ��Ƥ�ޥ��ϥ����ǽ�˵��Ҥ��줿�Τ�1880ǯ�Τ��Ȥǡ����ҼԤϤ��Υ��㡼�륺������������Ǥ��롣���̤ˤ�Ǯ�ӱ��Ӥ��˿����롣�����Ǥ������ؤι⤤��ʪ�����������ʤ���Фʤ�ʤ�����ưǽ�ϤϤ��������Ķ���Ŭ��������Τ���
3. �ƥåݥ�����
References:Squirting cucumber | plant | Britannica.com
������ʤ���Ǥ������μФ���Ԥ��ƥåݥ�����ϡ����ɼ�˼�����餹���Ϥ줿�ƥåݥ�����Ϥ���̾���̤ꡢ���Τȶ��˼��ͽФ���ΤǤ��롣
�����μ����ƤΤ褦�ʼ¤ϼ��6��ȥ�����Ф����Ȥ��Ǥ��롣
������ʤ���֤Ͽ��٤����Τ�¿�������ƥåݥ�����˼��Ф��Τϻߤ�ۤ����������������������ʹ֤����ˤ���л�̲�ǽ���⤢�롣
���Ӥ�ʤ��줿���äݤ������ǡ��礭����60��������餤�ˤޤ���Ĺ���롣�¤��礭����5��������٤������泤��ߤδ����ϰ踶���ǡ����δ�̯�ʷ����椨�˱�ݥե���ˤϿ͵�����
2. �ϥ��ȥꥰ��
References:Facts About Venus Flytraps
�����ʪ����̾��Ȥ⤤����ϥ��ȥꥰ����
���ͥХͥФ���Ǵ�դȻ��Τ褦�ʹ�¤�ǡ��ϥޥ���Τ褦�˳�ʪ����館�롣�ɤ����ܤdz����դ�ưʪ�Τ褦�ˤ⸫���롣
����������Ǥʤ��������ʥ��������館�ƾò����Ƥ��ޤ����̥���ꥫ�μ��Ϥ������Ǥ��ꡢ���㡼�륺�����������������ǹ�ζðۤ�1�ġפ�ɾ���Ƥ��롣
���⤵12������ۤɤǡ�櫤���ʬ�ˤϥ��ѥ����Τ褦�ʡɻ��ɤ��¤�Ǥ��ꡢ��ޤ�����ʪ���Ĥ������Ŵ�ʻҤ�����̤�����
��櫤��������ʪ�Ͼò��դǾò����졢���θ�Ƥ�櫤��������Ĥä��������Ǥ��Ф��������ʳ�ʪ����ͤ������롣�ϥ��ȥꥰ�������˸�������ʪ�˿����줿����������褦�ץ�����व��Ƥ��롣
������Ϥ��ޤ������������夷�����ߤʤɤ�ȿ�����ʤ�����λ��Ȥߤ���1���ܤλɷ���Ĥ��������Ԥ���2���ܤλɷ�Ǽºݤ�櫤��ư������3���ܤǾò��ץ��������Ϥޤ롣
1. �ޥ�

������Ȥ��ƿƤ��ޤ��ޥ��Ǥ��뤬�����Ĥϼ��9��ȥ�����Ф�ǽ�Ϥ����롣����ʤ�Τ��ܤ����ä������Ѥ���
���̥���ꥫ��4�����1����ܤ�1�郎ȯ������Ƥ��롣������ؤ��㤤�ФߤΤ褦�ʳ�����������ˤ�10��ȥ����ؤФ���⤢�롣
�����ֻ����������٤����̥���ꥫ�ǤϺǤ��٤��֤�餫���뿢ʪ�Ǥ��롣�ޤ����ͤ����Ϥ���ޤǤˤ���֤������ꡢ1ǯ�⤫���롣
�����Τ���ˤ���ǯ�γ��֤���ǯ�Υ��ͤ����Ϥ��¹Ԥ��뤳�Ȥ⤢�롣���ͤν����������ȡ�����ޤǤ��ߤ���줿��ư���ͥ륮���������褯�������졢���ͤ����Ф������줬�Ƥ��Ф�����ͻҤϥ���������ƤΤ褦����
written by hiroching / edited by parumo
���碌���ɤߤ���
 �������ȥ��顼�������ʹ֤ʤ�Ƥ��ĤǤ⻦���10��ο�ʪ
�������ȥ��顼�������ʹ֤ʤ�Ƥ��ĤǤ⻦���10��ο�ʪ ���ä���ʤ�����ɤ����俩�ѡ����������ǡ�����������䤳������ʪ8��
���ä���ʤ�����ɤ����俩�ѡ����������ǡ�����������䤳������ʪ8�� ���줤�ʲ֤ˤϻ����ϡ��ͤ��˻�餷���ۤɤ����Ǥ����10�β�
���줤�ʲ֤ˤϻ����ϡ��ͤ��˻�餷���ۤɤ����Ǥ����10�β� ��ʪ���äƹ��⤹�롣�����뤿��˿�ʪ���Ȥ��失����̯�ʻ����Υƥ��˥å�10
��ʪ���äƹ��⤹�롣�����뤿��˿�ʪ���Ȥ��失����̯�ʻ����Υƥ��˥å�10 ��ʪ�λ��Ķ���������ޤ��ޤ��ȼ´��������Ƕ����饹�����ǿ�ʪ�μ�갷����ˡ���Х����ϥ����ɡʥ��ʥ���
��ʪ�λ��Ķ���������ޤ��ޤ��ȼ´��������Ƕ����饹�����ǿ�ʪ�μ�갷����ˡ���Х����ϥ����ɡʥ��ʥ���







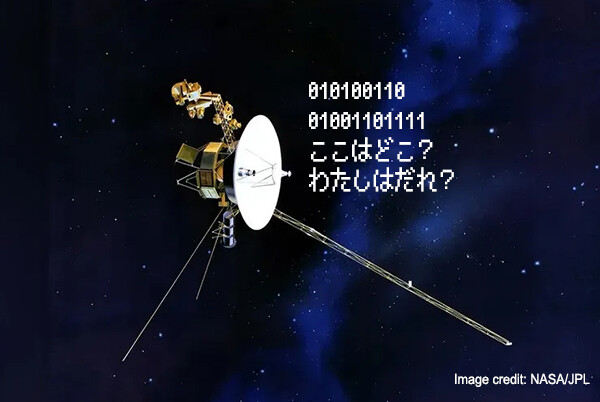
 6175
6175 313
313 11
11 37
37



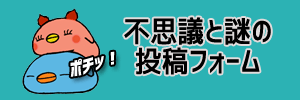





























































������
1. ƿ̾������
�ƥåݥ�����ࡼ�ӡ��ġĤ���ʸ��̲������ʤ�
2. ƿ̾������
�֥��̡ס֥���פȸ�������줫�Ȼפ�����֥ॸ�ʡס֥�פθ����ì���ʤ���ȵ����Ĥ���
3. ƿ̾������
�ӡ�����˸��������͡�
4. ƿ̾������
�ƥåݥ�����դ�����ʣ���������������������������
5. ƿ̾������
�ϥ��ȥ���Ȥ���ư�����ߥå����ο�ʪ��
���ߤ˳��������Ĥ����ꤵ���ޤ��ä�ͷ�����ܤ���
��ʪ¦�Ȥ��Ƥϥ���Ϥ��������ͥ륮����Ȥ��ΤǤ��ʤ����ô�ˤʤäƼ��
�Ǥ�ڤ����������äȤ����ʤ餤����������äȤ�����
6. ƿ̾������
���å����ˤ�˽����(�����ء�`)
7. ƿ̾������
��ǯ�ν뤵�Τ��������ʪ�Ϥ����ä��衦����
8. ƿ̾������
���ĥܥ������ư�衢�ͥ�������ʤ�����
9. ƿ̾������
�ޥ��Ϥ����������������ڤ�����
�ޤ��������ǽ�Ϥ�����Ȥϻפ�ʤ��ä���
10. ƿ̾������
��٤Ƥ���뿢ʪ�Ϥʤ���Τ�
11. ƿ̾������
���̥��⡢�ॸ�ʥ⡢�ɤä���ֲ����������Τ���ưʪ�פ�̾������äƤ�Τ�����
12. ƿ̾������
�ƥåݥ����꤬���뤵��
13. ƿ̾������
�ޥ��ϥ���ư��ϡ��������ץ��ʤΤ����ºݤ�®�٤ʤΤ����狼����˻��פ�̤��Ƥ����Ȥ��꤬������
14. ƿ̾������
�ϥ��ȥꥰ�⡢�ºݳ�ʪ�ᤨ�Ƥ�Ȥ����Ƥߤ����빽�����Ĥʤ���
15. ƿ̾������
ư�褬����Ƥ�衣
16. ƿ̾������
���粽�������Ϥ�ʼ��
�ȸ����ͥ���դ������ã�Ǹ���
17. ƿ̾������
���ʪ�����������Ĥ鲿�������ܼ���ä��Τä��ʡ������⡢�������ޤ����ݼ褹����ɤ���͡�Ū�ʹͤ��˻�ä��Τ�������
��¤������ˤ�����ƨ����ޤ��Ȥ������������ʤ���줽�����Ȥ������ԻĤ���ͤ�������
18. ƿ̾������
��8
�ͥ��ߤ٤�äƤΤ϶ˤ����˼�ä��ͥ��ߤ�
�����Ů��Ƥ�������������Ф�����Ǥ���
�����ϸƤӴ��ͥ��ߤ�̪��Ϳ���ơ�
�����ʵ�䤪���ä���ĥܤ���Ȥ����㤦�Τ���Ū�Ǥ���
ͭ��������ľ���㤦�Ȥ������Ǥ��͡�
19. ƿ̾������
�ƥåݥ����꤬���ä���ˤ����פ��ʤ���
20. ƿ̾������
�ɤ���Ť����������ʤ������ƥåݥ�����������
21. ƿ̾������
�ƥåݥ�����̲��ʤ�������������
��ʪ�äƤ褯���Ƥ���������������ǰ�ƤƤ���Ʀ�Ĥ������˸����äƤ��뤯����ư��������(�ۤ�ξ����ܤ�Υ���Ƥ����֤����餫�˸����Ѥ�äƤ�)���������Ĥ�������Ƥ����ʤäƿ��٤�Τ��ˤ����ʤä������ä����٤����ɡ�
22. ƿ̾������
������ �����ס��� ���äס��������ä�(�⤦�����͡�)
23. ƿ̾������
�����Ȥ������ʤ���ΤΡ��������������������˽����롣
�ޤ����������ʤä��襤��¤������ǽ���Ĥ�¤�ؤ����ޤ��ǡ�
24. ƿ̾������
�������Ρ֥ͥڥ�ƥ��դ��������